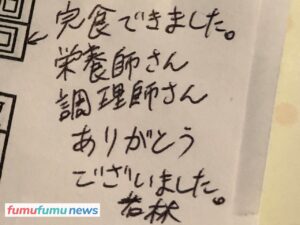「ジブリのアニメーションはやはり別格だ」。観るたびにそう思う。「作画がさすがだなぁ」なんて思っているうちに気づけばストーリーに没頭しており、結末で「何回観てもいいわぁ」なんて、ベタな会話をしてしまう。
しかし、かの宮崎駿も、いきなりスターダムにのしあがったわけではない。アニメ映画監督としてデビューしたころの彼は、興行成績がふるわず干されたり、「ロリコン」と呼ばれた時期もあった。
もしかしたら1980年代前半に彼の作品を観ていた人にとって、宮崎駿にはいまだにロリータ・コンプレックスのイメージがあるかもしれない。
では、なぜ宮崎駿は「ロリコン」と言われたのか……というか、果たして彼はロリコンなのか。2021年を迎えた今、もうあまり知られていない「宮崎駿ロリコン説」について語らせてほしい。
“カリオストロ”でロリコンブームが到来
宮崎駿が初めてアニメ映画監督を務め、そして日本に「ロリコン」というカルチャーを根づかせたきっかけになった作品は『ルパン三世 カリオストロの城』。今でも年に1回は『金曜ロードショー』(日本テレビ系)で放送される国民的アニメである。
「いや、ヤツはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です」という銭形警部のセリフは、もう永遠の流行語大賞。なんなら天敵のルパンよりかっこいい。クールすぎて、逆にちょっと腹立つレベルの名言だ。
また、崖の斜面……というか、もはや壁面を走る序盤のカーチェイス は、スティーブン・スピルバーグ監督が「映画史上、もっとも完璧なカーチェイス」と評した、なんて噂もある。
相手からの爆弾をがっつり食らってからの「面白くなってきやがった」という、射撃の名手・次元大介のセリフもよく知られている名言だ。次元とルパンは修羅場をくぐりすぎて、並のピンチはもはやエンタメ。危険を感じるセンサーが完全にぶっ壊れているのだ。
当時の『ルパン三世』はテレビアニメも好調で、1作目のアニメ映画『ルパンVS複製人間』もヒットした。ルパンが颯爽(さっそう)と泥棒をする様に、ファンは興奮していたのだ。
しかし、宮崎駿はそれまでのルパン像をアップデートすることに挑む。『カリオストロの城』では大泥棒・ルパンはあまり描かれていない。「王女・クラリスを守るロマンチスト」としてストーリーが進むわけだ。宮崎はデビュー作でいきなり大胆な改変を試みたのである。
駿が起こした“ロリコン・スキャンダル”
だが、ふたを開けると『カリオストロの城』は“爆死”してしまう。前作の『ルパンVS複製人間』は約5億円の製作費で、興行収入は9億円以上だった。しかし、同じほどの制作費をかけながら、収入は6億1000万円にとどまったわけだ。その結果、宮崎駿はこの後5年ほど、アニメ映画監督を干されている。
なぜ『カリオストロの城』は興行的に失敗したのか。その理由のひとつが「コアなオタク向けに作りすぎたから」だ。
宮崎駿はこの作品で峰不二子という永遠のヒロインではなく、クラリスという10代半ばの少女をメインに据えた。
設定として、クラリスはカリオストロ伯爵というオッサンに無理やり結婚を迫られている健気な娘だ。それをルパンが救い、守りきるのがメインの流れである。
作中でルパンが結婚式に乱入して発するセリフに「やかない、やかない、ロリコン伯爵、やけどすっぞ~!」というものがある。ここではっきりと「ロリコン」という単語を使っているのだ。ただ、’79年の公開当時、「ロリコン」という単語は、まだまだ市民権を得ていない。公言しにくいアンダーグラウンドな言葉だった。
そんなワードを宮崎駿は全国公開の映画で使った。クラリスは10代半ばであり、30代半ばのルパン を「おじさま」と呼び、抱きつく。ルパンは「ムホホ♪」とか言っちゃう。しかも、ラストにはキスを迫るシーンすらある。冷静に考えると、なかなかキケンだ。
“おじさんキラー”のクラリスは、のちに株式会社スタジオジブリの代表取締役社長に就任する鈴木敏夫が編集をしていた雑誌『アニメージュ』(徳間書店刊)で取り上げられ、大人気になる。人気投票では’82年、’83年のベストワンキャラクター部門で堂々の1位に。 コミックマーケットなどで、クラリスをモチーフとした「ちょっとあぶない同人誌」が売られ始める。
こうして’80年代から、ロリコン作品は限られたコミュニティでブームになる。コミックマーケットでは「少女をモチーフにした同人誌を売るサークル」に長蛇の列ができるようになり、一種のアングラなカルチャーができた。その火つけ役となったことから「宮崎駿はロリコンだ」というイメージがついて回るのである。
ご存じの通り『カリオストロの城』以降も、宮崎作品には少女が必要不可欠だ。特に、宮崎監督が手がけた作品を思い浮かべていただきたい。ヒロインの多くが10代の女性である。この設定も「宮崎駿ロリコン説」に拍車をかけた。
’80年代以降、この流れからも「宮崎駿はやはりロリコンなんじゃないか」という声があがる。作品におじさんの性癖が反映されているのではなかろうか、となったわけだ。
ちなみに、『風の谷のナウシカ』のDVD内オーディオコメンタリーでは、当時の原画スタッフで、のちに『新世紀エヴァンゲリオン』をつくる庵野秀明監督が、「ナウシカの胸の揺れ」について熱く語っている。彼いわく「女性キャラの胸を揺らす表現をしたのは、宮崎駿が初めてではないか」なんて言う。
果たして、これもおじさんの性癖が反映された結果なのであろうか。いやいや、私は「ナウシカの胸の揺れ」に関しては、宮崎駿ワールドの真骨頂である「リアルさ」だと思う。細かい描写が徹底してリアルだからこそ、私たちはその世界に没入できるのだ。
作品のリアリズムに関して、『耳をすませば』の例も挙げてみる。今作で監督を手掛けたのは、宮崎駿ではなく近藤喜文だ(宮崎は脚本を担当)。
近藤は「誰もいない場所で主人公の月島雫がしゃがみ込む際に、下着が見えないようにスカートを押さえる」 という絵を描いた。しかし、それに宮崎駿はめちゃくちゃがっかりしたそうだ。宮崎駿が考える月島雫というキャラクターは、右脳型の感覚肌であり、誰も見ていない場所でなら下着のことなど気にせずに、本能的に座ってしまうような子だったのだ。
つまり、雫はスカートを押さえることで「ちょっと考えてから行動する、自意識が強い子」になってしまったのである。『となりのトトロ』で宮崎駿は草壁サツキ(10歳)や、その妹・メイ(4歳)のパンツを描いている。これは、田舎町の自然のなかで暮らす子どもをリアルに描きたかったのだろう。「ロリコンだから」と結論づけるのは、あまりにも短絡的ではなかろうか。
作品に深みを加える10代少女の複雑性
そんなリアリティを重視する宮崎駿にとって「10代の少女」は、描いていて楽しいのだろう。というのも、10代の女子って“人類で最上級に複雑な精神状態”だと思うからだ。
彼女たちは同年代の男子より、何倍も人生哲学を考えている。コミュニティのなかで周りの目を意識したり、冒険したくなったり、おしとやかになってみたりと忙しい。ある意味、不安定で危うい存在だ。
例えば、サツキはトウモロコシにかぶりつく野生児っぽい顔もあれば、メイがいなくなった不安から涙する一面もあり、さらに、車道に飛び出して車を止める度胸もある。
ナウシカには勇敢さと母性があるし、『天空の城ラピュタ』のシータは清楚な一面もあれば、行動的な面も持ち合わせている。少女たちの複雑なキャラクターがものすごくリアルに描かれているから、宮崎監督の描く世界って面白いと思う。
ラピュタもナウシカも男子だけを登場させると、単純な冒険活劇化してしまうはず。ラピュタの主人公・パズーだけで敵のムスカを倒すと、もう少年向けのバトルアニメであり、筋肉の話になる。そうでなくて、きちんと心の機微を描き、最終的に哲学までを描くことが大事だ。そのために宮崎駿には”少女キャラ”が必要なのだと思う。
宮崎駿は確実に「少女への愛」を持っているはずだ。ただ、ロリコンではないと思う。セクシャルな欲求というより、精神性的な意味での少女愛なのだろう。
10代前半のナウシカの胸を大きく描いたのは、決してスケベオヤジだからじゃない。キャラとしての抱擁力を描きたかったからだ。ロリコンなら未熟さに萌えるはずなので、きっと胸を小さく描いただろう。
そんな”少女キャラ”の哲学に注目して宮崎監督のジブリ作品を観てみると、新たな楽しみが見えてくるかもしれない。作画、ストーリーと堪能できる部分が多すぎる宮崎作品だが、次回はぜひ「少女の魅力」に注目してみるのも一興だ。
(文/ジュウ・ショ)
【PROFILE】
ジュウ・ショ ◎アート・カルチャーライター。大学を卒業後、編集プロダクションに就職。フリーランスとしてサブカル系、アート系Webメディアなどの立ち上げ・運営を経験。コンセプトは「カルチャーを知ると、昨日より作品がおもしろくなる」。美術・文学・アニメ・マンガ・音楽など、堅苦しく書かれがちな話を、深くたのしく伝えていく。note→https://note.com/jusho