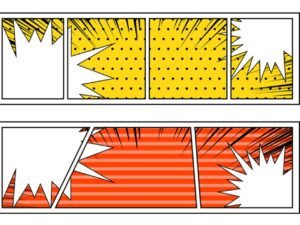「平安時代から現代まで、『漫画』はどのように扱われ、進化してきたのか」をさかのぼってみようじゃないか、というこの企画。前回は、主に子ども向け漫画を描くトキワ荘のメンバーが大活躍したり、劇画や『ガロ』の登場によって青年が漫画を読むようになったり、東京五輪でスポ根ブームが出てきたり……と、とにかく大忙しだった1960年代の漫画についてご紹介した。(記事:漫画の超激動期=1960年代がアツい!「トキワ荘」「戯画」「ガロ系」など多彩なキーワードとともに振り返る)
今回は、そんな1960年代のレジェンドたちが依然として活躍するなかで、さらなる盛り上がりをみせる1970年代の漫画をご紹介。この時代は「少年漫画」の攻防のほか、なんといっても「少女漫画」が激アツだ。漫画のレベルを「文学」にまで高めた時代を見てみよう。
まず漫画の歴史において、1960、1970年代から現在にかけて大きな舞台となるのが「少年漫画誌」だ。こんなにデジタルが発達した今でも、出勤前の時間にコンビニなんかで、スーツ姿のおじさんが少年漫画誌を立ち読みしているのを見かける。
「外見はおとなしそうな七三分けに眼鏡だけど、この人はきっと脳内に歴代の少年漫画キャラが宿ってんだなぁ」と。ヒーロー物の影響で、「たぶん今、強盗が入ってきたら、速攻でタックル決めるんじゃねぇかな」と。「でもアレだぞ。立ち読みはダメだぞ」と。もうなんか50、60歳くらいのおじさんが急に可愛く見えてくる。
まぁ、さっそくの余談はこのくらいにして、前回の記事でお伝えしたとおり、1959年に『少年マガジン』と『少年サンデー』が創刊。1963年には『少年キング』が始まって、3大少年漫画誌となった。1960年代後半、そこに加わるのが『少年ジャンプ(1968年創刊、1969年から週刊化)』と『少年チャンピオン(1969年創刊、1970年から週刊化)』だ。
創刊号からノリにノッていた『少年チャンピオン』
『少年チャンピオン』の発行元・秋田書店は『漫画王(のちの『まんが王』)』や『プレイコミック』といった漫画雑誌をすでに発行していた。つまり、「漫画雑誌創刊時の最大の難関」である漫画家集めに関しては、めちゃめちゃ優位だった。
創刊当初のメンツが、もうオールスター感謝祭みたいなレベル。手塚治虫をはじめ、梶原一騎、さいとう・たかを、藤子不二雄、水島新司、といったトキワ荘系、劇画系の豪華布陣を抱えている。まさに“チャンピオン”ばかりが目次欄に名をそろえたわけで、順風満帆にスタートする。
難破しかけるも新人発掘で波に乗る『少年ジャンプ』
一方、『少年ジャンプ』の売りは「懸賞、目次、予告以外は全ページが漫画」というスタイルだった。今考えたら「いや、そんなん漫画雑誌だから当たり前だろうが」とツッコんじゃうが、当時は異例のこと。1962年時点で『少年サンデー』と『少年マガジン』の漫画の比率は約50%だったという。つまり『少年ジャンプ』のこのスタイルは、今の少年漫画のスタイルの先駆者。さまざまな漫画雑誌が群雄割拠するなか、ロゴマークどおり「海賊」として切り込んでいく。
しかし『少年チャンピオン』と違って、海に出てみたらいきなり大しけ。もう完全に難破しかけていた。というのも、コンセプトが「全ページ漫画」なのに、肝心の人気漫画家を確保できなかったのだ。
その理由はシンプルに「編集部員不足」である。発行元の集英社は同時期に『テレビ・コミックス』シリーズ、『セブンティーン』『りぼんコミック』といった雑誌を同時に刊行しており、当初『少年ジャンプ』の編集部員は2人だけだった。会社として「いや、ジャンプはそんなに頑張らなくていいやろ」と思っていたわけだ。
創刊スタッフの1人だった編集者・西村繁男はその著書「さらば、わが青春の『少年ジャンプ』」の中で当時のことを《ちばてつやはもちろんダメ。手塚治虫、横山光輝はスケジュールの空きなし。さいとう・たかをにも躱(かわ)されてしまい、水島新司はいったん読み切りをOKしたものの、結局断られた》と回想する。売れっ子漫画家たちは新興誌に関しては、けっこう冷めた反応だったのだ。
そこで、『少年ジャンプ』は大胆にも「新人漫画家を積極的に起用する」という作戦を打ち出す。もうシンプルに有名漫画家は諦めた。逆に「ほかの雑誌では見かけない新人漫画家の作品を読める」という案で勝負した。
ちなみに、『少年ジャンプ』はこのように創刊当初から新人漫画家を積極的に登用してきたが、現在も、アプリや増刊号を組み合わせながら新人漫画家の発掘・育成に力を入れまくっている。『鬼滅の刃』の作者・吾峠呼世晴や『呪術廻戦』の芥見下々もジャンプの生え抜きだ。
漫画誌は大人向けと子ども向けにわかれていく
そんな海賊『少年ジャンプ』の「新人育成大作戦」は完全に当たった。特に世間的に認知されるきっかけになったのが、1968年にスタートして1970年代前半まで続く、永井豪の『ハレンチ学園』と本宮ひろ志の『男一匹ガキ大将』。両方ともいい意味で“超ガキっぽい”。ゆえに、小中学生の心をがっつりキャッチする。『ハレンチ学園』に関しては子どもの心をわしづかみにし過ぎて、作中に出てくる「スカートめくり」が三次元で流行(はや)りまくり、PTAが頭を抱えるレベルだったという。
この時期、すでに王座に君臨していた『少年サンデー』や『少年マガジン』は、漫画のターゲットを青年層まで広げていた。例えば、『少年マガジン』は『巨人の星』『あしたのジョー』といった劇画漫画を連載。前回の記事でお伝えしたが、劇画漫画は主に青年の読み物だった。実際、よど号ハイジャック事件での声明文にも「われわれは明日のジョーである」と書かれるほど、少年漫画誌は大人への影響力があったのだ。
また、『少年マガジン』では谷岡ヤスジの『ヤスジのメッタメタガキ道講座』を連載。ナンセンスなギャグは、もはや子どもの脳の範疇(はんちゅう)を超えたアートの世界だった。『少年マガジン』や『少年サンデー』などに掲載された『天才バカボン』も、とんでもなくナンセンス。赤塚不二夫のキレッキレのギャグは子どもにはシュール過ぎて、だんだん青年の読み物になる。
一方で「純粋な少年漫画」はちょっと手薄になりつつあり、後発の『少年ジャンプ』や『少年チャンピオン』は、そこに突撃したわけだ。なかでも、新人発掘作戦をとっていた『少年ジャンプ』は1970年代前半に吉沢やすみ『ど根性ガエル』、とりいかずよし『トイレット博士』、遠崎史朗原作、中島徳博作画『アストロ球団』といった、当時ほぼ無名の新人漫画家による「子どもにもわかりやすい漫画」で発行部数を伸ばしていく。1973年8月には、ついに『少年マガジン』を抜いて雑誌発行部数で首位に立った。まさに海賊。一気に宝物(読者)を奪っていったのである。
“がきデカ”と“こち亀”の共通点とは
そんな『少年ジャンプ』も1975年ごろから「ギャグマンガ路線」の強化に乗り出す。1976年には『こちら葛飾区亀有公園前派出所』がスタート。時事ネタなどを扱った1話完結のスタイルで、2016年まで連載が続いた。
初期“こち亀”の特徴といえば、とにかくド派手なギャグ。派手すぎて、もはや下町のいち派出所のスケールではない。主人公の両津勘吉は、とんでもないハイペースで鉄砲を撃ちまくる。往来でバズーカをぶっ放すのが、もはや日常茶飯事。警察なのにあらゆるタブーを犯しまくる漫画だ。
そのせいで「両津〜!」と毎回、部長にガチギレされるのだが、マジでまったく反省しない。ただ、その光景まで含めてみんなから許されており、愛されている。この「めちゃくちゃ濃いキャラクターの自由な振る舞いを許す」という作風は、1974年に『少年チャンピオン』で連載を開始した山上たつひこの『がきデカ』のパロディといってもいいくらいのものだった。「死刑!」の一発ギャグで有名なこまわり君のキャラクターを意識していたのだ。実際、こち亀の作者・秋本治の初期ペンネームは「山止たつひこ」だ。
ちなみに、この作風は1980年代に入って、鳥山明の『Dr.スランプ』に引き継がれる。主人公のアラレちゃんは、もうなんか鼻をほじるくらいのテンションで、月や地球を割ったりする。「懲役何年だよこれ」という大事件を犯すし、ニコニコして反省もしないが、みんなに愛されてすくすく育っていく。
そんな「新しいギャグの世界観」を生み出した、という意味でも、『がきデカ』は漫画史において重要な作品なのだ。見た目も行動もすんごくバカだけど、決してバカにしてはいけない。
「24年組」の影響で成人男性も少女漫画を読む時代に
そして1970年代にグーンと進化したジャンルといえば、なんてったって「少女漫画」だ。1960年代は「キラッキラのお目目」で、やたらとバラが舞う……、“かわいい”がぎっしり詰まった「女の子の読み物」というイメージだった。しかし1970年代に入り、そんな少女漫画はゴリゴリの成人男性にも読まれるようになっていく。
その立役者となったのが、いわゆる「24年組」。昭和24年ごろに生まれた青池保子、樹村みのり、大島弓子、ささやななえ(現・ささやななえこ)、竹宮惠子、萩尾望都といった女性漫画家を指す言葉である。
なお、前提としてこれだけは書かせてほしい。萩尾望都は自著『一度きりの大泉の話』で《私はなぜこのグループに括(くく)られているの?》と、自分が24年組に含まれていることに困惑していることを書いている。
また萩尾望都と竹宮惠子が一時期、練馬区の南大泉で同居生活をしていたこともあって、解説本などでは「当時、萩尾や竹宮が“女性版トキワ荘を作ろう! 新しい少女漫画を作ろう!”と盛り上がっていた」と紹介されることもあるが、萩尾自身が「少なくとも自分にはそんな意識はなかった」と振り返っている。
つまり「24年組」というのは「いつの間にかできた言葉」であって、周りが勝手にグルーピングしてる言葉なのだ。確かにちょっと「美談に持っていこうぜ」的なブランディング感は否めない。
ただし「この時代、先述したすばらしい女性漫画家の手によって、少女漫画は少女だけのものではなくなった」という事実は不変。そのハイレベルな作品は、大学生や成人男性までが読むようになったのだ。
では、彼女たちの少女漫画はそれまでと何が違ったのか。前回の記事でお伝えしたように、戦後すぐのころの少女漫画は、いわゆる『サザエさん』的な等身大の女性像を、リアリティたっぷりに描くものが多い。そして、その潮流は1968年に創刊した『りぼんコミック』の漫画家グループに引き継がれていった。
『りぼんコミック』は『りぼん』から派生したもので、新人を多く起用して短編の読み切りを掲載していた。そのため、かなりチャレンジングな作品が多い。しかし、それでも舞台やテーマはあくまで日常生活における学園恋愛ものや友情ものが多く「女子中高生の読み物」の枠を出られなかった。
一方で、前述の「24年組」は主に小学館の『別冊少女コミック(現在は『ベツコミ』)』などで描いていた。石森章太郎や水野英子といったトキワ荘のSF世界に影響を受けた彼女たちは、日常を抜け出して中世ヨーロッパや、架空の世界などを舞台にする。つまりSF要素、ロマネスク要素をふんだんに取り込んだわけだ。そんな幻想的な世界で、恋愛やコメディといった要素だけでなく、もっと深い人間の生き方・哲学を描くようになる。
また、ストーリー自体も文学性が高い。例えば、萩尾望都の『ポーの一族』は西洋の吸血鬼伝説を主軸にした漫画だ。ロマンチックな世界観のなかで時系列が行ったり来たりと前後して語られる。話ごとに別の時間軸に移るので、読んでいるうちに「あれ、これ夢かな? それとも現実? どっちよ。こわっ」という感覚に陥る。それほどまでに文学性が高くて幻想的な世界観なのだ。
また、『11人いる!』は宇宙船に閉じ込められた11人の受験生たちの話。密室ものならではの緊迫感あるミステリー要素だけでなく、登場人物の恋愛、友情、成長を描いた作品だ。複雑な設定のなかで、哲学的なテーマまで話を膨らませた。
さらに「元祖・ボーイズラブ」こと竹宮惠子の『風と木の詩』は外せない。同作は19世紀における、フランスの少年たちの同性愛を描いた作品だ。少年同士の性行為、レイプ、近親相姦(かん)といった、今考えても少女漫画誌ではあまりに衝撃的な描写が盛り込まれている。
当時、若者のリーダー的な立ち位置だった寺山修司が「これからのコミックは、『風と木の詩』以降という言い方で語られることとなるだろう」と断言していることからも、当時は成人男性も少女漫画を読んでいたことが分かる。
令和のいま「BLカルチャー」は完全に市民権を得つつあり、多くの女子が順調に“腐っている”が、その先がけとなった作品は間違いなく『風と木の詩』だった。これはもう気持ちいいくらいの余談だけれど、今やBL女子は進化しすぎたあまり「唐揚げとレモン」のカップリングで小一時間ばかり盛り上がるらしい。
今の若者にも支持される1970年代漫画の世界観
萩尾望都の『ポーの一族』は、スタートから40年近くたってもシリーズとして発表されており、『このマンガがすごい! 2018』オンナ編では、なんと第2位を獲得した。1972年に発刊された漫画が、令和の時代にトップクラスの評価を得るというのは、尋常じゃない。この作品で描かれる人生哲学は決して一過性のブームじゃない。だからこそ、いつの時代にも人の心に響くのである。
1970年代はコメディの表現や、少女漫画の世界観をはじめ「漫画の描かれ方」も大きくアップデートした時代だ。ここでは紹介しきれなかったけれど、宝塚歌劇の影響もあって大ヒットする池田理代子作『ベルサイユのばら』も重要だ。また、江口寿史の『すすめ!! パイレーツ』も革命的。「いや、これ怒られるだろ」とツッコんじゃうくらいのパロディの表現と量は、当時も今も斬新さを感じる。
また1975年には、あの「室内なのに人の熱気で雲ができる」でおなじみのコミックマーケットが初開催されている。地下では、アマチュア漫画家による同人誌作りなんかも盛り上がっていたわけだ。
このあと、1980年代に入ると、ラブコメブームが始まったり、大友克洋と鳥山明という2人の天才が頭角を現したりと、漫画の表現がまた大きく変わっていく。そのお話は次回でたっぷりお伝えしたい。
(文/ジュウ・ショ)
【参考文献】
◎『日本漫画全史:「鳥獣戯画」から「鬼滅の刃」まで』(平凡社刊)
◎『日本の漫画本300年:「鳥羽絵」本からコミック本まで』(ミネルヴァ書房刊)
◎『「コミックス」のメディア史 モノとしての戦後漫画とその行方』(青弓社刊)
◎『一度きりの大泉の話』(河出書房新社刊)
◎『日本一のマンガを探せ!-20世紀最強のコミックガイド』(宝島社刊)