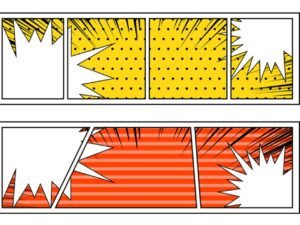今や日本を代表する文化となった「漫画」。この原稿を書いている今、世界は大混乱に陥っているが、そんななかでも頻繁に漫画タイトルがTwitterのトレンドに入るのを見ると、「日本人ってホントに漫画大好き民族だなぁ」と、なんだかホッとしたりする。
そんな日本における漫画の歴史を平安時代から楽しく追ってみようじゃないか、というこの企画。前回は、少女漫画界で大きな変化が起こった1970年代の漫画についてご紹介した。今回は1980年代の漫画について。世間的には戦後の高度経済成長期がひと段落して「OK、バブリー!」な時代に入っていくなかで、漫画はどのように変化したのかを見ていこう。
あぁ、愛すべき「おたく」の誕生
1980年代、まず特筆したいのが、「おたく」という言葉の誕生についてだ。コンテンツがあふれかえっている現代では「誰もが何かしらのおたく」であり、2021年には「推し活」が流行語大賞にノミネートされたほど。そんな現代に通づる「推しのことは何でも知りたい」「推しに関係するものはとにかく手に入れたい」という現象は、実はこの時期にスタートする。
「おたく」という言葉は、1983年に雑誌『漫画ブリッコ』に掲載された中森明夫の記事「『おたく』の研究」のなかに登場したといわれる。ここでは、1975年に初開催されたコミックマーケット(コミケ)に集まる中高生の少年少女を指す言葉として使われた。その男女らが、「……でさぁ、おたくはこの作品をどう思ってんの?」って具合に、友達などを「あなた」ではなく「おたく」と呼んでいたことから命名されたという。
おたくは最初、どちらかというと「自虐っぽい」言葉だった。つまり、同人誌やアングラな雑誌を集めまくる人たちが「世間一般のみんなとは、この気持ちを分かち合えないよね……」って自嘲していた感じである。
1980年代前半は「ネクラ」や「ネアカ」という言葉がはやり、やたらと「社交的な人間こそ正しい」といった風潮が高まっていた。それもあって、内向的とされたおたくは、“地下”で仲間意識を強めていたのかもしれない。
そんななか、「オタク=ヤバいやつ」というイメージが高まったのが、1989年の「宮崎勤事件」だ。このあたりから「漫画・アニメ好きってさぁ、現実と虚構との区別がつかない”ヤバいやつ”なんじゃねぇの」と、ひそひそ言われるようになる。当時の新聞では、もともと平仮名の「おたく」が「オタク族」と、カタカナ表記になっている。仲間内の「おたく」という自虐用語は、世間的に「オタク」として、ネガティブイメージとともに広がっていくわけだ。
現代だとSNSなどで「おい!(犯罪者と)一緒にすんなよ!」と言い返せるだろう。しかし、当時はそんな術(すべ)がなかったし、何より、おたく自身が「自分はちょっと世間的にヤバい趣味がある」と自認していた。
その変な負い目があるため、内向的な性格にさらに拍車がかかり、人と話すときに軽いパニック状態になり「へへ……へへへ……」と、謎にニヤニヤするだけで会話がうまくできない。しかも、そんな失敗をあとから思い出して、さらに人見知りが深くなる……という、もう「地獄の陰キャスパイラル」に陥っていくおたくも多かったことだろう。
自分もおたくと自負しているからこその意見だが、おたくといえば総じて早口だと思う。あれは「話したいことが山ほどあるから」だけではない。前提として「自分の話で時間を奪いたくない」と卑屈になってしまい、相手に死ぬほど気を使っているのだ。
そんな“野生のおたく”にとって、インターネットはまさに安住の地だった。「対面じゃないし匿名だし、これなら自分の”好き”を存分に長文で書ける!」となり、ブロガーなどが増加。また、2000年代以降になると「オタク」は「ヲタク」という言葉として、2ちゃんねるのスラングなどで多用されるようになった。
そこから短縮されて、今ではよく「ヲタ」と呼ばれるが、もう偏愛コミュニティを差別する風潮はない。むしろ「推し活」は人生を豊かにするという意味で、ポジティブにとらえられている。1980年代前半に比べて、非常にヲタに優しい世界になりつつあるのは、いちおたくとして、本当に幸せなことである。
高橋留美子という“ラブコメの巨匠”の登場
さて、漫画の話に戻ろう。1970年代に成人男性が少女漫画を読むようになったことは、前回の記事でお伝えした(記事:1970年代は“少年漫画の攻防”と“少女漫画の哲学化”が激アツ! 伝説の「24年組」の作品は何がスゴかったのか)。青年男子は少女漫画の心理描写を読んで「おぉ……漫画ってスポ根とかロボットだけじゃねぇんだ……」と気がついた。
そこで、少年誌のあり方も変わってくる。「ラブコメもの」を少女漫画から輸入したのだ。例えば、1978年スタートの柳沢きみお『翔んだカップル』は、少年漫画誌におけるラブコメのパイオニア的作品である。主人公の少年は、海外にいる叔父夫婦の家でひとり暮らしをしている。そこで美少女と同居することになる……と、もう完っ全に少女漫画の設定だ。ラブコメ少女漫画において、主人公の家族はマジで都合よく海外に行くのだが、それを少年誌でやったわけだ。
そんななかで出てきた”ラブコメの巨匠”のひとりが高橋留美子である。1978年に、当時まだ大学生でありながら『うる星やつら』の連載を開始。その後、1980年には『めぞん一刻』、1987年には『らんま1/2』と、おなじみすぎるラブコメヒット作品を次々と生み出す。
特に、『うる星やつら』に登場する「ラムちゃん」というキャラクターは、今考えても強烈だ。まず「鬼型宇宙人」というぶっ飛んだ出自。で、超能力者で怒ると電撃を放つ。見た目はスタイル抜群で超絶美人なうえ、「ビキニが一張羅」というセクシーさ。さらに、おてんばでちょっと天然。しかも語尾は「だっちゃ」「のけ?」といった「いや、故郷どこなん?」という独特な方言。
いやもう、具だくさんすぎる。薬膳鍋くらい具が多い。ここまで魅力たっぷりなうえに、何より主人公・諸星あたるに一途(いちず)で、彼がどれだけ浮気しようとも愛し続ける。これが当時の男性諸君の心をシビれさせまくったのは、いうまでもない。まだ「萌え」という言葉ができる前だが、『うる星やつら』は「萌えの元祖」といわれることもある名作だ。ちなみに2022年、36年ぶりにTVアニメ化されることが決定した。今から”そわそわしている”おじさんも、たくさんいることだろう。
「スポ根」ものに終止符を打ったあだち充
また、スポーツ漫画の土俵でいうと、あだち充も外せない。彼は初期のころ、原作者つきで劇画漫画や少女漫画を描いていたが、1978年に完全オリジナル作品として野球漫画『ナイン』をスタートさせる。
1970年代のスポーツ漫画は、とにかく「血と汗と涙で勝利をつかむぞ!」みたいな。「夕日に向かってウサギ飛びだ!」みたいな。フィジカルを鍛えまくったうえで、試合ではものすごい魔球を投げるみたいな、熱いスポ根ものが主流だった。
なぜ、こんなにもスポ根がはやったのかというと、高度経済成長期のまっただ中だったことも関係している。当時の日本は、とにかく戦後復興の真っ最中。「貧乏」をコンプレックスにして「働け働けぇ!」という、「努力こそ美学」の時代だった。しかし、1973年のオイルショックを経て安定成長期に入ると、ゆっくりとスポ根ブームは廃れていく。
「相手よりトレーニングして、白熱した試合をしておまえに勝つ!」みたいな勝負だったのが、だんだんと「いやいや、そんな熱くなんなよ」ってなる。”スカす”っていう感覚が、ちょっとオシャレだったのだ。
例えば、水島新司『ドカベン』(1972年に連載開始)では、熱い根性論よりも、冷静に技術面や試合としてのリアリティを見せた。また、江口寿史『すすめ!!パイレーツ」(1977年に連載開始)は、パロディを存分に入れたギャグで、完全にスポ根をいじりまくるようになる。
スポ根が古くなっていくなかで登場した“あだち漫画”は、「ゆるゆる~っとしたラブストーリー」が見どころなので、試合に負けても無問題なのである。
そして1981年に始まった『タッチ』で、完全にスポ根漫画ブームにとどめを刺す。『タッチ』はみなさんご存じ、努力家の弟・上杉和也が怠け者の兄・達也に夢を「バトンタッチ」する野球漫画だ。
その最終巻でスポーツ漫画界に衝撃を起こした。まず甲子園の開会式当日に、達也は球場にいない。地元(設定では東京都練馬区)に帰って「上杉達也は浅倉南を愛しています」と、別の意味で”宣誓”している。で、当然のように甲子園での試合はまったく描かれない(優勝しているのに)。極めつけは、ライバルの新田明男が「またどこかのグラウンドで」と達也にさらっとリベンジを申し込むが、達也は「もういいよ。疲れるから」とあっさり答える。
この「もういいよ」こそが、スポ根に終止符を打った。読みながら「おい。新田の気持ちどうするん」とツッコんだが、いやいや、これこそが新しいスポーツ漫画だった。この「熱いライバル関係に無理に固執しない」という、どこかクールで身軽な感覚こそ、安定成長期からバブルに向かう「満ち足りた日本の価値観」が反映されていると私は思う。「貧乏をコンプレックスに頑張りまくっていた日本」は、このときに終わりを告げ始めたのだ。
漫画を大幅にアップデートした2人の天才
また、1980年代といえば鳥山明と大友克洋を抜きにして語れない。この2人によって、漫画の表現は大幅にアップデートされた。
1980年に連載を開始した『Dr.スランプ』で知られる鳥山明の「画力の高さ」は、当時の漫画家にとって脅威でしかなかった。手塚治虫をはじめ同業者が大絶賛し、漫画全体の画力レベルが底上げされた2020年代でも、いまだにヒクほどうまい。絵が達者な漫画家が現れたら定期的にSNSや5ちゃんねるなどで話題になり、そのたびに鳥山明の絵と比較されて「いや、やっぱ格が違うわ」と言われるのは、もはや恒例行事である。
そんな鳥山明の絵のルーツは漫画でなく「グラフィックデザイン」だった。幼少期にディズニーの『101匹わんちゃん』などを模写していたが、小学校高学年からは漫画に触れていなかったという。しかし、絵は得意だったため、工業高校のデザイン科に入学する。卒業後にデザイナーとして広告を作っていたが2年半で退職。お金がなくて困っていたときに少年ジャンプの漫画賞を知り、そこではじめて漫画を描き始めたという。
また、彼はプラモデル作りの腕前もプロ級である。絵のルーツが「漫画」というより「デザイン」だったことも含め、当時の漫画絵を知らずにコミックの世界にやってきた。だからこそのデッサン力、バランス感覚があったのだろう。
「大友以前、大友以後」といわれるほどの革命
もう1人、漫画の絵を大幅にアップデートした存在が大友克洋だ。以前「今の文系大学生の部屋には、なぜか『ガロ』が置いてある」という話をしたが、大友の名作『AKIRA』も同じ。なぜかサブカル系大学生の家には、ほぼ100%『AKIRA』がある。ただ、彼らのうち80%はインテリア的な感じで置いている。ゆとり世代以降のサブカル系大学生にとってこの作品は「持ってるだけでインテリっぽく見える」の代名詞なのだ。
大友克洋はもともと映画監督を志望して上京し、食いつなぐために漫画を出版社に持ちこみ始めた。最初は海外文学原作のコミカライズだった。1970年代後半にコンスタントに作品を発表していくなかで、おたく界隈で「大友克洋っていうなんか、えげつない作画レベルの漫画家がいる」と話題になる。
そんな彼の名がマニア枠を超えて世間に知られたのは、短編集の『ショート・ピース』と『ハイウェイスター』、『さよならにっぽん』だ。これら3作品のヒットで大友克洋の名はは一般層にまで広がり、多くの読者は”衝撃”を受けた。
このあと1980年に入って、代表作である『童夢』や『AKIRA』の連載をスタートしたが、このあとの時代からは、もうみんな大友克洋の絵に寄せていく。漫画家志望の若者はもちろん、同年代や先輩漫画家、江口寿史をはじめとするギャグ漫画家、吉田秋生や高野文子といった少女漫画家などが彼の影響を受けた。
では、「大友作品の絵はそれまでの漫画と何が違ったのか」。例えば、キャラクターの描き方でいうと「登場人物がみなキャラクター要素のない、どこにでもいる日本人の顔をしている」「老人の皺について、それまではほうれい線1本程度の表現だったが、目じりやおでこまで緻密に描かれている」「風景と人物の線の太さが同じであり、人を風景のひとつとして描く」などが有名だ。
つまり、キャラクターの表現自体がとんでもなく「リアル」。むちゃくちゃ写実的で、過度なデフォルメをしていないのだ。以前の記事で「手塚治虫がキャラクターをデフォルメすることで子ども向けの漫画表現を構築した」と紹介した。『ジャングル大帝』のレオが驚いて立ち上がる……みたいにデフォルメすることで愛らしさ、コミカルさを出したのだ。そこから劇画漫画が登場してカウンター的に「絵のリアルさ」を打ち出し、青年読者を獲得する。
この1950年代の発明から20年間、漫画家は「リアルとデフォルメ」のバランスを考えながら「漫画らしい絵」を考えていたわけである。そこに3次元に限りなく近い大友のキャラクターが登場するわけだ。もう「この20年間はなんやったん?」っていうレベルの革命である。
いや、もっというなれば、「漫画」という言葉は葛飾北斎が「漫ろに描いた絵のことやで~」と定義したように、そもそもデフォルメするのが基本だったはずだ。ちょっと大げさかもしれないが、大友克洋は150年以上続いてきた「漫画の定義」すらひっくり返してみせた、といってもいいのではないか。
どれだけリアリティをもって描かれたか。例えば「アトムってどんなキャラだっけ?」という質問には「お目目がクリクリでツノがあって……」と、すぐ答えられるだろう。「デューク東郷は?」に対しても「極太まゆ毛で目が鋭くてスーツで……」などと、キャラの個性がすぐ頭に思い浮かぶ。
でも「AKIRAの金田は?」は、とんでもなく難問だ。デフォルメされてない平均的な日本人の顔だから、わかりやすい特徴がないのである。名前も「金田」や「鉄雄」など、全然キラキラしていない。大友は過去のインタビューで「近くの友だちを参考にしていたら自然とこうなった」と答えているが、逆にそんな「奇をてらわない表現」が漫画においては、ものすごく革命的だったのだ。
もちろん「大友克洋が漫画界に起こした革命」はこれだけではない。「建物や乗り物の造形が信じられないほど緻密で、かつ3Dだったこと」「フランスの漫画家、特にジャン・ジロー(メビウス)の影響を受けた『よく分からない宇宙人みたいなキャラ』や『巨大メカ』といった未知の造形物を生み出したこと」など……語りだすとマジで止まらなくなりそう。読者のみなさまに「地獄の永久スクロール」をさせてしまうのでこの辺でやめておくが、まさに「大友以前、大友以後」といわれるまでに漫画の歴史をひっくり返した。
さて、今回は1980年代の漫画の歴史について、たっぷりと紹介した。なかでも鳥山明と大友克洋の作品は、世代ではない私が読んでも「なにこれ、超斬新なんだけど」っていう表現が山ほどある。
そんな2人の共通点といえば「メディアミックス」と「世界進出」だ。1980年代後半から1990年代にかけて、漫画やアニメは立派なジャパニーズカルチャーになっていく。
いよいよ次回でこの連載もラスト。日本の漫画やアニメが世界に認められるまでの流れとか、「萌え系」「セカイ系」「なろう系」の歴史、現在のSNS漫画などをたどりながら、2022年の今、漫画はどう進化したのかを楽しく考えていきたい。
(文/ジュウ・ショ)
【参考文献】
◎『日本漫画全史:「鳥獣戯画」から「鬼滅の刃」まで』(平凡社刊)
◎『日本の漫画本300年:「鳥羽絵」本からコミック本まで』(ミネルヴァ書房刊)
◎『「コミックス」のメディア史 モノとしての戦後漫画とその行方』(青弓社刊)
◎『マンガ熱』(筑摩書房刊)
◎『ジャンプ流Vol.1』(集英社刊)
◎『芸術新潮 2012年4月号』(新潮社刊)
◎『ユーロマンガ Vol.3』(Euromanga合同会社)
◎『東京大学「80年代地下文化論講義」』(白夜書房刊)
◎『マンガ熱』(筑摩書房刊)
◎『漫画・まんが・マンガ』(青弓社刊)
◎『マンガ熱』(筑摩書房刊)