1972年「ワイルドな17才」のキャッチフレーズでデビューした西城秀樹さん。「新御三家」として芸能界の第一線を走り続け、キラ星のごときヒット曲は数知れず。長身に甘いマスクで人々の胸を熱くさせ、持ち前の明るい性格でも愛された。
2018年5月、惜しまれつつも天に召されたが(享年63)、デビュー50年の記念日にあたる3月25日を迎え、ありし日の姿を振り返ってみたい。
貴重な証言を寄せてくれたのは、マネージャーとして35年間にわたって秀樹さんを支えた片方秀幸さん(61)。秀樹さんの5歳下で、最初は付き人兼運転手。その後はチーフマネージャーとなり、プロデューサーとしても苦楽をともにしてきた。
まずは間近に接した、スター・西城秀樹の素顔から聞いた。
圧倒的なオーラとやさしさと
「ふだんは本当に普通のお兄ちゃんなんですが、店に入る時は気を遣いました。洋服屋さんでも食べもの屋さんでも、入ったとたん店にいる全員に気づかれる。全員が気づいて “西城秀樹だ!”って感じになるんです。マネージャーとしては “守らなければいけない”と緊張しましたね。
見られていると、本人も西城秀樹にならないといけませんし、握手やサインを求められても断らないんですよ」
──背が高いし(身長182cm)、普通にしていたって気づかれますよね。
「とにかく存在そのものから放つオーラが半端ない。べつに派手な服装とかしているわけでもないのに目立ってしまう。そのくせ本人は気にしないでお店に入るんですよ。
なじみの飲み屋さんとかだと大丈夫なんです。周りのお客さんもみんなわかっていますから。気を遣ったのは洋服屋さんですね。洋服が大好きで気になったお店があるとフラッと入っちゃう。局から局の移動で30分時間があいたときとか、赤坂から六本木に行く間とか。レコード会社も渋谷の宮益坂の上にあって(1980年代はRVC所属)、場所が場所だけにどこへでも(笑)」

──マネージャーとして現場についた当時、秀樹さんは何歳でしたか?
「1984年だから29歳です。若いから本当にパワフル。仕事が終わるのは毎晩てっぺん(24時)を超えていましたけど、そこから飲みに行くんです。行くと必ず誰か知り合いがいますから、夜通しワイワイやっていました」
──その間、現場マネージャーは車の中で待たされるんですか?
「いいえ。一緒にお店に入っていました。秀樹さんは絶対に “外で待っていろ”とは言わない人でした。メシにしても飲みに行くにしてもいつも一緒。やさしいんですよ。
でも、翌朝は大変です。たとえばテレビ東京の『ヤンヤン歌うスタジオ』とかで朝10時入りだと8時半には家を出なきゃいけないんですけど、5時ぐらいまで遊んでいるから、起こすのがひと苦労です。1時間ぐらいかけて起きるまでマッサージですよ。“起きてください!”って言いながら、“脚やって……”みたいな(笑)」
──二日酔いで困ったなんてことは?
「あるとしたらコンサートツアー中ですね。身体も大きいし体力があるから、本当によく飲むんです。しかも人が飲んでいるものを飲みたがる(笑)。 “芋? じゃ俺も芋(焼酎)。そのウイスキーはバーボン? じゃバーボン”って、ひたすら明るいお酒です。さすがにホテルに帰るころにはベロンベロンなんてこともありました。
そんな次の日は汗をかくために服を着込んで、コンサート会場の階段の一番下を何往復もするんです。めったになかったけれど、やっぱり二日酔いするときはあるんだなと(笑)」

──ふだんの食事とかはどうされるんですか?
「だいたいラーメン、蕎麦、焼きそば、カレー。これでローテーションを組めるくらい、ごく普通のものが好きでした。ファンクラブの会長とかがサポートについていますから、顔見たら“◯◯ちゃん、今日は焼きそば” “◯◯ちゃん、カレーがいいなぁ”。そんな繰り返しです」
──やっぱりカレーはお好きなんですね!
「ハウスさんのCMでお世話になっていますから。外で食べるときはCoCo壱も好きでした。主な地方都市にはだいたいありますよね。なかったらコンサートをする会館の食堂のカレーとか」
──それでも大丈夫なんですか?
「ぜんぜん大丈夫でした。むしろ、そういうほうが好きなんですよ。もちろんフォーマルな高いお店も知っていますし、夜はお寿司とかステーキとか鉄板焼きとかにも行きます。でも楽屋で食べるなら高級な懐石料理の弁当とかよりも、あったかいカレーとか焼きそばとか。
あとは子供のころから広島のお好み焼きを食べているので、何かあるとお好み焼きですね」
『YOUNG MAN(Y.M.C.A.)』を盛り上げるために
──秀樹さんはシングルだけでも87曲。ヒット曲が本当にたくさんあります。コンサートで歌う曲目はどうやって決めていましたか?
「毎年セットリストは変えていました。時代の流れを見ながら、最初に僕らマネージャーがたたき台を作るんです。今年は秋っぽいバラードから始めてアコースティックに行って最後にはガーンと盛り上げようとか。もしくはド頭からロックで行こうみたいな流れを決めて。
秀樹さんからも “この曲とこの曲は離したほうがいいな”とか意見が出てきて、その直感を生かして枠を組み合わせていきます。幸いオリジナル曲はたくさんあるので、その組み合わせたるや無限なんですよ」
──絶対にやると決まっている曲はあるんでしょうか?
「特にありません。『傷だらけのローラ』があるから今回は『ブルースカイ ブルー』ははずしておこうかとか。今年は『若き獅子たち』を聞いてもらおうとか、本当に無限ループのようにいろいろな組み合わせがあって、流れができると一気に決まりますね。
例えば『傷だらけのローラ』をフィーチャーしようと思ったら、まず『激しい恋』から盛り上げて『ブーメランストリート』と『炎』をやってから、ジャーン!(ローラのイントロ)とか。メインとなる曲を決めてその前をつくっていくんです。その流れをつくるための曲というのが、本当にいっぱいありましたから」
──『YOUNG MAN(Y.M.C.A.)』はどうですか?
「さすがに近年のコンサートでは『YOUNG MAN』だけは、どこかのポイントでガーンとやっています。『YOUNG MAN』をやるためにも、前の曲からどんどん盛り上げていくんですよ。例えば『俺たちの時代』をやって『ホップ・ステップ・ジャンプ』をやって、そこからの『YOUNG MAN』でお客さんは最高潮に達するんです」

2012年からスペシャルゲストとして出演した「同窓会コンサート」では、フィナーレで必ず『YOUNG MAN(Y.M.C.A.)』を歌って盛り上げた。あいざき進也、あべ静江、伊藤咲子、リリーズなど、年によって多少メンバーに変化はあったが、往年のアイドルたちが大集合。その中心に常に存在していたのが西城秀樹だった。
「同窓会コンサートは『YOUNG MAN』がないと成立しません。いちばん最後に出演者全員がステージに登場して『YOUNG MAN』をやって終わる、と。お客さんはみなさん、若いころに戻ったような感じでキラキラと目を輝かせてくれました」
日本全国各地をまわって年間70〜80公演にもおよぶステージは、秀樹のライフワークとなっていた。
『ちびまる子ちゃん』ありがとう!
熱心なファンには知られていることだが、実はその『YOUNG MAN(Y.M.C.A.)』ですら、一時期、歌われないことがあった。
1985年1月、日本武道館で開催したコンサートで、それまでに発表したシングル50曲すべてを歌い上げた秀樹は「これで歌い納め」と言わんばかりに、しばらく過去の曲を封印する。
「秀樹さんはヒット曲は “自分が残した財産だ”と常々言っていました。ただ、どちらかといえば過去に固執するタイプではないんです。アイドル時代のことにしても、こと細かには覚えていないと思いますよ。ドラマや映画にしても、撮影が終わったと思ったらすぐさま気分を切り替えて、次に進んでいく。
1985年以降は “あの曲はもういいよな……”という感じで『YOUNG MAN』も歌わず、当時の新曲とアルバムの曲を中心にやっていました」

そんな変化に一抹の寂しさを感じていた向きも多かったが、5年ほどで封印が解かれる。
きっかけは、あの『ちびまる子ちゃん』だった。
作品世界はなつかしい昭和(1974年ごろ)で、まる子のお姉ちゃん(さきこ)はヒデキの熱狂的ファンという設定。1990年からフジテレビ系でアニメ放送がスタートして大人気となり、翌1991年、秀樹がエンディングテーマ曲『走れ正直者』を歌うことになる。
「『走れ正直者』はあちらからオファーをいただきました。ちびまる子ちゃんのお姉ちゃん同様、さくらももこさんご自身が秀樹さんのファンだったと聞いています。それで作詞・さくらさんで、作曲・織田哲郎さん。おかげさまでヒットしましたね。
そして、CDシングルのカップリングには『HIDEKI Greatest Hits Mega-Mix』として往年のヒット曲を入れました。ビートに乗せて『激しい恋』『傷だらけのローラ』『情熱の嵐』『薔薇の鎖』など8曲をミックスでつないでいった。そこから一気にこだわりがなくなりました」
──こだわりですか?
「それまでは変なこだわりがあったんですね。“俺、歌わないぜ”みたいな。若いアイドルとは一線を画すというか、アイドルから脱皮しようというか。まだ30歳そこそこだったのに “下の世代とは違うんだ”みたいな意地もあった。
でも、やっぱりいい曲は時代を超えて愛されるし、みなさんが求めてくれるんですよね。ようやく気づいたのが35〜36歳のときですね」
ひと言「俺、結婚決めたから……」
往年のヒット曲を解禁する一方、欧米のロックが大好きで、ライブではローリング・ストーンズやクイーンやキング・クリムゾンの曲を歌う秀樹の嗜好(しこう)は、別の形で実を結ぶことになる。
「『走れ正直者』と同じ日(1991年4月21日)の発売で『Mad Dog』というオリジナルアルバムを出しているんです。これは織田哲郎さんのプロデュースでロック色の強い作品です。
織田さんは『おどるポンポコリン』(B.B.クィーンズ)を作曲して大ヒットさせていますが、織田さんといったらやっぱりロックじゃないですか。秀樹さんもロックが大好きなので話が盛り上がって『Mad Dog』につながったわけです。とてもいいバランスだったと思います」
この頃の秀樹はまさに円熟の境地。
1994年にはNHK『紅白歌合戦』に10年ぶりに復帰し、『YOUNG MAN (Y.M.C.A.)』を熱唱。さらに『紅白』では1997年YOSHIKIが作曲したシングル『moment』を歌い、2001年まで5年連続で出場している。
プライベートでは2001年6月に美紀さんと結婚。46歳にして「独身貴族」といわれたシングルライフにピリオドを打った。
──結婚については、どういうかたちで聞かされましたか?
「マネージャーにはあらたまって言いません。“俺、結婚決めたから”。“あ、おめでとうございます”みたいな感じだったと思います。
もちろん美紀さんと会っているというのは、なんとなく知っていたんです。最初は秀樹さんのお姉さんの紹介で。だんだん “ひょっとしたらそうかなぁ”みたいな気配がただよってきて。決まったときは、発表するまで絶対に外に漏れないように、というのにいちばん気を遣いました」

──いい人と結ばれてよかったですね。
「はい。すぐ子宝に恵まれて、翌年にはお嬢さんが生まれました。
当時のご自宅は地上2階、地下1階という造りで140坪ありました。まるで美術館みたいな洋館だったんですが、やっぱり独身だから成立した空間だと思います。プライベートスタジオがあったり、完全に趣味を謳歌(おうか)するための家でした。住み込みのお手伝いさんもいましたね。
それが美術品やオブジェや骨董品やらの横に、お子さんの三輪車やジャングルジムが置かれるようになったり(笑)。床もぜんぶ大理石でしたから、転んだら危ないというのでフローリングに貼り替えたりとか。だんだん家族のための家になっていき、2012年には引っ越しをされました」
──お子さんは3人(1女2男)ですよね。秀樹さん自身の変化はありましたか?
「やっぱり父親としての自覚というか、“自分がこの家族を支えていかなきゃいくんだ”という責任感をすごく持つようになりました。それは僕らスタッフも含めて、です。なんとかして木本家(本名は木本龍雄)を支えるんだという思いで、どんなことにも立ち向かっていきました」
(取材・文/川合文哉)
※インタビュー後編では「秀樹さんに驚かされたこと」「カバー曲の秘密」など、さらにエピソードを紹介します。
【関連情報】
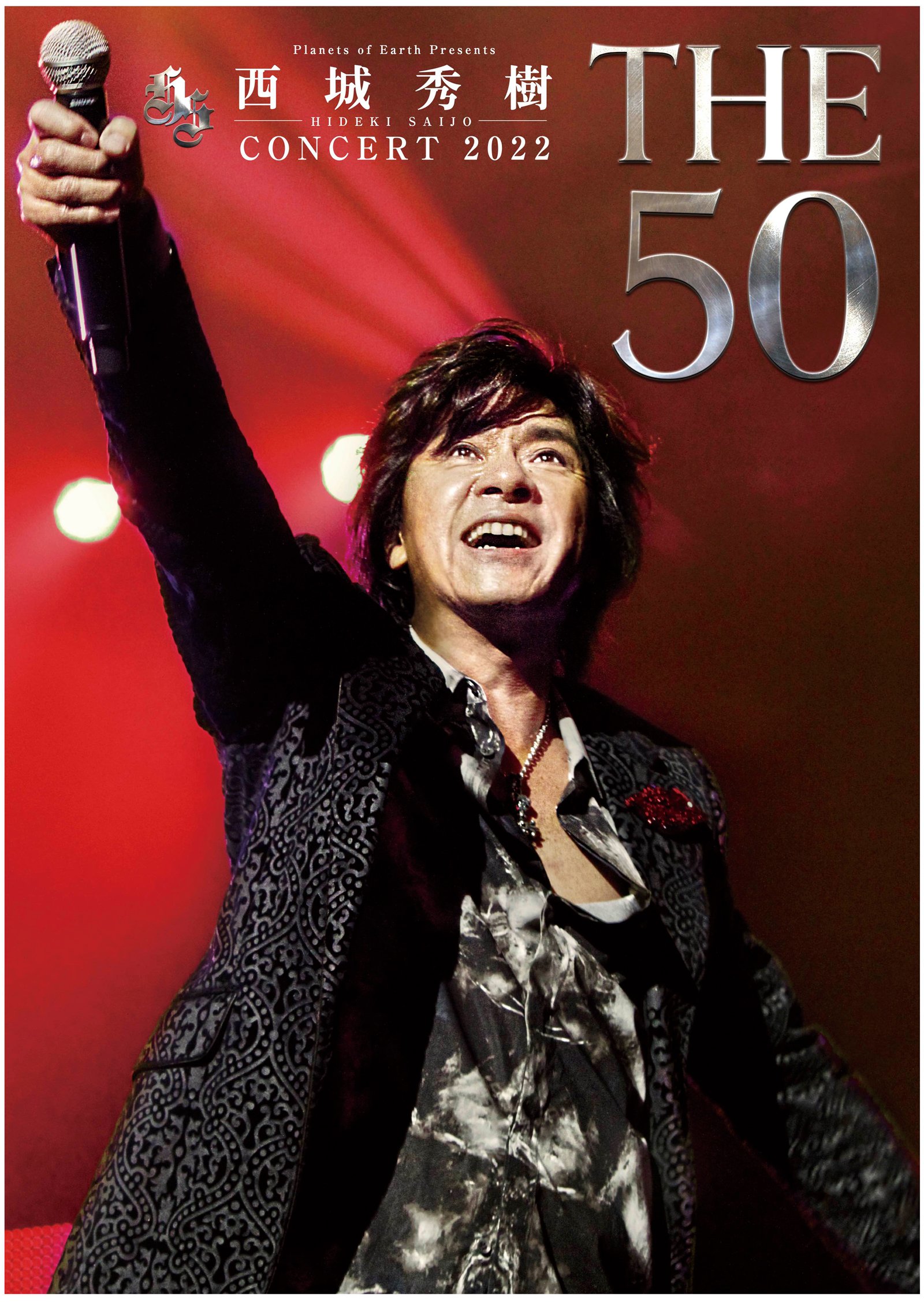
◎西城秀樹 コンサート2022「THE 50」
4月3日(日)17:00〜 神奈川県民ホール(横浜)
4月14日(木)18:00〜 オリックス劇場(大阪)
https://earth-corp.co.jp/HIDEKI/special/concert2022-the50/
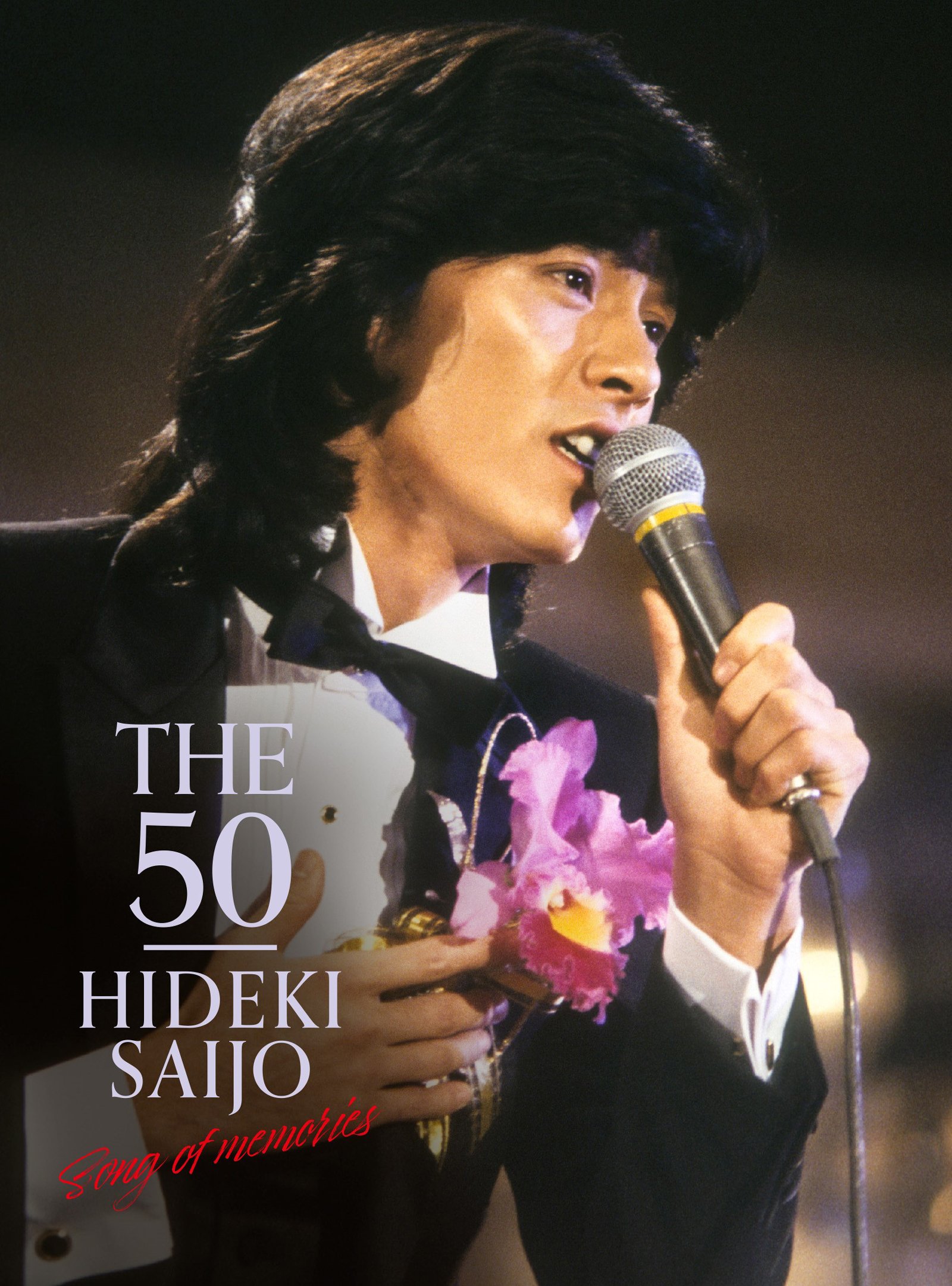
◎西城秀樹デビュー50周年記念7枚組DVD-BOX
「THE 50 HIDEKI SAIJO song of memories」
https://hidekiforever.com/page/the50hs-song-of-memories/
◎西城秀樹オフィシャルサイト
https://earth-corp.co.jp/HIDEKI/







