2015年、東京・北千住の下町のにぎやかな商店街を通り抜けた場所に、“しずけさとユーモア”を掲げ、ひとり出版社の「センジュ出版」を立ち上げた吉満明子さん。今や、本の出版だけでなく、文章の講座塾である『文章てらこや』を開いたり、コミュニティースペース「空中階」を運営したりしている、非常にユニークな出版社です。なぜひとり出版社を立ち上げたのか。やりがいや、つらかったエピソードなどを前編と後編に分けてお届けします。

無意識にあった本音に気づき生まれた心境の変化
──いつごろから、どんなきっかけで、センジュ出版を創業しようと考えたのですか?
「もともとは大手の出版社で、文庫事業部の編集長を務めていました。当時は、販売部数などの数字を追いかけることに喜びを見いだしていましたが、2011年の東日本大震災と、その翌年の長男の出産、このふたつの出来事が“私が本当にやりたかった編集”を、改めて考えるきっかけとなりました。それから“長きに残る本を作ってみたい”と、思うようになったんです。
その後、社会人になってからほぼ初めて、平日の日中に街中を歩くという経験を通して、これまで見えていなかった町の活気や、安らげる雰囲気などをこの北千住に感じるようになり、改めてここで暮らしながら、私にできる情報発信を行いたいと考えるようになりました」
──会社を退職すると同時に、すぐに出版社を設立されたのでしょうか?
「正直、センジュ出版を立ち上げる直前までは経営者になりたいだとか、出版社をつくりたいとかは夢にも考えていませんでした。当初は個人事業主として始めようと思っていたのですが、ありがたいことに立て続けにいくつかのお仕事をいただくなかで、取引先から“この取引額だと与信調査を入れなくてはならないため、個人ではなく法人化してほしい”との要望があり、急きょ、株式会社として会社を設立することになりました。そういう意味では、あまりドラマチックなスタートではないかもしれません」

──会社の設立前と設立当時では、価値観は大きく変わりましたか?
「そうですね。会社員のころは、多いときで年間30冊近くの本を作り、増刷がかかることにやりがいを感じるほど、数字にこだわって仕事をしていました。いつも巻き髪にネイルとつけまつげをして、ヒョウ柄のカットソーを着て、ガツガツ仕事を取ってくるような装いで、今とは別人でした。当時の座右の銘は『弱肉強食』でしたから。
その価値観が大きく変わったのは、東日本大地震であり、長男の出産でもあるのですが、それ以前にたまたま参加した『習慣力を身につける講座』で自分の無意識化にあった本音に気づいたことです」
──どんな出来事があったのですか?
「そのとき講師に投げかけられた“もしもこの習慣を続けた場合、起こる最悪の事態とはどんなことですか?”という質問で、このまま私が家族の“暮らし”をないがしろにし続けたら、“主人に三行半を突きつけられるだろう”という危機感が、頭をよぎりました。まさか自分がそんな恐れを抱えていたとは夢にも考えていなかったので。それで帰ってすぐに主人に講座で感じたことを話すと“離婚とは思ったことがないけれども、ちょっとうんざりしてた”と言われました。
当時の私はお盆も正月もなく仕事に明け暮れ、部屋のあちこちには原稿の束が散乱していました。しかし、それはノルマでも何でもなく、当時の上司にも“そういう働き方をすると、メンバーがひくからやめろ”と口酸っぱく言われていたくらいです。自分としては会社が伸びているこの時期に、“今ここでアクセルを踏まないでどうするの”という焦りや使命感を勝手に感じていたのだと思います」
──まさに仕事漬けの毎日だったわけですね。
「家の中には何日も洗っていない食器がシンクにあり、取り込んだままの洗濯物がそのままの状態になっていて、部屋の四隅はホコリの山になっていました。それでも家にいるときは、私はそれらを見ないように、感じないようにしていたと思います。
しかし、主人に本音を聞いた翌日から、出社する前に5~10分ほどかけてモノを少しずつ片づけ始めたんです。最初はテーブルの半分を、次の日はもう半分。そこが終わると部屋の中、その次は隣の部屋、家全体、そしてカバンのなかへと広げていくと、最後は“思考”が整理されていくようになりました。こうした行動の変化によって“本当に私が望んでいた編集のスタイルとは、こういうことだったのか”という、自分自身への問いが生まれていったのだと思います」

等身大サイズの自分になって見えてきたこと
──会社員を辞めて、ひとりでセンジュ出版を立ち上げたときは、不安はなかったのでしょうか?
「周りに促されるように会社を立ち上げたものの、自分のやりたい本作りができるという点では、非常に楽しさを感じていました。しかしその一方で、もちろん不安もありました。
編集者として何十年と出版業界に携わってきて、当然業界の構造は理解していましたし、それに最後の会社を退職する前は、小さな出版社の立ち上げに役員として関わっていたので、どのくらいの運転資金が必要で、何にコストがかかるのかも理解して、誰よりもリスクについては把握していたつもりです。それでも結局主人に言わせれば”周りが何を言っても、あなたはやるでしょ”という性格らしいので、不安よりもやりたいことが少し勝っていたのだと思います(笑)」
──前向きな気持ちでいられたということですね。
「自分が嘘偽りなく、世の中に問うていきたい本を“自由”に作れることが大きかったと思います。会社員のころのように、 企画書を書いて上司を説得し、予算を取っていく本の作り方も意味があり、私自身もそのなかで編集スキルを磨いてきたので大事さは痛感しています。ですが独立後は、世に残していく本を自分で自由に選び、作り上げられることに喜びを感じていました」

──今は協力してくれるスタッフも増えたとお聞きしていますが、改めて、ひとりで出版社を立ち上げるやりがいや醍醐味は、どんなところにありますか?
「私が、ひとり出版社を立ち上げてよかったと思うのは、“等身大の自分”で仕事ができることです。著者に会うときも、ありのままの自分でいられるので、相手も同じ目線になって私と話をしてくれます。“何万部、何十万部の本を売りました”と言っていた会社員時代は、そういう数字に魅力や正義を感じていて、そういうことで私自身も評価されていました。
それに比べてセンジュ出版は0の単位が2〜3つ少ない発行部数で、自分の等身大サイズの事業を行えるようになったことで、相手も飾らず私に向き合ってくれるので、誰にも話したことのない話が聞けるなど、飾らない人の美しさに触れることができるようになりました」
──具体的にはどういうことでしょうか?
「例えば、“誰にも今まで言ったことはないんだけど……”、“吉満さんだから聞いてほしい……”といった話を、たくさんの方がしてくださいます。決して活字にはならない話でも、その話を本人が吐き出さない限り、私たちが本当に聞きたいと思っている本音の部分が見えてきません。
つまり、その手前の、どこにも行き場がなかった感情や思いをまず言語化してもらうことでしか、著者の奥にある優しくてピュアな言葉には、たどり着けないのです。これは、等身大の私だからこそ、相手に踏み込むことで生まれてくるのだと思っています」

コロナ禍の絶望と起死回生の“感謝の手紙”
──反対に、これまでで一番つらかったことは何ですか?
「出版ビジネスは利益の回収に時間がかかります。設立して2年目には、出版以外にもカフェ『book cafe SENJU PLACE』の経営(現在は休業中)、文章講座『文章てらこや』などのサービスを展開し、会社は黒字化したものの、私の給料は2年間ほぼ出ませんでした。
また、スタッフが徐々に増えてきたときに、その人たちがセンジュ出版に求めていることをしっかりと汲み取ることができず、その結果、大切なスタッフの信頼を失い最後は袖を分かつようなことも起きました。
他にもいろんなことがありましたが、一番苦しかったのは、2020年の“新型コロナ”です。センジュ出版は、大きな出版社のように書店さんに大量に本を販売するのではなく、著者の人となりとともに、読者に本を手渡していくことで売上を立てていました。
そのためコロナによって、小さな空間で人が集まることや、著者と読者が直接会うことができなくなったことで、私たちは手足をもがれたような思いでした。当時は、私たちの最後の砦(とりで)を失い、いよいよ会社を畳まなければないところまで追い詰められていました。それによって、私も6月には2週間近くスタッフとやりとりできないくらいまで落ち込み、家の中に閉じこもってしまったのです」
──どのようにして復活されたのですか?
「そのときにひとつだけ決めたことがありました。それは“今回とことん落ち込みきろう”と。そうしないとまた同じことを繰り返す。付け焼き刃的に売上を立てるよりも、今後のために根本から打つ手を見直さなければならない気持ちもあったので、とにかく絶望しきろうと思ったんです。
結果、“もうこれ以上ここにいてもしょうがない”と思うまで閉じこもったおかげで、翌日には気持ちを切り替えて仕事を始められました。そのとき最初にしたのは、スタッフに対して“今までの読者ハガキやSNSの読書感想に対して、全部お礼を伝えてほしい”というお願いでした。
閉じこもっている間に反省したのが、忙しさにかまけて、本来すべきことをおろそかにしていたことです。会社には読者ハガキや読書感想という財産があったにもかかわらず、“読んでくださってありがとうございました”というお礼の言葉を何ひとつ伝えてこなかったんです。
“やるべきことをやってもいないのに、落ち込んでいる場合じゃない”と思ったので、会社がつぶれるにしても、読者の皆さんに感謝の言葉だけはしっかり伝えようと、みんなで協力して行いました。一方で私も、新たな読者を開拓するためのアクションに取り組みました」
──具体的には、どんな施策ですか?
「まだ当社の著者を知らない人が絶対にいると思ったので、まずはオンラインでの手法を必死に勉強して、著者との対談を企画しました。著者に対して、本を出した理由や本に込めた思いなどを視聴者に代わって質問し、本の魅力を伝えるコンテンツを配信。それによって、新たな読者を少しずつ増やすことができました。
そのほかには“お宅に本を直接、宅配します”というチラシをつくり、自分たちで千住エリアでのポスティングを実施。そのことをSNSで発信していたところ、千住にお住まいの大手出版社の営業部長さんと奥さんが“手伝わせてほしい”と言ってくださる、新たな出会いも増えました。今となっては絶望してよかったと思うことさえあります。もし絶望していなかったら、こうした新たな施策も生まれていないでしょうし、もしかしたら今ごろセンジュ出版もつぶれていたかもしれません」

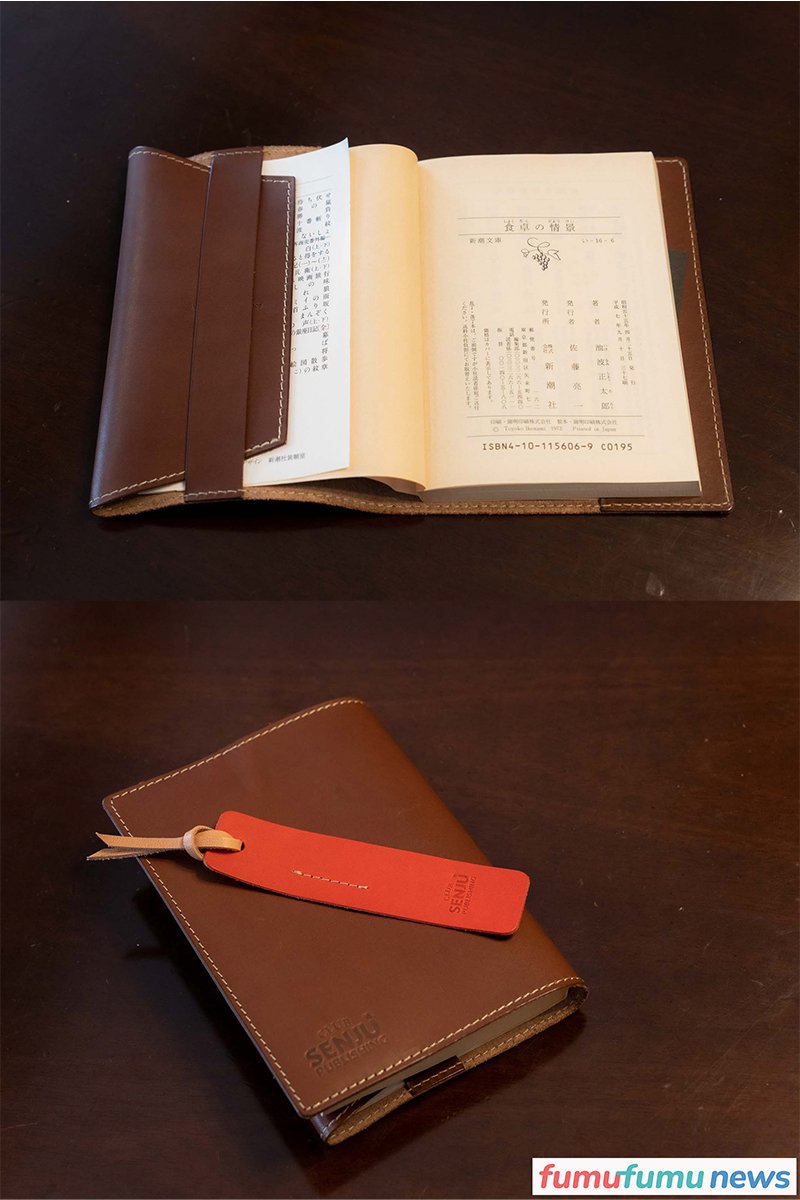
後編では、センジュ出版の2021年以降から現在につながる取り組みや、吉満さんの本作りにまつわるあれこれをお届けします。「新たに加わったスタッフが投げかけた問いによって、会社に明るい道筋が見えてきた」と話す吉満さん。その出来事を中心に、当時のことを振り返っていただきました。
(取材・文/西谷忠和、編集/本間美帆)
【PROFILE】吉満明子(よしみつ・あきこ) 1975年、福岡県生まれ。日本大学芸術学部文芸学科卒業後、高齢者福祉専門誌編集、美術写真集の出版社勤務を経験。その後編集プロダクションにて広告・雑誌・書籍・WEB・専門紙など多岐に渡る編集を経験し、同事務所の出版社設立とともに取締役に就任。2008年より小説投稿サイトを運営する出版社に中途入社、編集長職就任後に出産。2015年4月に出版社を退職、同年9月1日、足立区千住に“しずけさとユーモアを大切にする小さな出版社”、株式会社センジュ出版を設立。多数のメディアに出演実績を持つ。








