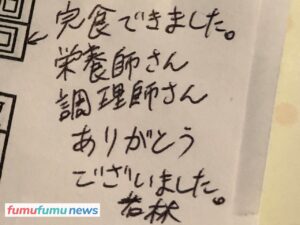「小学校の6年間、この子は場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)でした」
母がそう言ったとき、自分の子ども時代にひとつの名前がついた気がした。
バメンカンモクショウ。
6年間、私は学校で同年代の子たちと話すことができなかった。あの経験には名前があったのか。
言語能力には問題がないのに、家にいるときは会話ができるのに、学校でだけは、どうしても話せなかった。“自分は周りとは違う変な子どもなんだ”と思い込んでいた。
だが、違った。私は「場面緘黙症の子ども」だったのだ。
子ども時代は、社会生活において難なく話せるようになったいまの私と地続きになっている。
学校へ行くと、話したくても話せない
言語能力は正常であり、家では問題なく普通に話すことができるのに、特定の状況(例えば、幼稚園や学校など)においては声を出して話せないことが1か月以上続く疾患で、選択制緘黙症ともいう。話す必要があると感じても話すことができないほか、身体が思うように動かせず、固まってしまうことも。500人に1人ほどの割合で発症するといわれており、5〜10年以内に改善することも少なくないが、慢性化して成人になっても症状が続く場合もある。
休み時間になると、教室はいっせいに活気づく。校庭で遊ぼうとする足音と、おしゃべりする高い声が混じり合う。
「楽しそうやなあ」
そう思いながら、私は、ランドセルから本を出した。
「ひとりでいるのが好き」という雰囲気を出さないといけない。
本心は、目の前にあるものすべてから逃れたかった。私以外の「ちゃんと話せる」みんながとても幸せそうで、違う人生を生きているように見えた。
読書を始める。本のなかには、無限の可能性が広がっているように思えた。誰かが目の前にいるように感じて顔を上げると、クラスの男子と目の位置があった。
「あーいーうーえーお」
本の世界から現実の世界に引き戻される。
「言えるやろ。あーいーうーえーお」
私は「あ」の形を作りかけるが、声を出せない。
「もう、やめえや」
女子が近くで笑いながら言った。
私は泣き出した。泣いた私の周囲が、さっきよりも、もっとざわめく。
「ほんまは話せるくせに。泣いたら先生から味方してもらえるって思ってるやろ」
目の前にいた男子が、吐き捨てるように言った。
ドロドロとしたものが、胸の中にあふれてくる。
このドロドロは、いま初めて生まれたものじゃない。小学校に入学してからずっと、私の胸にあるものだ。
家のなかではうるさいくらいよく話すのに、学校だと、とたんに話せなくなる。言語能力は正常だそうだ。
ほかの子と同じようにちゃんと話したいと思えば思うほど、私は口を開くことができなくなった。どうしてそうなったのかはわからない。ただ、自分は同年代の子たちのなかで、異質な存在なんだと感じていた。

転校先でも進学先でも悩まされ続けた
それが「場面緘黙症」という症状で、苦しんでいたのは私だけじゃないと知ったのは、大人になってからである。
勤務していた会社での日々がつらくて、うつ状態になった私は、母と一緒にメンタルクリニックを受診した。
「いままで、何か精神疾患を患ったことは?」
医者から聞かれたとき、母は私の前で初めて「小学校の6年間、この子は場面緘黙症でした」と言った。
私の記憶にはないが、児童精神科で診断も受けていたらしい。
病院を出て、なぜいままで教えてくれなかったのかと母に聞いた。「傷つくと思ったから」という言葉が返ってきた。
確かに子どものころなら、「自分は心の病気なんだ」とショックを受けていたかもしれない。
だが15年後、大嫌いだったあのころの自分にひとつの名前がついて、大人の私は安心していた。自分だけが苦しんでいるわけではないと、わかったから。
そのあと、いろいろと調べていくうちに、中学生時代に不登校になったことも、小学生のころの場面緘黙症が原因だったのでは? と思うようになってきた。
小学6年生の2学期、父親が一戸建ての家を買った。それに伴い転校した私は、「今度こそクラスの子といっぱい話して、楽しい学校生活を送ろう」と心に決めた。転校先の小学校では、話せない私を誰も知らない。
転校した日の休み時間、女子たちが私を取り囲んで、ひとりひとり自己紹介をしてくれた。同じ大阪とはいえ、転校前の学校より田舎だったせいか、みんな素朴に見えた。
一生懸命、話した。
周りの反応がわからないほど、私は「話すこと」に必死になった。
話し終わったあと、周囲を見わたすと、みんなが奇妙なものを見たときのような表情をしていた。
私は、話しすぎてしまったことに気づいた。自分が言ったことに対しての、誰かの言葉をさえぎったような気もする。
大人になってから考えると、あの瞬間の私は、ほかの子どもたちが日常生活で無意識のうちに訓練を受けているはずの「人の話を聞くこと」「自分が話し終えるタイミングを見極めることができなかったのだろう。
「あの子、空気読めないんやな」と言われるようになり、転校先でまたひとりぼっちになってしまった。
半年後、進学した中高一貫の女子校でも、同じようなことを繰り返した。
クラスメイトとの会話に慣れていないせいで、話した相手の内面にどこまで踏み込んでいいのか、わからない。友達とたくさん話して、楽しい中学校生活を送りたかった。
しかし、小学校のころと同様に孤立したとき、私はかつてない劣等感に苛(さいな)まれた。「もうダメだ」と思った。
「“うまく会話ができない変な人”というイメージは一生、私につきまとうんだ」
そう思い込んだ私は、どんなに親に叱られても、先生に諭(さと)されても、中学1年生から2年生の終わりまでの約2年間、登校しなかった。
場面緘黙症をを克服した時期と、克服できた理由はいまだにわからない。不自然とはいえ学校で話せるようになっていたから、中学生の私はもう場面緘黙症を克服した、と当時の主治医も母も思っていたそうだ。
しかし、場面緘黙症との共存から解き放たれたばかりの私に必要だったのは、友達とスムーズに会話しようと頑張ることだったのだろうか。焦らずに、学校という社会に溶け込む方法を、理解してくれる大人と一緒に探すべきだったのではないだろうか。
小中学生の居場所は、学校と家庭だけであることがほとんどだ。学校で人間関係を培えなかった私は、「人生に失敗した」と思い込んでしまった。
その原因は紛れもなく、場面緘黙症を患っていた小学生時代にあった。

誰かを“異質な存在だ”と排除する前に
場面緘黙症は、ほとんどの人が数年で治ると言われている。私もそうだった。
だが、治ったあとの学校生活も、思うようにうまくいかなかった。いじめられる日々が続いた。
疎外感を抱えて自分を取り戻せないまま、もしくは、場面緘黙症を患ったまま成人する人もいるという。
「大人になる前に克服できたりおちゃんは幸運だったね」と言われることもあるが、それで終わらせていいのだろうか、と最近思う。
場面緘黙症だった過去は、いまの自分を形づくる要素のひとつになっているからだ。
私には、特技がある。
自分がなるべく傷つかないための防護柵をはることだ。
「この人、今、〇〇が嫌だと思っているな」といち早く気づくことができるので、知人・友人が自分と離れたいと思っているとき、私はなるべく早く身を引く。
7歳から12歳まで、場面緘黙症のせいで、ずっと自分は異質な存在だと感じ続けてきた。クラスメイトと仲よくなりたいのに、傷つくのが怖くて、ひとりでいるのが好きなふりをした。
だから、誰かと離れたあとに「ひとりでいても平気」というふりをするのが上手になった。
電車に乗っていて、特定の人に違和感を抱(いだ)くことはないだろうか。
奇声をあげている人を見て、“気持ち悪い”と思ってしまうことはないだろうか。
目をそらす前に、少しだけ想像してみてほしい。
その人たちも、もしかしたら、小学校のころの私のように、自分ではどうすることもできない苦しみに立ち向かっている最中なのかもしれない。
私たちには見えていない世界と、戦っているのかもしれない。
そしてまた、目立たなくても、「ひとりでいても平気」という演技をしながら、自分の傷を隠す人が、今もいるはずだ。
大人も子どもも関係ない。
場面緘黙症だけではなく、異質な存在を「自分たちと違うから」とすぐに排除せずに、一度、想像力を働かせてみると、彼らと近い視点で物事が見られるようになるのではないかと感じている。
(文/若林理央)