今から600年近く前、沖縄県は「琉球王国」と呼ばれ、日本とは異なる独自の文化を育んでいました。
1429年から1879年の450年にわたって存在していた琉球王国の遺産としては、首里城(現在は再建・復興中)ほか、たくさんのグスク(城)や史跡が県内全域に点在していますが、ウチナーンチュ(沖縄の人)の日々の暮らしに欠かせない食文化にも王国の名残りが。今回は、海外の使節団をもてなすために宮廷で作られていたとされる、「琉球菓子」を伝承する人物を紹介します。
琉球王国時代の正統な味、ごまと黒糖から作る「こんぺん」は創業当時から
1935年創業の「南島製菓(なんとうせいか)」は、那覇市の真ん中にあるお菓子屋さん。87年ものあいだ(2022年現在)、沖縄の人たちに愛されてきました。
和菓子に洋菓子、手みやげやお茶請けにしたくなる、たくさんのお菓子がショーケースに並んでいますが、このお店の名物といえば、琉球菓子「こんぺん」(沖縄の言葉で「くんぴん」)。見た目が素朴な焼き饅頭(まんじゅう)で、おやつとしていただくこともありますが、行事の際のマストな1品です。琉球王国時代の高級菓子で、ご先祖様への最高のお供えものという意味合いがあります。
材料に製法に味。創業者である祖父の「こんぺん」を受け継ぎ、老舗の名に恥じない努力を続ける4代目・村吉政人(むらよし・まさと)さんの半生に迫ります。

「僕は南島(なんとう)の日に生まれたんですよ」と笑顔で話し始めた村吉さんの生年月日は、1978年7月10日。なるほど、誕生日が「なんとう」と読め、生まれた日から店主になる運命だったと思わせるエピソードです。
店名の「南島」は琉球諸島を表す縁起のいい言葉ということで、創業者のおじいさま・村吉政能(むらよし・せいのう)さんが「南島風土記」という古文書から引用して名づけたとのこと。
「祖父は那覇市東町にあった『さちまのクヮーシヤー』(標準

現在は数々のお菓子屋がこんぺんを製造していますが、餡の主流はピーナッツ。米軍関係者から入手しやすい材料なので、戦後に広まったとされています。しかし、琉球王国時代の正統なこんぺんに入っていたのは、ごまと黒糖から作る餡。40年来の付き合いのある業者から仕入れたごまと県産黒糖を使うなど、材料も伝統もこだわり続けているのが南島製菓なのです。
そんな歴史ある老舗菓子店を実家に持つ村吉少年は、どんな幼少期を過ごしたのでしょうか。
商売繁盛の陰で過ごした寂しい幼少期、家を離れたくて東京へ
「子どものころの家族の思い出はほとんどありません。商売が忙しくて、子どもにかまう状況ではなかったんでしょうね」と語る村吉さんは、千葉出身であるお母さまの苦労話を続けます。
「当時の沖縄は他県の人に厳しい風潮がありました。そのうえ歴史ある商売一家ですから、家族から母への風当たりは当然、強かった。でも母は諦めることなく、ここでの生活を続けてきたんです。今思えば、母の生きざまから必死に生きることを学んだ気がします」
おじいさまのお菓子作りの確かな腕とアイデアあふれる商才で、南島製菓は大繁盛。県内で初めて、ちんすこう作りを機械化し、首里城をかたどったおみやげ菓子を作るなど新たな挑戦を続けます。また、本土の菓子メーカーの問屋になったり材料販売も始めたりと業務を広げ、会社として大きくなっていったそう。
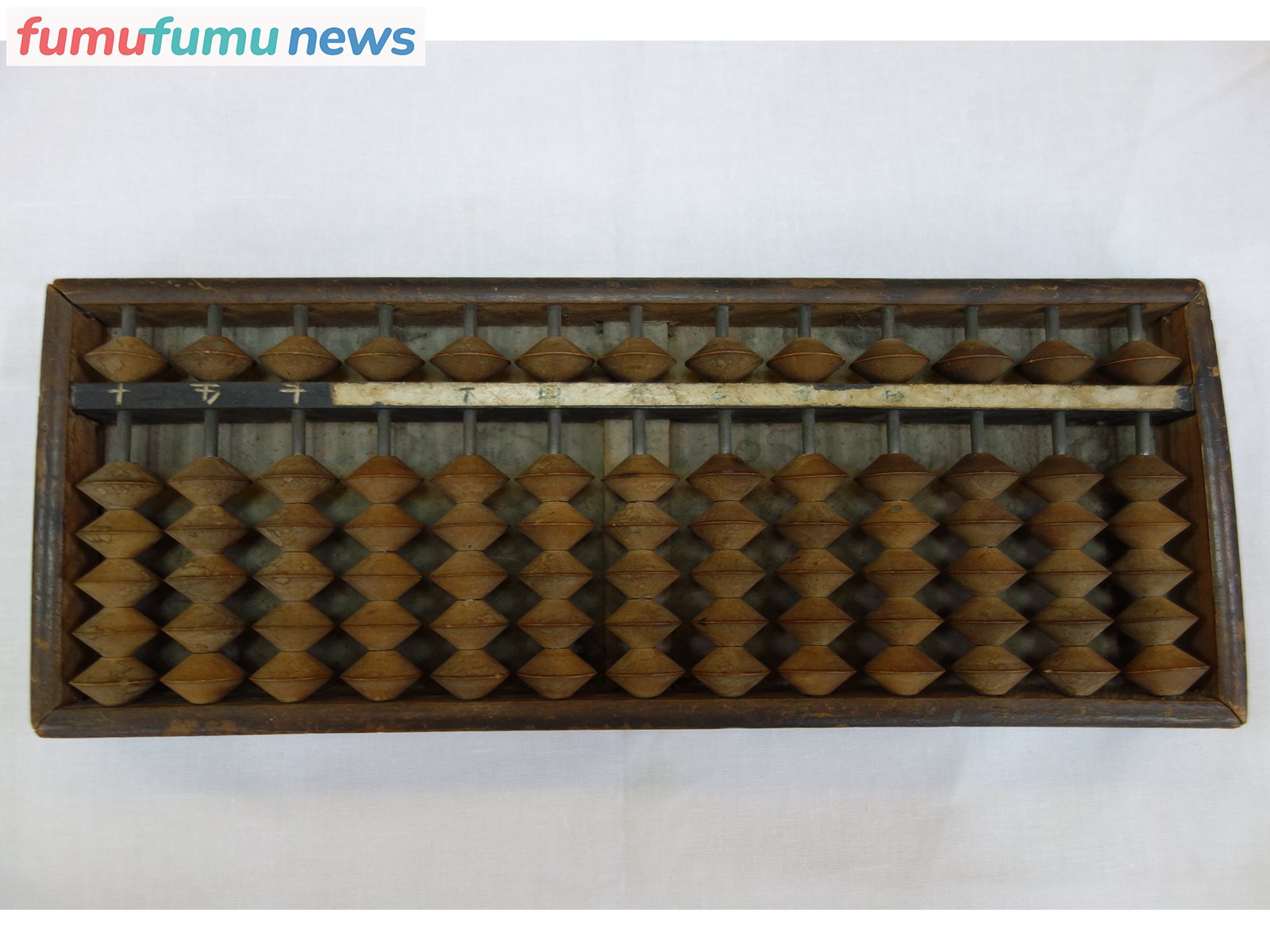
必然的に村吉家の家業となり、おじいさま亡きあとは弟が2代目、次男が3代目と跡を継いでいきます。長男である村吉さんのお父さまも、店舗運営を支えてきたため家族と触れ合う時間があまりありませんでした。その時期の、つらそうなお母さまの姿も見ていた村吉少年は、寂しさを感じていたのでしょう。
「家にはいたくないという気持ちが膨れあがり、高校卒業後、逃げ出すように東京に行きました」と遠くを見つめます。
上京してアルバイトを探したそうですが、財布に数十円しか入っていない日もあったという村吉さん。アルバイト先の店長からもらった100円で買ったカップ麺1個のみで一日をしのぐなど、今から25年くらい前の出来事とは思えない体験をしたようです。

「しばらくはそんな生活を続けていました。寮完備の飲食店に勤め、昼夜関係なく馬車馬のように働いていたのが、東京で過ごした4年間の思い出です。その後、大阪に住んで1年たったころ、友人からバーを経営しようと誘われ、開店準備に取りかかりました。でも、その最中に実家から連絡があったんですよ」
それはお母さまからで、「職人さんたちの高齢化が進み深刻な状況。帰ってきてほしい」というお願いでした。
当時、中心になってお店を切り盛りしていたのは、どんなに忙しくても孫の村吉さんを気にかけ、愛情を注いでくれたおばあさま。「僕はおばあちゃん子でした」と認める村吉さんは、孝行をしたい一心で家業を継ぐ決意を固め、沖縄に戻ったそうです。
経営難と大切な2人の死。代表就任後に直面した悲劇を乗り越えて
’02年、南島製菓に入った23歳の村吉さんは一念発起。工場での修業から始めます。当時の先輩職人たちの指導は「見て覚えろ」方式でとても厳しく、ひとりで涙する日も多かったそう。過呼吸の症状が出るほどの大変な日々を過ごした、と振り返ります。
「嫌がらせもありました。でも、やめようと思ったことは一度もありません」
家業を継ぐ村吉さんの覚悟はそうとう強かったのでしょう。重ねた努力が周囲に認められ、村吉さんは10年後に代表に就任。達成感とうれしさを感じながらさらなる高みを目指し、「より専門的にお菓子作りを学びたい」という思いで、調理師専門学校に入学しました。
早朝に工場に出て製造業務に取りかかり、時間になると学校へ。そして戻ってきてから、また仕事。そんな日々を続ける中、厳しい経営状態に直面したそうです。

おじいさまである故・村吉政能さんが地域に根ざしたお菓子屋を開店し、隆盛を極めた南島製菓でしたが、2代目が推進する多角経営の失敗で、7億円の負債を抱えることに。その後、3代目になったとき、建物4
「 ’15年に親友が亡くなりました。幼稚園からの幼なじみで、一緒に東京にいた時期もあります。彼が末期ガンを宣告されてからは、一日の終わりや仕事の合間など、可能な限り見舞いに行きました。最後は僕が病院に来るのを待っていたようで、呼びかける声を聞いた瞬間に息を引き取りました」
深い信頼で結ばれていた親友を失い悲しみにくれる村吉さんでしたが、2年後にも悲劇が起こりました。
「右腕だと思っていた職人さんが工場で亡くなりました。普段どおり業務の話をして、一瞬、目を離した隙に倒れていたんです。救急車で病院に運びましたが回復せず、心臓にダメージがあったと後から知りました」
気心知れた親友と頼りにしていた職人さん。身近な2人が自分の目の前で死を迎えた悲しい経験から、「明日死ぬかもしれないと考えるようになりました」と語る村吉さん。
「中途半端なことはしないという思いが強まりました。とはいえ、店も家族も守らなければならないので、がむしゃらに突っ走るわけにはいきません。背負うような重荷を感じることなく、今あるもの、受け継いできたものをつなげていこうと考えるようになりました」
精神面でも資金面でもつらかった村吉さんですが、苦難を乗り越えながら老舗店を守り抜く覚悟ができたといいます。そして家族と職人・店員の力を借り、新たな取り組みを始めていきます。
まずは、おじいさまのもとで働いていたベテラン職人を呼び戻し、専門学校に行っている時間に工場に入ってもらったそう。「こんぺん」をはじめとするお菓子の製造方法やお店のことなど、60年以上前のことを教わる機会にもなり、当時のこだわりや誇りが深まったのではないでしょうか。

そして「こんぺん」の新パッケージを開発。お店のイメージカラーであり、琉球王国時代に高貴な色とされていた紫を基調にした袋を作り、個包装して高級感を出しました。また、食べやすいミニサイズを販売したことで、おみやげとしてチョイスしたいお菓子へと進化します。

’20年2月には、日系航空会社の国内線ファーストクラスで振る舞われるお菓子に選ばれました。
また、販路拡大を目指し、’21年秋に東京向けの商談会に参加。ですが、「こんぺんはおろか、琉球菓子のことを誰も知らない状況でした」と、悲しい現実にぶち当たったことを明かします。
失意の中でなんとか1件、契約寸前までこぎつけたそうですが、発送準備をしていたところで、相手との連絡が途絶えてしまったそう。
「セレクトショップにこんぺんを置いてもらう契約を進めていましたが、東京の厳しさを改めて実感しました」と村吉さんは苦笑い。
「このままではダメだ。琉球菓子とお店のブランディングを強化して知名度を上げ、先方から声をかけてもらえるくらいにならなければ」と心に誓ったといいます。悔しさをバネに、気持ちに火がついたのですね。
コロナ禍でも忘れないモットーは「つなげる伝統 ちむぐくる(真心)を込めて」
強い意志と新たな決意で、琉球菓子のブランド力アップに奮闘する村吉さんでしたが、コロナ禍の影響もダイレクトに受けます。
「シーミー(清明節)や旧盆など、沖縄の年中行事も簡素化する流れになりました。それに伴い、こんぺんをはじめとした琉球菓子の売り上げがガクンと落ちていきました」
心の中で「このままでは、先祖代々続く店を自分の代でつぶしてしまう」という危機感を抱くこともあったようですが、不安に打ち勝つのが村吉さん。ある行動に出ます。
「店舗のリフォームを計画しました。南島製菓を愛してくださるみなさまを大切にするのはもちろんですが、なじみのない方でも入りたくなるお店にできないか、と考えました」
資金もない、売り上げ不調の中、リフォーム費用の工面はどうやって!? と思ってしまいましたが、意外なことにコロナ禍がきっかけを与えてくれたそうです。
「事業を再構築するコロナ禍の補助金を活用してみては」というアドバイスをもとに、銀行への手続きを進めます。ですが残念ながら条件に届かず、実現には至りませんでした。
「ただ、リフォームに向けて気持ちが高ぶっていたので何とかしたいと思い、ダメ元で金融公庫(※沖縄振興開発金融公庫)さんに相談しました。対面が難しかったので、どんな店舗にしたいのかなどを、まずは手紙で伝えることに。便せん3枚に思いをつづり、相談を重ねるうちに認めてもらえたんですよ」
先祖から継いだ歴史ある菓子店を続けていきたい、という村吉さんの熱意は、国の機関である金融公庫にも好意的に映ったようです。その手紙のおかげで、リフォーム費用の借り入れがかなうことに。熱い気持ちを原動力に、さまざまなことを動かしていくエピソードが、またひとつ増えました。
店舗は’21年10月に施工を始め、’22年2月17日にリニューアルオープン。沖縄の伝統的な染物「紅型(びんがた)」の大きな暖簾(のれん)を店頭に掲げ、しっくい壁で囲んだ落ち着いた内装です。築50年の昔ながらの雰囲気から、スタイリッシュに生まれ変わりました。

「リフォーム後はとてもいい流れになっています。売り上げが好調で、過去最大の注文も入りました。こんぺんが『那覇市長賞100周年特別賞』を受賞するうれしい知らせもありました」と笑顔を見せた村吉さん。
これまでは店の前を通りすぎていたと思われる若い層や男性客を取り組むことにも成功し、着実に業績を伸ばしています。
「コロナがはやり始めた2年前に、様子見のつもりで3日間、閉店しましたが、その後は店を開け、リフォーム中も休むことなく営業しました。取引先、そしてお客さまとのコミュニケーションは信用につながりますので、一日たりとも穴を開けたくありません。その体制も、現在のいい状況につながっていると感じています」

不屈の精神で数々の壁を乗り越え、経営を上向きにしている村吉さん。修業時代から20年間、家業である老舗菓子店に身をささげていますが、そのモチベーションはどこから湧き出ているのでしょうか。
「<元祖>こんぺんを残すこと。単純な理由ですが、南島製菓が続けていかなければならないという使命感を持っているんです」と、目を輝かせます。
温故知新の心で、脈々と受け継がれる琉球のアイデンティティを形にする村吉さんは、出会う人に「ちむぐくる(真心)」で接しながら、老舗菓子店の4代目として快進撃を続けます。
(取材・文/饒波貴子、執筆協力/Shotaro)
所在地:沖縄県那覇市那覇市松尾2-11-28 浮島通り
電話:098-863-3717
営業時間:月〜土9時〜18時/日10時〜17時
定休日:正月(1月1日〜3日)
駐車場:なし







