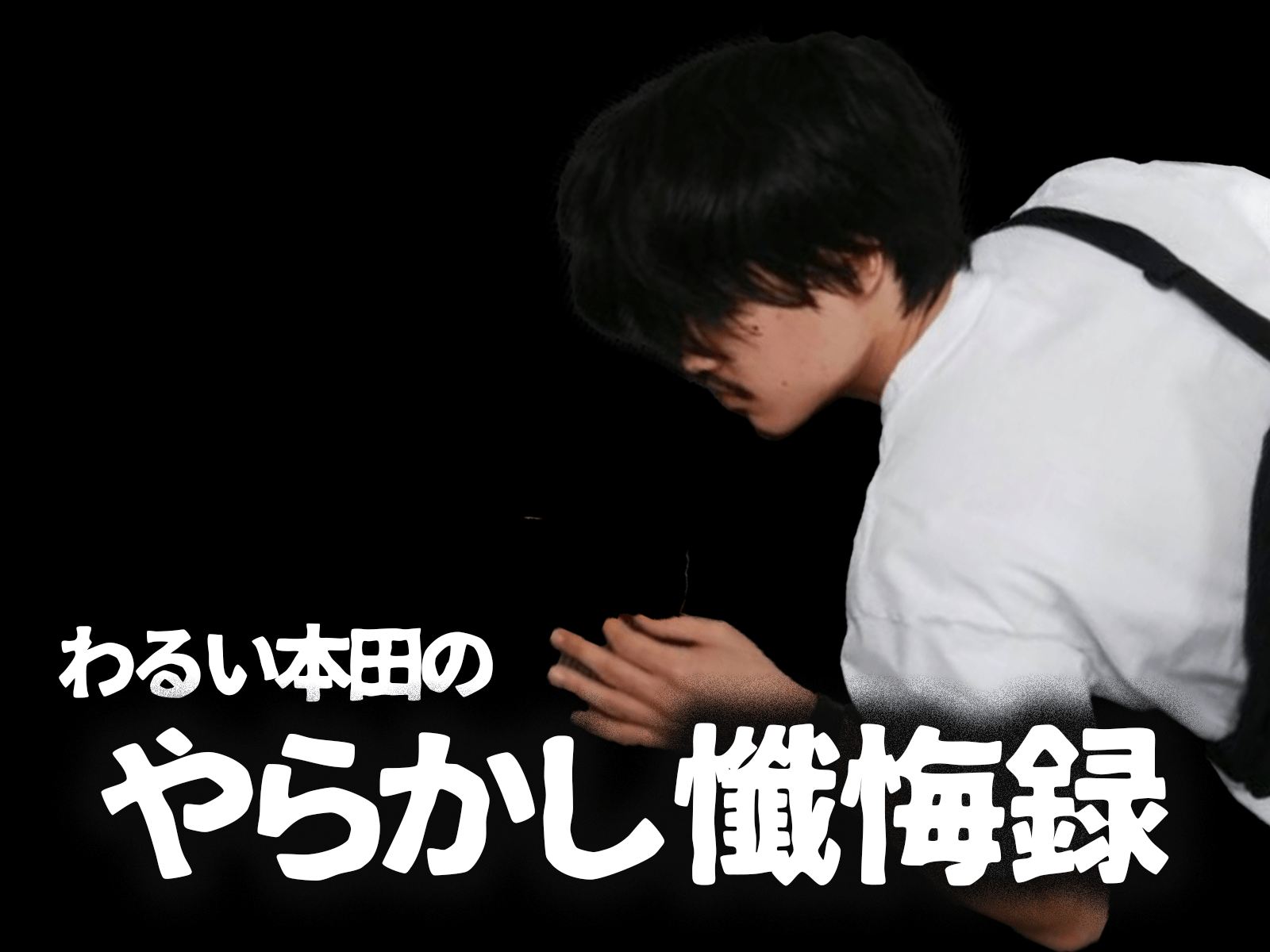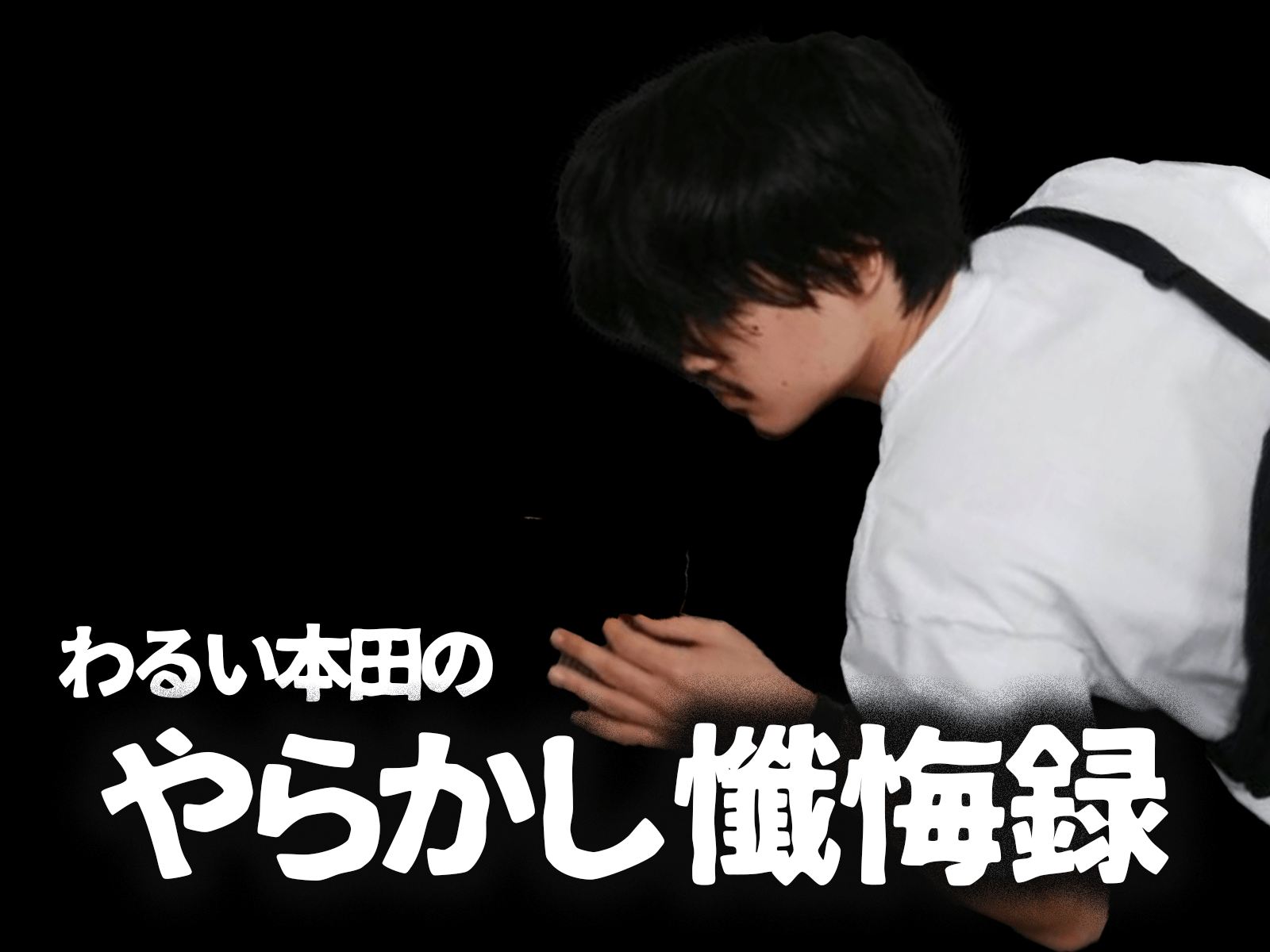破滅的に女性にモテなくなる趣味が三つ存在する。「パチスロ」と「カードゲーム」と「メダルゲーム」である。僕はこれらを「男の三大非モテ趣味」と呼んでいる。どれも女性の人口が極端に少なく、絶望的に将来性がないことが主な理由だ。どれか一つでも摂取すると人生が変わってしまう劇薬だが、悲しいかな僕は三つ全てにハマっている。御多分に洩れずそれぞれの領域にやらかし話があるのだが、今回は「メダルゲーム」で起きてしまった悲劇的な出来事について懺悔したい。
大学一年生の時、僕は四つ年上の先輩の「涼子さん」という人と付き合っていた。篠原涼子氏のファンだという彼女の両親の願いが通じたのか、容姿が整っていて魅力的な外見を持った女性だった。強烈に「女」を感じる話し方と身振りをする人だったので、男性からは非常にモテるが女性の友達が一人もいなかったのを覚えている。どうしてこんな人が僕と付き合っているのだろうと都度考えたが、人間には一瞬の気の迷いというものがある。何らかのタイミング、何らかの血迷いなのだろうと、深く考えずにいた。
涼子さんは西武新宿線の上石神井駅近くに住んでおり、僕は自堕落にも連日そこに入り浸っていた。当時の僕は「ハイパー楽して生きてやろうスタイル」の極致に達しており、所属していたバンドサークルの活動も保留し大学の授業にも一切行かず、毎朝涼子さんの家からパチンコ屋に通っていた。
そんな僕に対して涼子さんは甘かった。小学校の先生として働いていた涼子さんは毎朝、出勤する前に食事を作って冷蔵庫に準備してくれたし、お金がない時にはパチンコの軍資金も貸してくれた。仕事から帰って来ると「今日はパチンコどうだった?」と笑顔で聞いてくれる菩薩のような人で、「この人がこんなに甘やかすから僕はパチンコがやめられないんじゃないか?」と強く恨んだ事もあった。
そんな無限の慈悲を注いでくれる涼子さんのために僕がやっていた事といえば、一緒に煙草を吸う事、ほんの少しの皿洗いをする事、そして、涼子さんが作った「知育用教材」の実験台になる事だった。この習慣は僕と涼子さんの異常な関係を物語る上で重要な因子である。
小学校一年生のクラスを担当していた涼子さんは小さい子向けの教材を自作していた。様々な可愛らしい動物が登場する紙芝居で、楽しみながら読んでいくうちに自然と頭が良くなるという素晴らしい教材である。そして自作した新作教材の出来を確かめるために駆り出されるのが、年中暇を持て余していた僕であった。僕は小学生の気持ちに戻って、ゾウさんやシマウマさんが乱舞する物語を楽しみ「ぞうさんは にひき おみず をのみにいってしまったので、あと さんびき のこっています!」と答える役目だった。その後ならば「明日、海物語打ちたいから三万貸してくれない?」という交渉がスムーズに通ったのである。
そんな毎日を半年ほど繰り返していたのだが、ある日涼子さんが「本田が考える理想のデートに連れて行って欲しい」と言ってきたことがあった。目は少しだけ疲れていた。
「涼子さんも日頃の仕事で大変なのだろう」と合点した僕は、一念発起して理想のデートプランを練り始めた。だがデートのエスコートなど全くした事がなかった僕は、行くべき場所が全く思い浮かばない。ましてや男に事欠かない涼子さんである、大体のそれらしい場所には足を運んだであろう。行き詰まった僕は初心に戻り「自分はどこに行くと一番楽しいか」を考える事にした。導き出した答えは「メダルゲーム」であった。
「どうぶつ を ねらって メダルを いれてね〜!」
僕と涼子さんは都内某所のゲーセンのメダルコーナーにいた。僕が日夜足を運ぶこだわりのお店である。どうですか涼子さん。これがメダルゲームです。数字が書いてあるバスケットゴールにシュートするゲーム、うさぎさんが持つお皿に頑張ってメダルを乗せるゲーム、シンプルにじゃんけんに勝つゲーム。これでもかと言わんばかりのメダルゲームが取り揃えられています。どれもが歴史という荒波に振り落とされず生き残ってきた名機達です。涼子さんの知育教材にも役立ちそうではありませんか。子供っぽいのだけじゃありません。大きな画面で大迫力の競馬を楽しんだり、大海原へお魚を釣りに行けたりもします。
涼子さんは仕事でだいぶ疲れているのか、とても暗い表情だった。僕は漢気を見せようと千円札をメダル両替機に入れた。ジャラジャラと出てくるメダル。それをコップを使って半分ずつに分けて涼子さんに渡した。奢りである。
涼子さんはそれを受け取ると、ぎこちなさそうに遊びだした。分かります。最初は恐る恐るでしょう。それでも一度、一攫千金を経験すればその興奮が脳裏にこびりついて、ただメダルを投入するだけで脳に鳥肌が立つようになるのです。それは脳汁というやつなんです。涼子さん。今はそんな楽しくなさそうですけど、そのうち分かります。
メダルゲーム新入生の涼子さんを温かい眼差しで見守っていると、ある出来事に気がついた。しまった。メダルがもう無くなりそうである。僕は涼子さんに良い所を見せようと、ハイリスクハイリターンの博打台にメダルを投入し過ぎてしまっていた。
焦った僕は「早くメダルの洪水を引き起こさなければ」と、メダルを追加購入するために財布を取り出した。すると、財布の中にお金がない。しまった。直近のパチンコで手痛い負けを喰らっていたのであった。動揺する僕。だがここで引くにはもう遅すぎる。台にメダルを入れ込み過ぎてしまっていたのだ。この店の常連であるあの中学生達にハイエナ等されたりしたら堪ったものではない。そこで僕は「ここは、先ほどの奢りと見せかけた千円を『割り勘するはずのものだった』ということにして、次の千円は涼子さんに出してもらおう」と思いついた。誰がどう考えても名案だった。
「次は涼子さんがメダルを買ってください!」僕は、僕と涼子さんがメダルの洪水を引き起こすための一蓮托生の仲間である事を自覚せしめる声色で、そうお願いした。清らかでフェアな提案だった。台から止めどなく溢れ出てくるメダルを見れば、涼子さんも表情が明るくなるに違いない。本気でそう思っていた。もしかするとこれを機に今後のデートはメダルゲームが定番になるかもしれない、僕はそんな可能性にさえ期待していた。
と、その刹那。
バーーーーン!!!!!!
何かを打ちつけたような、激しい衝突音が聞こえた。後ろを振り返る。メダルゲームで遊んでいた小学生や中学生が、皆その方向を見ている。
眼差しの中心は、涼子さんだった。
顔は俯いていた。肩をわなわなと振るわせ、前髪の奥から見えるその綺麗だった瞳は僕を睨みつけているようにも見えた。というか、めっちゃ睨んでた。身につけていたハイブランドのバッグは肩から落ちて、床に接着している。メダルゲームの台に叩きつけた彼女の手の中には、グシャグシャになった千円札が握り締められていた。
鬼のような形相で僕を凝視する涼子さんは、僕がいつも見ていた涼子さんではなかった。その光景に完全に萎縮してしまった僕は、数秒硬直した後「え、ごめんね……」と絞り出すように声を発した。うまく声が出なかった。そして、そのあまりにもか細い声が届く前に、彼女はそこから立ち去ってしまった。
空のコップを手にしたまま動けなくなる僕。メダルゲームコーナーにいる全員が、遊ぶ手を止めて一部始終を静観していた。
「メダルを入れてね!」
あまりにも空気の読めない言葉が、空中に木霊していた。普段は愉快な遊び相手であるはずのメダルゲームの筐体の自動音声は、この時初めて、少しだけ無機質なものに聞こえたのを覚えている。嗚呼、この場所にいる全員が、この出来事が起こった原因を、心の底から理解することはできないのだろう。なぜ彼女が怒り、取り乱し、金だけを置いて帰ったのか。彼女が感じた無限にも等しい虚無の類を、ここにいる我々が理解することは不可能に近いのである。だってメダルゲーム楽しいもん。
少し遅れて店を出たが、涼子さんは見つけられなかった。
そんな涼子さんへ謝りたい。ごめんよ。メダルゲームなんかデートに選んじゃって。
でも、まだ貴女はメダルゲームの本当の楽しさを理解していないと思う。だから次回があれば、今度は友達として一緒にどうですか。
(文/わるい本田、編集/福アニー)
【Profile】
●わるい本田
1989年生まれ。YouTubeチャンネル「おませちゃんブラザーズ」の出演と編集を担当。早稲田大学を三留し中退、その後ラジオの放送作家になるも放送事故を連発し退社し、今に至る。誰にも怒られない生き方を探して奔走中。