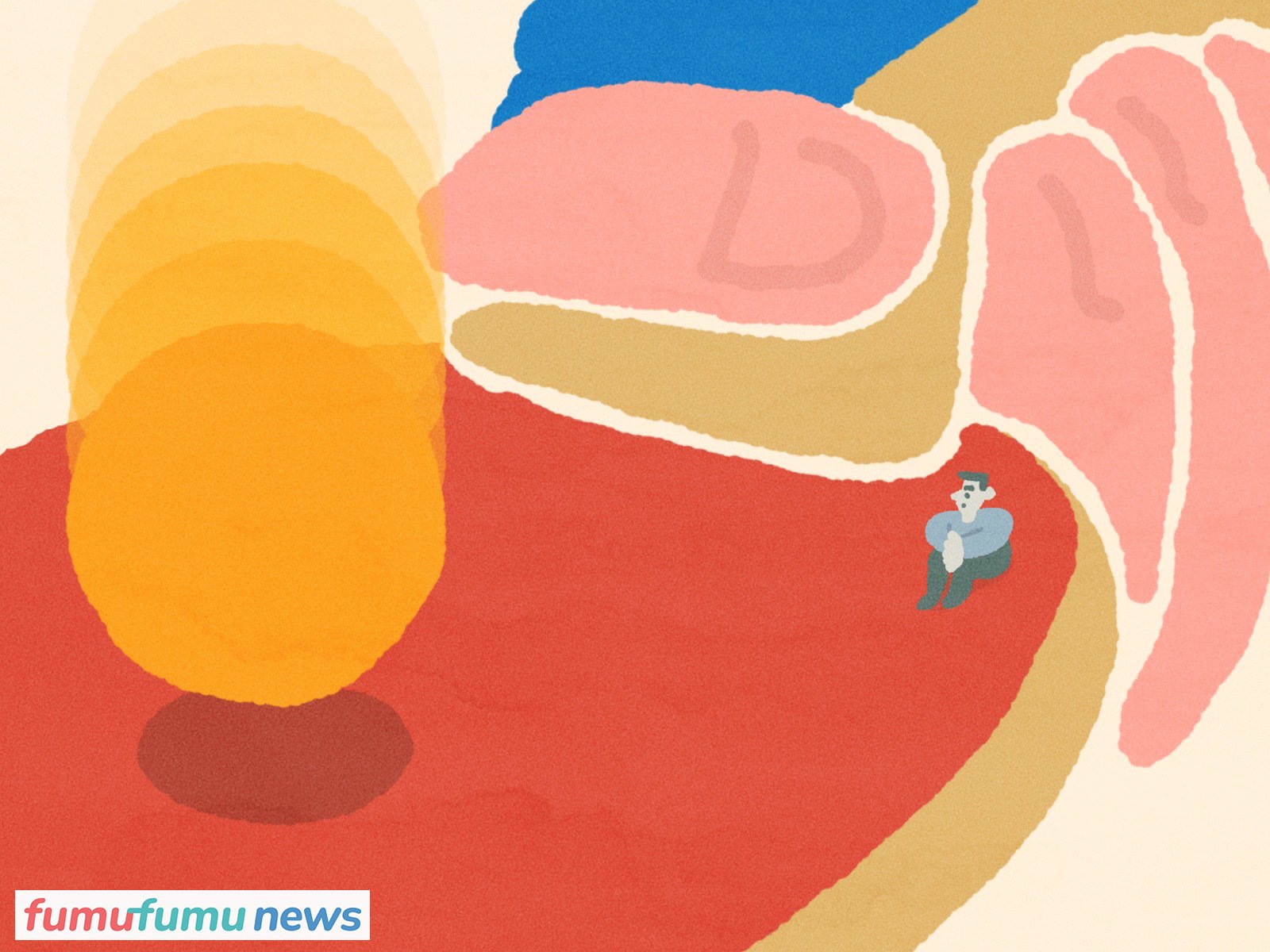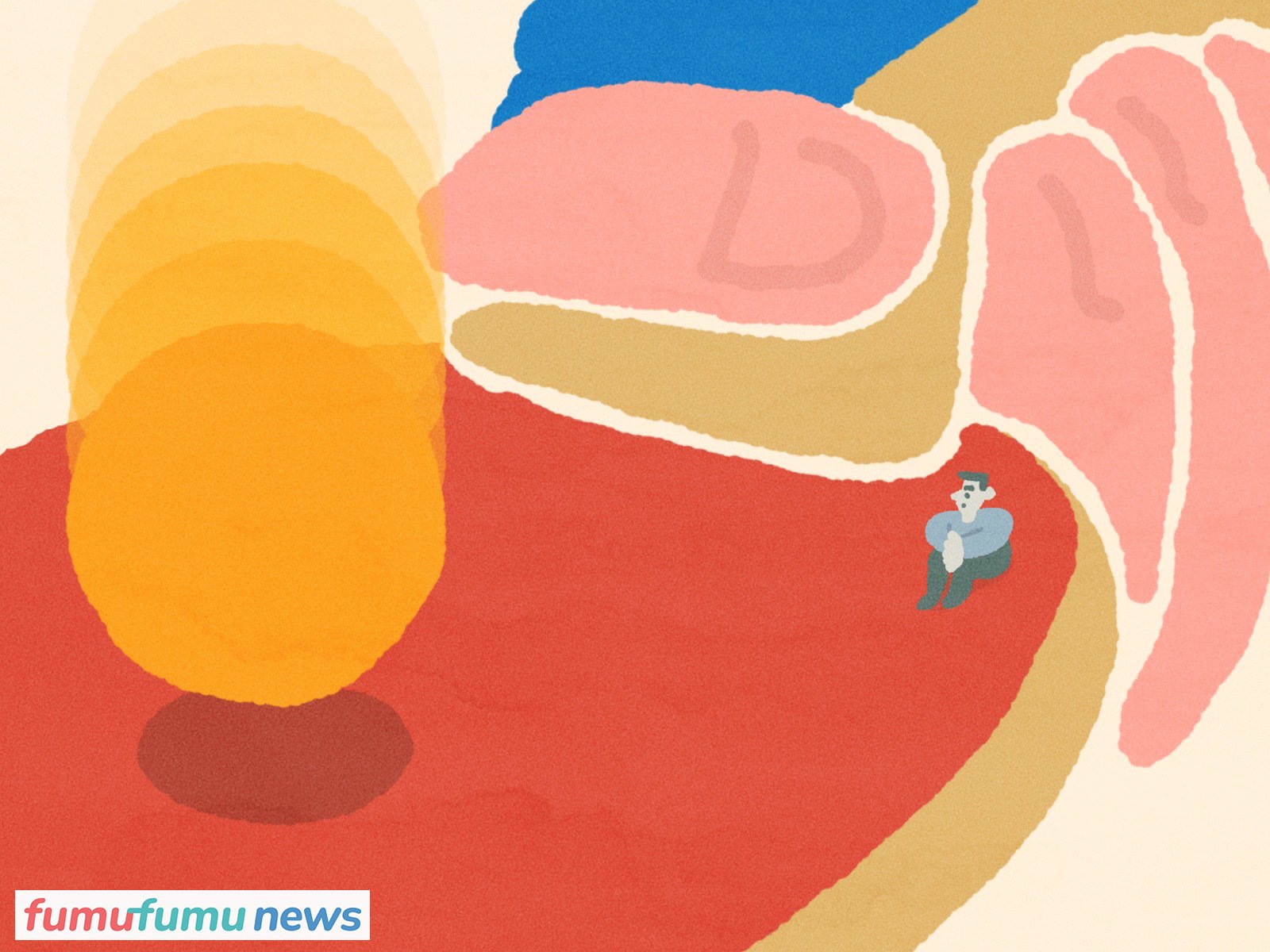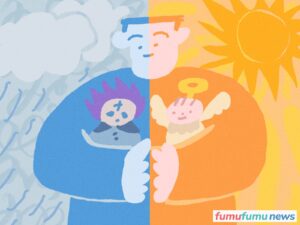人生が一本の映画ならば、とよく思う。もし映画だったならば、あのときのあれは、なんだったのだろうか。今は起承転結の転なのか。それとも、まだ起すら始まっていないのか。想像する。
イメージとしては、脳みそのなかに映画館がある。小さな私がスクリーンの前に着席していて、これまで見てきた思い出や現実の私が今見ている景色が、現在進行形で編集されて上映されているのだ。小さな私はポップコーンを片手に、あーだこーだと感想を言っているわけである。
だとすれば、先ほどの現実のしょうもない私、すなわち、鍋の底にへばりついたうどんを箸でこそぎ取っていた私は、この映画においてどんな意味を持っていたのだろうか。カット、全カットか。それとも、伏線となって後に回収されるのか。
「うどんの精です。あのとき、こそぎ取ってくださりありがとうございました」
こうなるかもしれない。人類と麺類の共生を描いたうどんファンタジーとして、これから私の人生が花開く可能性だってある。だから、私は一生懸命、鍋の底にへばりついたうどんをこそぎ取るし、しょうもない記憶も大切にしている。例えば、おじいちゃんが右利きなのに、サウスポーだったこととか。
人生という壮大な時間の流れにおいて、全くもって意味がないと思われる小さな出来事は、常々起こる。そして、そうした出来事を小瓶に入れるなどして大切にとっておきな、と言ってくれたのが、私にとっての星野源であった。星野源は、小さな出来事を「くだらない」と名づけながら、その矮小(わいしょう)さをそのままに、だからこそ尊いものとして歌い続けてきたように思う。
《首筋の匂いがパンのよう すごいなあって讃えあったり
くだらないの中に愛が 人は笑うように生きる》
──『くだらないの中に』より
《明日なんて 誰も知らない
けど取り敢えず
今日まで続いてよかった
そしたら 作ろう今夜
珍しいって笑う
君が好きかわからぬ
このトマトパスタを》
──『そしたら』より
星野源の歌っているものを、なんと言い表すことができるだろう。うまく言葉にすることができなかった。とにかく私は、そうした大して美しくもない記憶だったり、しょうもないがやけに脳裏にこびりつく出来事に出合うたびに、「星野源だ」と思うようにしていた。
驚いたのは、『Pop Virus』を初めて聴いたときのことである。
《刻む 一拍の永遠を》
──『Pop Virus』より
この詞を見て、「星野源だ」と思った。星野源の曲なので、星野源なのは当たり前なのだが、私が思う星野源の音楽のすべてを、星野源自らがたった一言で、言い表してくれていたのだ。「一拍の永遠」。この一言、この5文字に尽きる。星野源である。
よくある言い方として、「一瞬が永遠になる」という表現がある。甲子園の優勝を決める最後の一投など、一瞬の出来事だったけど一生の思い出になるような瞬間を語る際に、よく使われるフレーズである。
星野源が歌っている一瞬の永遠性は、こうした記憶の濃度の話におさまるものではない。思うに、星野源の音楽は人生をもはるかに超えた時空のはざまに自らを置き、「今」を歌っているのだ。
僧侶の私の目からその姿に眼差しを向けたとき、浮かぶ言葉はブッダだった。それ以外の言葉は見つからない。星野源はまさしく野生のブッダなのであった。
★この連載では第1回では『ばらばら』、第2回は『Crazy Crazy』、第3回は『Same Thing (feat. Superorganism)』を取り上げ、星野源を「野生のブッダ」として読み解いています。詳しくはそれぞれの連載記事をご覧ください。
星野源がとらえている「今」
星野源以外にも「今」を歌うアーティストはたくさんいる。しかし、星野源が少し異なっているのは、「二度と来ない今を謳歌(おうか)しよう」だとか「今を楽しめ」だとか、青春や衝動にこじつけて、今を単純に美化していないところにあると思う。
《時よ 今を乗せて
続くよ 訳もなく》
《時よ 僕ら乗せて
続いてく 意味もなく》
──『時よ』より
《ただ ただ 過ぎるさ僕等
未知を行く》
──『Continues』より
星野源が歌う時間は、ただ過ぎていくだけのものだ。前向きでも後ろ向きでもない、ただ流れていくだけの存在。刻々と過ぎていく時間に意味が与えられることもなければ、生きている私たちの今を手放しで賞賛したりはしない。根幹にあるのは、人間の意思や欲望ではどうにもならない世界観である。
こうした無常観をベースにしながら、星野源の楽曲では同時に、「つづく」ことの尊さが歌われているように思える。
《ふざけた生活はつづくさ》
──『喜劇』より
《「さようなら」も「また逢えた」も
出会った意味すらも
空に消える 夜に光る
もやした日々 河になるよ》
──『ある車掌』より
一つひとつは無意味だが、降り積もっていく。そこに意思があるわけでもないが、なぜだかつづいている。星野源が歌のなかで眼差しを向けているのは、一秒一秒の時間の粒そのものの美しさではなく、どんな一秒であっても次の一秒が来れば二秒となること、すなわち、時間のつながりの尊さにあると私は思う。
《無駄なことだと思いながらも それでもやるのよ
意味がないさと言われながらも それでも歌うの》
《日々は動き 今が生まれる》
──『日常』より
《輝き 無駄の中に
過ぎた時間に ともってる灯》
──『ひらめき』より
生きていると、笑ってしまうくらいにくだらない出来事が起きる。どうしようもないことも起こる。それでも、平等に時は降り積もる。くだらない今も、次第に過去となって古びていくが、その存在は確かに残っている。迎えるこの瞬間の今も、あの日のくだらない過去の上にある。たとえもう記憶になかったとしても、あの日がなければ、今もないのだ。
こうした連綿とつづく時の流れから、ふと何気ない瞬間を切り取ったとき、決して美しくもなかったその光景が、一つとして無駄ではなかったことに気づく。星野源の歌う「くだらなさ」とは、今この瞬間を切り取って現れた無意味が、長い目でとらえたとき、逆説的に今を支えるうえでなくてはならない不可欠な存在として映ることの発露なのではないかと、私は思う。
《剥げた色のふちを 今日も口に運ぼう
ほら 長い長い日々を 今日も繋ごう
少し割れた底に こびりついた過去まで
かき込むの よく噛んでね 同じ茶碗で》
──『茶碗』より
《飯を作ろう ひとり作ろう
風呂を磨いて ただ浸かろう
窓の隙間の 雲と光混ぜた後
昼食を済まそう》
──『うちで踊ろう(大晦日)』より
ここまでして星野源が「生活」を歌う理由も、なんとなく近づいて見えてくる。星野源にとって生活とは、「一日」よりも長く、そして「人生」よりかは時の粒を感じ取ることのできる、そんな時の連綿の象徴だからなのではないだろうか。
とにかく私は星野源を聴くたびに、いつもは思い出すこともない、くだらない記憶を思い出すのだ。
星野源は時空のはざまに歌を置く
このように、星野源は大きな時間の流れとともに今を歌っているように思うが、刮目(かつもく)するべきは、星野源が見ている時間はたった一人分の一生ではないところだ。その視線は遠く果てしない。
《生まれる前の 思い出が
この心を いつも蹴り上げてるんだ》
──『Continues』より
《言葉に ならない Soul
名もなき 記憶に 見える 見える
道外れ 逸れた者
身体に 刻んだ 時を 越えて》
──『Soul』より
《何処の誰か知らないが
出会う前の君に捧ぐ》
《僕たちは骸を越えてきた
少しでも先へ
時空をすべて繋いだ》
──『Helllo Song』より
私たちが経験できる時間よりはるかに遠くの時間を、星野源が見つめているのがわかる。自分が生まれる前の世界、もうすでに記憶にすらない存在、自分も知らない未来の誰かへ、星野源は眼差しを向けているのだ。さらに、《生まれ変わりがあるのなら 人は歌なんて歌わないさ》(『生まれ変わり』より)と歌っていることから、星野源は時空を超えるものとして歌をとらえているのだ。すごすぎる。
以上、私が思うことをまとめるならば、星野源のとらえている時間の感覚とは、過去や未来といった悠久の時のなかに自らと音楽を置き、ちっぽけでくだらない瞬間であってもその瞬間が今へ、そしてこれからの過去や未来となることを受け止め、今を今のままに掬(すく)い取る姿勢だと言うことができるだろうか。
それを一言で表すならば、そう、「一拍の永遠」もしくは「一粒の永遠」なのである。
まるで矛盾したような言葉の組み合わせではあるが、無限の時空の連なりと目の前のトマトパスタを同時に見ることができる星野源からすれば、一拍も永遠も変わりのないものと映るのかもしれない。星野源にとってすれば、その一拍と永遠は切り離せないものであって、たとえ一拍を切り取っても、それは永遠のなかの一拍でしかないのだ。海を掌で掬ったとしてそれは海であるように。
《夏の中に手を伸ばして
海を掬うと
山の静寂 雨を落とせ
掌から》
──『海を掬う』
この『Pop Virus』の世界観に、数少ない私のボキャブラリーから見つかるのは「一即多 多即一」という仏教の言葉である。これは「一瞬即永遠 永遠即一瞬」という言葉で語られることもある。「一瞬は永遠であり、永遠は一瞬」ということだ。
「全は一、一は全」と言い換えることもできる。仏教がとらえる世界像は、一部と全部が単なる大きい小さいの包含関係にあるのではなく、同時に存在しているのだ。一がなければ全もなく、全がなければ一もない。だからこそ、仏教の耳からしても、一拍もまた永遠として聞こえるのである。
この連載では、これまで好き勝手に星野源を野生のブッダとして評してきたのだけど、だんだんとそう言いたくなる私の気持ちが伝わってきただろうか。いや、そんなことは伝わらなくてもいいのだ、結局。私が言いたいことは、「星野源すげぇ」の一言に尽きるのだから。
今日もまた、野生のブッダとの源(禅)問答をつづける。ランダム再生で流れてきた『Pop Virus』は沁みる。
(文/稲田ズイキ)
《PROFILE》
稲田ズイキ(いなだ・ずいき)
1992年、京都府久御山町生まれ。月仲山称名寺の副住職。同志社大学法学部を卒業、同大学院法学研究科を中退のち、広告代理店に入社するも1年で退職し、文筆家・編集者として独立する。アーティストたかくらかずきとの共同プロジェクト「浄土開発機構」など、煩悩をテーマに多様な企画を立ち上げる。2020年フリーペーパー『フリースタイルな僧侶たち』の3代目編集長に就任。著書『世界が仏教であふれだす』(集英社、2020年)