沖縄本島のいちばん南に位置する糸満(いとまん)市は、海人(ウミンチュ=漁師)の町として知られ、農業も盛んで自然豊かな地域。また、沖縄戦の終戦地で、平和祈念公園やひめゆりの塔をはじめ、戦没者の鎮魂と恒久平和を祈る施設も多くあります。
そんな糸満市でハルサー(畑を耕す人)になり、インゲンやトマトなどを栽培している中川陽介さんは東京出身。2009年に東京から住まいを移し、戦争の悲惨さと平和の尊さを継承する「糸満市平和ガイド」としても活動しています。
そして’20年から、糸満を舞台にした映画も制作。実は中川さん、数々の作品を世に送り出してきた映画監督なのです。世界各地の映画祭に出席し、誰もが知る有名俳優を主演に迎えて撮影するなど、華やかな実績を残してきました。その中川さんが、なぜ糸満市で農業を!? インタビューを通して、半生に触れてみます。
“アジア色”を感じる那覇の街に魅了されて……
東京で生まれ育った中川さんは映画が好きで、大学生のころ「映画にかかわる仕事がしたい」という思いが生まれたと言います。当時の映画会社は新卒者の就職チャンスがなかったため、1984年、出版社に入社。その出版社のグループ企業が映画事業に参入していたため、映画に近づけるのでは、とイメージしたそう。
出版社の社員として若者向けの雑誌作りを担当する中、ついにチャンス到来。社内で行われた映画の脚本コンテストで見事、入賞します。
「初めて書いた脚本でした。いい作品だとほめられましたが、審査員に“映画化するには5億円かかる”と言われ実現しませんでした。終戦直後のプロ野球を題材にした話で、取材から着想した物語だったんですよ」
笑顔で振り返る中川さんから、映画の世界が近づいてきた喜びが伝わってきました。
出版社で10年働いたところでグループ企業の業績は不振になり、一方で、映画にかかわりたいという情熱は増すばかり。中川さんは早期退職を決め、自ら会社を立ち上げました。
「映画にかかわる仕事なら何でもやりました。岩井俊二監督の『スワロウテイル』や吉田健監督の『喜多郎の十五少女漂流記』などの現場を手伝いながら、映画の脚本を書き始めました。沖縄で自主制作映画を撮ろうと思ったのはそのころです。
那覇の街の風景にアジアの文化を感じ、それが魅力的に映ったんですよね。ネクタイを締めているサラリーマンが屋台で麺を食うような、バンコクや上海などで見かけるアジアンチックな日常が、那覇にはあったんです。仕事場のそばで飯を食い、住まいも近い。歩くだけで人の営みが匂ってくるような風景が好きになりました。10代から沖縄に来ていましたが、リゾートの旅から、だんだん感覚が変わっていったんです」
映画に当てはめると、「’80年代後半から’90年代にかけて発表された中国のチャン・イーモウ監督やチェン・カイコー監督、そして香港のウォン・カーウァイ監督らの作品に影響を受けた」と言います。世界中で注目を浴びた彼らの作品はアジア色が濃く、街の風景や人の営みを映し出していたのです。
’61年生まれで、自らを“アメリカン・ニューシネマ世代”と言い、ダスティン・ホフマンやアル・パチーノらの主演作に夢中になったという中川さん。娯楽色が強い作風になっていく風潮に「アメリカ映画らしさが失われてしまった」と感じたそうで、そのころから中華系をはじめ、アジア映画に惹(ひ)かれていったのですね。
日台の大スターが共演した『真昼ノ星空』は「100%のできばえ」
映画制作への情熱が高まり、パワーあふれる人間力と才能でチャンスをつかんだ中川さんは、’98年『青い魚』でついに監督デビュー。脚本も手がけた本作は那覇を舞台に少女の儚(はかな)い恋を描き、叙情的で美しい映像が注目され、釜山国際映画祭・モントリオール世界映画祭ほか多くの国際的な映画祭で上映されました。ベルリン国際映画祭では、ヤングフィルムフォーラム正式招待作品に選出されています。
続く『departure』(’00年)、『FIRE!』(’02年)も沖縄が舞台。「街中でも人々の生活が息づいている」というアジア感を沖縄に見たという中川さんは、東京にいながら沖縄の人や街を描く映画を撮り続けたのです。
’04年には名実ともに日本を代表する女優・鈴木京香さん、中華ポップスの貴公子・王力宏(ワン・リーホン)さんを主演に迎えた『真昼ノ星空』を発表。日台トップスターの共演、ベルリン国際映画祭での上映時は会場が満員で人があふれたなど、さまざまな話題を呼んで注目されました。ウチナーンチュ(沖縄出身者)の私としては鑑賞当時、かの京香さんとリーホンさんが市場など庶民的な沖縄の街中でロケをしたことに驚き、せつない愛の物語に大感動したことを覚えています。
「高い評価をいただいた『真昼ノ星空』は、自分自身でも100%のできばえだったと思っています。京香さんにたまたま会う機会があり、“私に合う映画はないの?”と聞かれたので脚本を見ていただいたら気に入って、出演してくれました。撮影の合間にひとりで100円ショップに行って、クリスマスのかぶり物を買って楽しそうに遊んでいましたよ。天然でかわいらしい素顔ですが、本番になるとグッと表情が変わるのはさすがでした。本当にいい女優でいい女、この映画の京香さんの美しさは、多くの観客を引きつけました。でも那覇の農連市場に、あんないい女はいませんよね(笑)」

数年越しの大作を発表後「やり尽くしたので次はない」
『群青 愛が沈んだ海の色』を発表したのは’09年。主演の長澤まさみさんが20代に突入し、女優として成長したと注目された作品です。大手映画会社が製作・配給し、中川さんにとっては企画から脚本執筆まで数年間かけた大作。「作家性と商業的なことで揺れ動きました」と振り返り、最終的には商業的にやろうと腹をくくったのだそうです。
「渡名喜島で1か月、撮影しました。すてきな島で楽しい滞在になりました。ドラマ収録があった佐々木蔵之介くんは、いったん東京に帰ったんですが、電話があり、“渡名喜が恋しいです!”と言われましたよ。懐かしいですね」
そして、本作の完成後に燃え尽き症候群のような感覚になったという中川さん。作家性にこだわりたい気持ち、制作過程での苦労など、さまざまな出来事や葛藤があっただろうと想像します。
「この作品でやり尽くしたので次はない、沖縄で映画を撮ることも、もうないだろうと思えました。それは僕にとって、映画をやめる決断でした」
50歳間近だった中川さんは、新たにどんな仕事ができるだろうと考え「農業が楽しそう」と興味を持ったとのこと。
「千葉や埼玉で土地を探しましたが、農地といわれるところは、すごい田舎。繁華街に出るまでに車で数時間かかる環境だったんです。ところが糸満だったら、車を15分程度走らせれば那覇に行ける。花粉症持ちの妻の悩みもなくなるし、沖縄はいいと思いました」
憧れの映画業界で活躍して評価され、確実に実績を積んできた中川さん。40代まで突っ走ってきましたが、離れることを決意。映画を撮り続けた沖縄で農業に携わるのが、自然な流れだったようです。
アラフィフで沖縄へ移住、農業を生業に小説も執筆
「沖縄で農業を始めようと伝えると、妻は“賛成”と二つ返事。人生最大の賛成を示してくれました。高校生だった下の息子と妻が沖縄に来たのは僕の移住から1年後で、最初の1年間は単身で(本島北部の)名護市に住み、農大で学んだんです」
’09年に暮らしと仕事という、第2の人生における2つの柱をガラリと変えた中川さん。沖縄県立農業大学校・短期養成科へ入学し、野菜作りや農業経営を基礎から学びました。「しっかり計画し、道筋どおりに進んできたんですね」と伝えると、「整理しながら話しているからそう聞こえるだけ。実際はいろんなことにぶつかってきました」とひと言。この答えから、苦労を乗り越えてきたことがわかります。
1年後に農大を卒業し、農地として魅力を感じた糸満市で新しい生活をスタートさせました。
「インゲン・トマト・ニンジンをハウスで栽培しています。今はインゲンが育っていて、12月に収穫。早朝にハウスに行き、暑くなる11時ごろには家に帰ってシャワーを浴び、15時過ぎにもう1回行って暗くなるまで作業、という毎日です」


このようなスケジュールで農業に勤(いそ)しむ中川さんにとって、7〜8月の台風シーズンの作業はお休み。小説を書く執筆活動の時間にあててきたとのこと。
「映像を前提にした脚本を書くことはありましたが、小説を書くようになったのは沖縄で農業を始めてから。趣味のようなものですが、賞が取れたらいいなという気持ちはありました」
作品を書きあげると、’14年からは「おきなわ文学賞」に応募し、佳作や二等賞に選出されました。そして’18年にはオリジナル作品『唐船ドーイ』で「第44回 新沖縄文学賞」、’21年には『笑顔の理由』がJAグループ主催による「第69回地上文学賞」を受賞。新作を発表するごとに高い評価を得ています。
「50歳を過ぎているし映画監督をやっていた人間だから、賞を取って当たり前と思われるかもしれないね」
そう笑顔で語る中川さんですが、映画制作で培ってきた経験と豊かな才能で、沖縄在住の小説家として実績を積んできました。発表作品中2作、『唐船ドーイ』と『一九の春』は書籍化もされています(ともに沖縄タイムス社刊)。どちらもタイトルが沖縄民謡風なので、テンポよく展開する娯楽作品では!? と勝手にイメージ。読んで確認したいと思っています。
沖縄で再発起! 平和を願い、糸満市を舞台にした短編映画に挑戦
東京にいたころは映画、沖縄に住むようになってからは小説を手がけてきた中川さんですが、共通するのは沖縄を舞台にしていること。前作から10年近くたったころ、沖縄にいながら、ついに映画制作に再挑戦します。地元の糸満市をロケ地に短編映画を数本撮ったのです。
「農業を始めたころは余裕のない日々でしたが、年月が過ぎ、少しずつ余裕ができてきました。’20年にはコロナ対策で文化芸術を支援するためのプログラムがあり、応募したら選ばれて、その補助金でも制作しました」
沖縄でも映画制作をしようと思った背景には、「農家の師匠と慕う人物から印象的な言葉をもらったこと」も影響しているようです。
「師匠は、農業を目的にするなと言うんです。目的にしてしまうと、人生のすべてが農業になってしまう。そうではなく、農業はお金を稼ぐための手段。趣味を持たないと人生は楽しくないよと言われました」
そんな言葉に、最初は反発したという中川さん。
「東京での生活を捨て、かなりの金額をつぎ込んで農業のためにハウスを建てました。その行動や思いを根底から揺るがされ、ショックでした。でも、だんだんわかってきたんですよ。馬車馬のように働いて、生活できるようになったとします。その先にやることがないと、いったいどうなるのか、と先を考えられるようになりました。だんだんと師匠の言葉が心にしみてきて、“自分にはやっぱり映画や小説なのだろう”という気持ちが大きくなっていったんです」
前述の、長澤まさみさんが主演した映画『群青 愛が沈んだ海の色』の監督は楽しい経験だったけれど、大作すぎて目の届かない部分ができてしまう。昔はスタッフ数百人体制で映画を撮ったこともあったけれど、機材が発達した現在は5人でもできるなど、過去と現在を比べながら、映画作りをリアルに考えられるようになった中川さん。
「全国公開はできなくても、自分でコントロールできる小規模な映画を沖縄の役者と作りたい。短期間・低予算で取り組みつつ、映画の本質が少しだけでもわかる作品づくりを、と前向きになりました。自主制作に戻る感覚でしたね」
映画制作への意欲を取り戻した中川さんは、’20〜’21年に『のぶゆきと母ちゃん』『笑顔の理由』『やくそく』を続けて完成させました。監督と脚本を兼任したこの作品たちは短編三部作といえる内容。
「沖縄の文化や人の考え方を自分なりに解釈し、沖縄を撮ろうと思いました。東京にいたころはロケ地として沖縄で撮る、という感覚だったんですよね。
また、お盆をはじめとする年間行事や日常を通して、沖縄は“生きている人と亡くなった人の距離が近い”ことに驚きました。だから、亡くなった人への思い、亡くなった人からの思いを3作品で描きました」
このように、以前とは撮る映画の作風が変わったと、自ら認識する中川さん。
「東京で作ったデビュー作『青い魚』と最新作『やくそく』はまったく違います。自分だったら農作業を終えて家に帰ると、小難しいアート作品などは見たくないわけですよ。頭を使わず沖縄の人気役者が放つセリフを聞くのが楽しいし、おじぃとあばぁが出てきたりするのが面白い。過去作品よりも『やくそく』のほうが、観客向けでわかりやすいです」
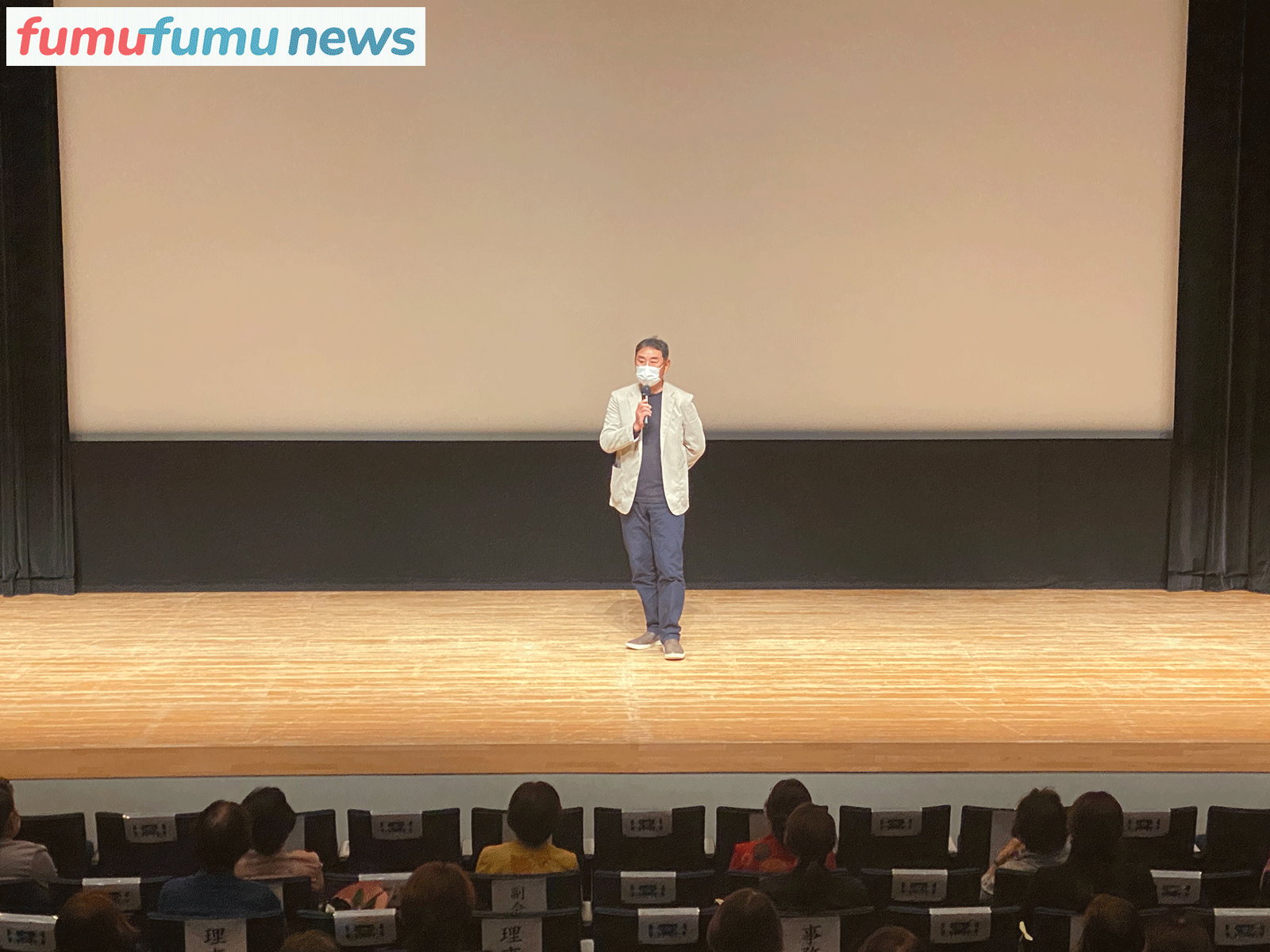
監督としての中川さんの現在のスタンスは、「自分が見たい映画を作っていくこと」。また、3年間かけて学習し活動する「糸満市平和ガイド」としての立場から、戦争映画の必要性にも気づいたと言います。
「戦争を扱うのはとてもデリケートですが、記憶を色あせさせないためにも戦争映画は必要だと考えています。戦争を美化している、アメリカ人をヒーローにしているなど批判を浴びた作品がありますが、沖縄戦を知る機会になった人もいたでしょうね。鑑賞後に戦争がいいと思う観客もいないと思います」
平和ガイドの活動を通して、沖縄戦を知らない若者たちに触れる機会も多い中川さん。
「悲惨な面をストレートに伝えると怯(おび)えにつながるので、初恋のエピソードを入れつつ戦争の悲しさを静かに語ったのが『やくそく』です。批判は覚悟のうえで、多くの人に見ていただけたら、という思いで作りあげました」

ついに長編制作! 「銀天街」の街おこしムービーに意欲
そして’22年11月末、長編作品のメガホンを握ることが決定。沖縄市(旧コザ市)に実在する「銀天街」の活性化への取り組みとなる映画制作です。ショッピングセンターに客足を奪われ、商店主の高齢化問題もある中でシャッター街となったこの商店街を舞台に撮影を行い、完成後は上映イベントを開催予定。また、出演者やスタッフを住民から募るなど「ワッター(私たちの)町の映画」という意識を高める作品づくりにしていくそうです。
映画のタイトルは『コザママ♪〜うたって!コザのママさん!!〜』。ジョニー宜野湾さん・jimamaさんらミュージシャンをはじめ、舞台役者や芸人など幅広いジャンルにおける沖縄の人気者たちが出演します。
「20年前のコザで人気だったガールズバンドのメンバー4人が、街おこしイベントで再結成する話です。主役は70年の歴史を持つ銀天街の街並みで、はたしてもう一度息を吹き込めるのか、という実験的な映画。そこに住む子どもたちに、自分の街は最高だとプライドを持ってもらうことも目的にしています」
11月末から12月にかけて撮影し、’23年1月の毎週土曜日に、銀天街特設会場にてプレミア上映を計画中。スクリーンに映し出される場所で映画を見るワクワク感、見終わったあとは現地を散策する楽しみがあり、県内外から注目される上映スタイルになりそうです。
「夢を取り戻そうとするママさんたちの姿を描き、かつて黒人街といわれたこの商店街で日常に流れていたR&Bミュージックを取り入れます。音楽と映画がどれだけ街や人を豊かにするのか、というのがポイント。昭和の建物が残っているノスタルジーな銀天街は、ロケ地としても魅力です」
そう言って目を輝かせる中川さんは、13年ぶりに取り組む長編制作に「やっと戻ってきた」と実感するのではないでしょうか。以前と変わらず、楽しく和気あいあいとした現場づくりをモットーにするそうです。
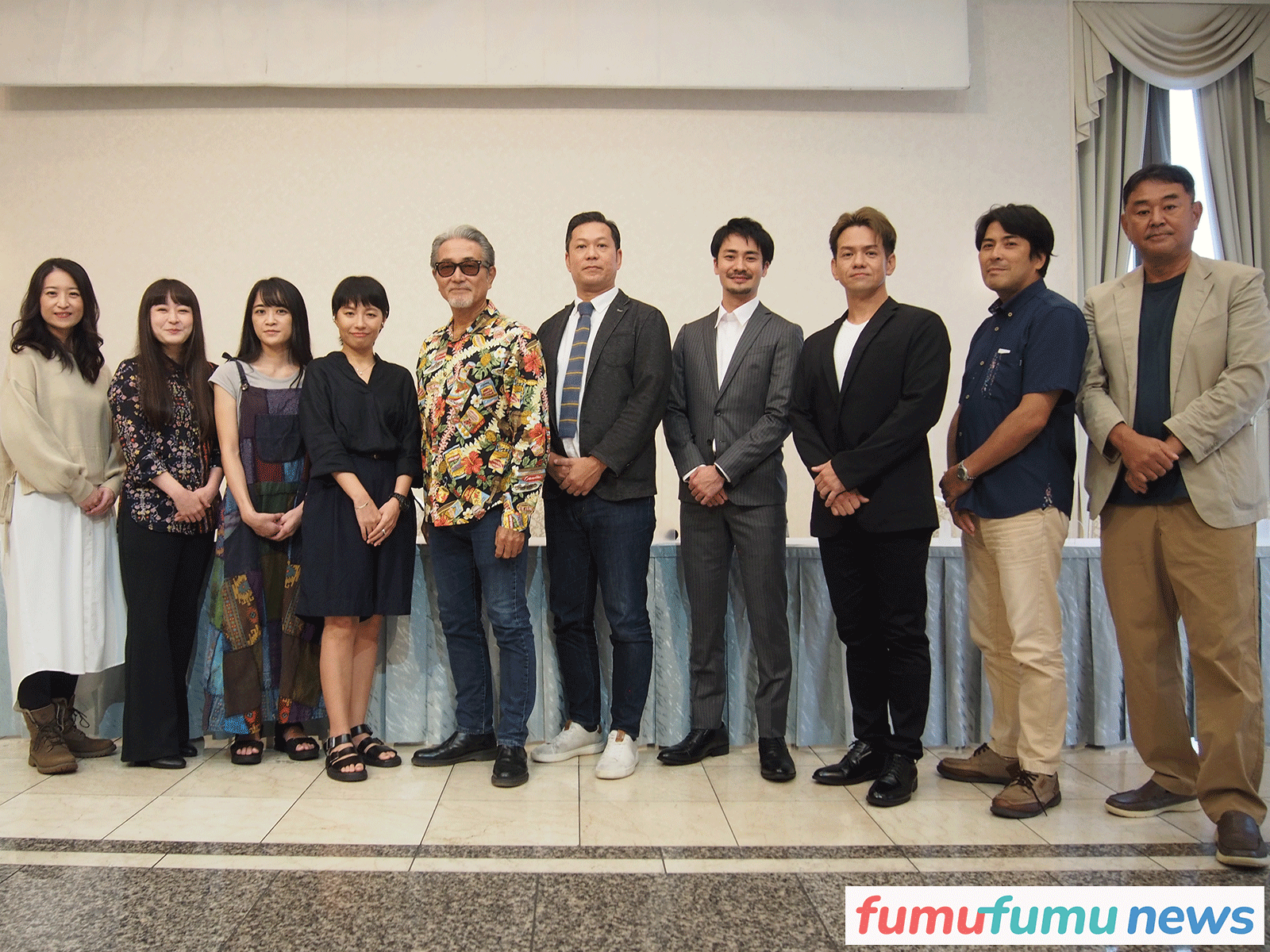
映画で始まり、農業も始め、現在は兼業している中川さんの半生。影響を受けた人物を聞くと、お父さまだという答えが返ってきました。
「祖父が99歳まで生きたので親父も長生きすると思っていたら、68歳で他界しました。親父は新聞記者で、定年後も舞台などの評論を書いていました。亡くなる前は無念そうな顔をしていて、もっと発表したい気持ちが伝わってきましたね。親父を見て、“明日にでも死んでしまうかもしれない、いちばん若い今、やりたいことをやろう”と思うようになりました。もし失敗することがあっても、命までは取られないだろうという開き直りもあるんです」
その言葉から、中川さんの真っすぐな気持ちが伝わってきます。お正月には『コザママ♪』を鑑賞し、ときどき中川農園の野菜を味わって、中川陽介さんのこれからを追いかけたいと思いました。
(取材・文/饒波貴子、執筆協力/Shotaro)
【PROFILE】
中川陽介(なかがわ・ようすけ) ◎映画監督。SOUTHEND PICTURES主宰。1961年東京都生まれ。沖縄を舞台にした数々の作品を世に送り出し、世界各地の映画祭に招待、上映される。’09年に糸満市に移住し農業を開始。小説家としても活躍しており、沖縄を舞台とする作品群で「おきなわ文学賞 理事長賞」や「第44回新沖縄文学賞」、「第69回地上文学賞」を受賞。代表作に『青い魚』『真昼ノ星空』『群青 愛が沈んだ海の色』『やくそく』などがある。








