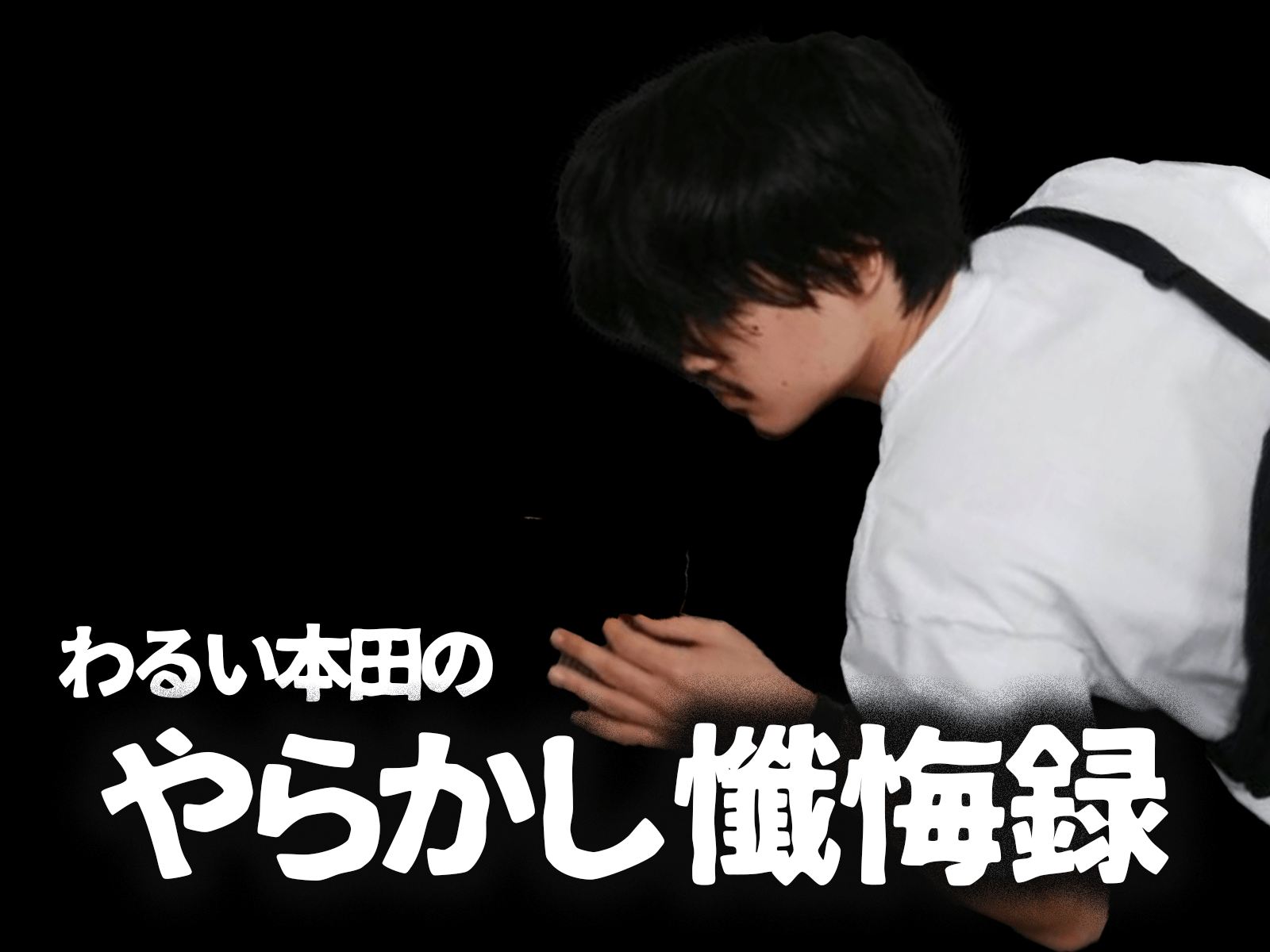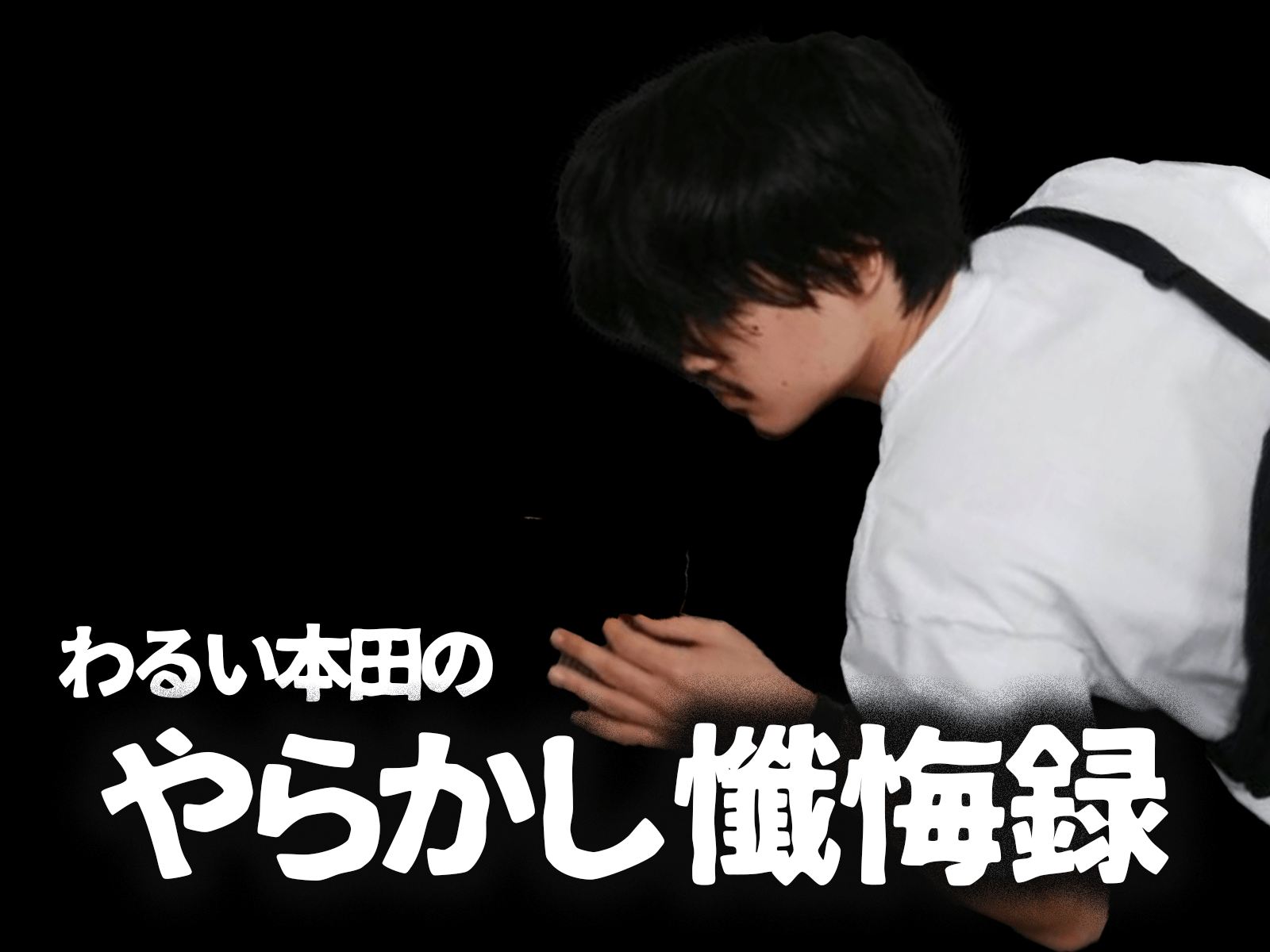「説教を受ける人間の正しい姿勢」とは何だろうか。「正座」あるいは「直立姿勢」という声が多いだろう。僕はかつて「説教を受ける姿勢」で大失敗してしまったことがある。今回はその時のことについて謝罪したい。
大学生の頃の僕の家には「24時間誰でも来ていい家」という狂ったルールがあった。そこは友人(時には全く知らない奴)が三、四人ほど常駐し、真夜中でも次々に人が訪ねてくる無法地帯で、僕はプライバシーやプライベートとは全く疎遠の日々を送っていた。
そんな家では無論、自堕落で退廃的な遊びが流行していた。麻雀やポーカー、オンライン競馬、徹夜で無限桃鉄など、生産性のない行動に時間を消費しては全員留年を繰り返すという地獄のようなルーティーンの日々。この部屋に住み着く住人が一つも単位を取れないことから、「ゼログラビティ」と呼ばれていた。
ある日、そんなゼログラビティの住人の誰かが声を上げた。
「インディアンポーカーをやってみないか」
インディアンポーカー。それはトランプの表を見ずに1枚だけ額に貼り、数字の大小で勝負をするというゲームだ。本人は自分が持っている数字の大きさを知らないので、周りの反応だけを見て勝負をするか降りるかを決めるという駆け引きがあった。
真実は知らないが、僕達の中でインディアンポーカーは、山手線ゲーム、ジェンガ、王様ゲームと並ぶ「リア充御用達のゲーム」という位置付けであり、年中部屋で退廃的に腐っている「隠の者」たる僕達がそのようなパーティゲームに興じるというのは一周回ってシニカルで痛快なことのように思えた。二つ返事で全員が快諾し、インディアンポーカーが始まった。
案の定ゲームは盛り上がり、僕達は擬似リア充になったパラレルワールドを皮肉っぽく愉しんでいた。この遊びに何の意味があるのかと思われるかもしれないが、優秀な同級生達がいい企業に就職したり、起業で大成功したりというあからさまな人生の勝ち組ルートに乗っていくのを横目で見ていた僕達にとって、耽溺と逃避こそが彼らに対する唯一の反抗であった。
そんな僕達の虚しい笑い声は、深夜にも関わらずそれなりの音量になってしまっていた。
「静かに。鬼奴(おにやっこ)が来るぞ」
誰かがいつも通りの警鐘を鳴らした。「鬼奴」とはこの部屋の上に住む推定三十代後半の女性のことで、顔がどことなく椿鬼奴に似ていることからその名が付けられた。加えて彼女は非常に長身で、怒ると鬼のような形相をすることからその名は僕達の中でとてもしっくりきていた。
なぜ彼女の怒った顔を知っているかというと、我々は幾度となく彼女から怒られていたからである。
二十代の若者が夜な夜な狂乱しているこの家からは、当たり前のようにストレスフルな騒音が常時漏れ出しており、それに業を煮やした鬼奴が度々ブチギレ訪問をかましていた。過去には、激怒した鬼奴がこの家に入って来て、玄関にあったヤカンを豪速球で投げつけ、寝起きの僕の顔の横を通過したこともあったし、深夜三時に家の前に全員整列させられ、一人ずつ謝罪の言葉を発表させられたこともある。ちなみにその時、今YouTubeを一緒にやっている青柳が発した「楽しくなってしまってすみません」というあまりにも見当違いな謝罪は、僕達の思い出し笑いの種の一つである。
鬼奴に対して苦い思い出がある我々は、表情を一瞬曇らせた。しかし、沸騰しようとする鍋を蓋で抑えれば圧力が増すように、その緊張感は我々にとって逆効果だった。「笑ってはいけない」「大きい声を出してはいけない」そう思えば思うほど、笑いの空気は張り詰めていく。大きい数のトランプを持った奴がフォールドするたび、小さい数の奴が自信満々に突っ張った態度を見せるたびに、膨らんだ風船に針を刺してしまった時のような笑い声が噴出した。朝方四時であった。
ドンドンドン!
玄関が勢いよくノックされた。その音には明らかに怒りと殺意が宿っていた。一小節にも満たないリズムの中にこんなにも暴力性を内在させることができる人物は一人しかいない。そう、鬼奴である。
招かれざる訪問者に、額にトランプを貼った面々は一瞬で真顔になった。我々はいつもこの瞬間に後悔する。「どうしてあんなに騒いでしまったのだろう」と。
僕達は馬鹿なのだろうか。こんな時、いつも一瞬だけ居留守をしてしまう。何故か数十秒間黙りこくり、この家には人っ子ひとりいませんよ的カモフラージュを試みるのである。冷静に考えて、先ほどまであれだけ馬鹿騒ぎの音が漏れ出していた部屋からノックの瞬間にたちまち一人もいなくなるなど、日本最大級の神隠し並みの不自然さであるのに。滑稽でしかない居留守作戦は諦め、恐る恐るドアを開ける。この家の主である僕が鬼奴の沈静化を任された形だ。
だが、この日の鬼奴はいつにも増して暴力的だった。彼女はいきなり僕の胸ぐらを掴み「なんっ、じだと、思ってん…どゴラ!!!!!!!」と怒号を浴びせた。その怒りはフルスピード過ぎて、自らの言葉を置き去りにする程だった。前述の通り彼女は長身なので、胸ぐらを掴まれた僕は少し地面から浮き上がっていた。怒号と共に男を持ち上げ前後に揺さぶる。その様子はシルエットだけ見れば、クリスマスプレゼントにテディベアを貰った女の子がはしゃぐ姿だった。
僕は狂乱への後悔と暴力に晒される羞恥、そして鬼奴への心苦しさに苛まれ、暫く反省の面構えを維持していたが、ふとあることに気がついた。
「(そういえば、額にトランプがくっついたままだ)」
そう、僕の額にはインディアンポーカーの名残りであるトランプのカードが未だくっつけられたままだった。ガムテープでくっつけられたそのカードは、鬼奴の首ガクンガクン攻撃にも負けない程にガチガチに固定されており、僕の頭と同期し揺れている。その強度は正に、僕達のゲームへの公平性や誠実さと比例していた。
だが、僕達のゲームへの真摯な一面など鬼奴に伝わるはずもなく、首を締める力は益々強くなるばかりだ。僕は朦朧とした意識の中で、ある素朴な疑問を抱いた。
「(鬼奴は、いつこのトランプのことを言うんだろう)」
彼女のお説教は延々と続いていた。「お前は何の役にも立たない偽物だ」「この家にいる人間はこの先ろくな人生を送らない」MC鬼奴の2ラウンド目のディスは僕の人間性や人生観のテリトリーにまで踏み込んでいる。だが、肝腎要の、先ず真っ先に目に入るであろうトランプ(数字は不明)には一向に触れてこない。説教を垂れている目の前の男の額にはトランプ(数字は不明)がくっついているのだ。「そのトランプ取れよ」の一言くらいあってもいいはずである。
僕は決意を固めた。こうなったらこちらも、自分からトランプを取り払うなどという野暮な真似はしない。そんな自粛は全くセンスがないではないか。彼女が指摘するまでトランプは取らないでおいてみよう。そう固く決心し、鬼奴と対峙した。
突然、鬼奴の怒りはまたボルテージを増した。「てめぇ人の話聞いてんのか!?」僕の考えが他所に飛んでいったのがバレたのであろう。だが怒りの矛先は相変わらずトランプのことではなかった。拳が頬に向かって飛んできたので避けようとすると、僕の顔を固定するために彼女は僕の前髪を掴んだ。
「(あれ? 今、トランプ避けなかった?)」
明らかにちょっとした忖度があった。僕の額のトランプが剥がれないように、少し迂回して僕の前髪を掴んでくれた気がしたのである。お陰でトランプはまだ額にご存命だ。もしかして鬼奴、インディアンポーカーのルールに気を遣ってくれてる? もしかして鬼奴、ゲーム続けさせようとしてくれた? 彼女も昔、隣人に怒られながらインディアンポーカーに興じた青春があったのだろうか。罪を憎んで人を憎まずではないけれども、騒音にこそ注意をしても、肝心のゲーム性は崩壊させないように慎重に暴力を振るっていたのではないか。そう思うと、彼女への申し訳なさが込み上げてきた。
結局、最後まで彼女がトランプを指摘することはなかった。もう二度と騒音騒ぎは起こさないという念書にサインをする時まで、僕はトランプを額につけたままだった。事を終えて部屋に戻ると、仲間達が全員トランプを外していた。
そんな鬼奴に謝りたい。当時は深夜に騒いでしまって本当に申し訳ありませんでした。
大人になった今なら分かります。次の日仕事がある夜、隣の馬鹿大学生が騒いでいるなんて地獄です。その節は大変ご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。
それと、どうしても気になることがあるのですが、僕のトランプの数字は何だったでしょうか? ジャックより上なことは間違いないのですが。
(文/わるい本田、編集/福アニー)
【Profile】
●わるい本田
1989年生まれ。YouTubeチャンネル「おませちゃんブラザーズ」の出演と編集を担当。早稲田大学を三留し中退、その後ラジオの放送作家になるも放送事故を連発し退社し、今に至る。誰にも怒られない生き方を探して奔走中。