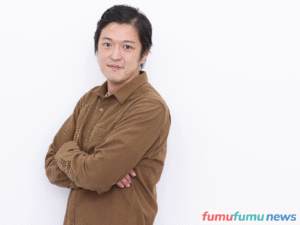悠然とたたずむ姿から“大人の余裕”がただよう、俳優の辰巳琢郎さん(64)。人気ドラマ『浅見光彦シリーズ』(TBS系)への出演のほか、『たけし・逸見の平成教育委員会』(フジテレビ系)、『クイズプレゼンバラエティーQさま!!』(テレビ朝日系)などクイズ番組での回答者としてもおなじみです。
近年はテレビのみならず、舞台への出演やワインのプロデュースなども手がけています。クイズ番組ではたびたび驚異の正答率をたたき出し、“元祖インテリ俳優”ともいえる辰巳琢郎さんに、中高時代や、京都大学へ進学してから本格的に役者の世界へ入っていくまでの道のりを振り返っていただきました。
本に囲まれた生活が基盤に、高校では芝居に没頭するも数学を鍛えて京大に合格
──『たけし・逸見の平成教育委員会』(1991年10月~1997年9月放送)では全問正解も成し遂げていましたが、勉強はもともと得意だったのですか?
「僕の世代は、ちょうど模擬試験が導入され始めたころだったかもしれませんが、小学校時代にそういうのを受けてみたら、よくできたんですよ。幼いころからお受験用の勉強をさせる家庭も増えてきた現代とは違って、周りがまだ勉強していなかったから(笑)。それで、当時は大阪でいちばん難関だと言われていた中高一貫校(大阪教育大学附属天王寺中学校・高等学校)に入りました。ただ、中高時代はずっと芝居をしたり遊んだりしていたので、下から数えるほうが早かったんです(笑)」
──学校はどのような雰囲気でしたか?
「僕が通っていた学校は、自由放任主義を大事にしていました。今ではそういう教育方針は、あまり支持されなくなっているようですね。少人数制の学校で、校則もあまり厳しくなく、勉強以外にも好きなことを自由にやらせてもらっていたのは大きかったと思います。同級生には推理作家の芦辺拓さん、4歳下の卒業生には山中伸弥さん(京都大学iPS細胞研究所名誉所長)や、世耕弘成さん(第22〜23代経済産業大臣)といった、ユニークな人材も多いんですよ」
──小さいころから続けていた、勉強にかかわる習慣などはありますか?
「父親が大の本好きだったので、昔からいろいろな本を買ってきてくれたんです。両親も“読書に勝る教育はない”と思っていたんでしょう。僕は地図と図鑑が好きだったので、気になったことはどんどん自分で調べたし、わからないことがあれば辞書を引くことを習慣にしていました。今の子たちは何でもすぐネットで調べてしまうから、頭に残りにくいのではないでしょうか」
──やはり勉強には、知的探求心が大事なのですね。
「本などを使って調べていると、同じページに載っているほかの事柄にも興味がわいて、それをまた調べて。そうするうちに、いろんな知識が入っていくんです。でも、AIが選んで自動的に表示される、自分に合ったニュースばかりを見ていると、知らないものがなかなか目に飛び込んでこないから、脳が退化してしまいそうですよね」
──記憶力も、周りと比べて抜きんでていたのですか?
「そんなことないですよ。記憶に関しては僕の場合、写真式で覚えていくタイプですね。年号などの数字を含め、字面や形で覚えるんです」
──現役で京都大学の文学部に進学されましたが、京大を選んだ理由って、ありましたか?
「まず、東大には興味がなかったんですよね。関西人あるあるですが、アンチ東京だったから(笑)。“絶対に東京になんか行くもんか”って思っていたものの、今は住んでいますが。京大を選んだのは、父親も京大だったことが影響していたのかもしれません。でも大きな理由としては、“日本一単位が取りやすい大学”と聞いていたからかな(笑)」
──そうなんですか!? 逆に、入るのは難しそうですが……。受験勉強は、いつごろから始めたのですか?
「高3に上がるまでは、そんなに勉強していませんでした。というのも、高2のときに、つかこうへいさんの芝居に魅了されて劇団を作って、それにのめり込んでいたんです。ただ、高3の9月に行われた学園祭までは芝居を続けつつも、高2が終わった春休みから、受験勉強を頑張り出しました」
──それで間に合うのですか!?
「大学受験の勉強は、1年も本気でやればなんとかなりますよ。母校の教育方針も、“高校での3年間は大事な時期だから、受験勉強にうつつを抜かさず学生生活をエンジョイしなさい。そして1年浪人してでも好きな大学に行きなさい”という感じでしたね。文系の入試って、数学で差が出ると思うんですよ。英語や社会では大きな差がつきにくい。そこで、もともとは実力テストで15点ほどだった数学を1年間、徹底的に勉強して、ばーっと点数を上げました。参考書は何冊も手を出すのではなく、薄い本を繰り返し解いて、内容をすべて頭に叩き込みました。現役で合格したことは、先生も友達も驚いていましたけれど」
劇団を主宰し演劇活動に明け暮れる日々、アトリエも構えて演劇ブームを牽引
──京大では、劇団に入団したのですよね。
「高校時代も演劇をやっていましたが、役者をするよりも、物を作ることのほうが好きだったんです。本当は映画がやりたかったけれど、お金もかかりますし。京大に入学したとき、学内に『劇団卒塔婆小町』(現・劇団そとばこまち)というサークルがあったんです。その2期生になりました。意外と体育会系で、日ごろから腹筋をしたり、ランニングしたり。大文字山(京都府の山)にも登りましたね」
──本格的に演劇を志したきっかけはあったのですか?
「大島渚監督(代表作は映画『愛のコリーダ』『戦場のメリークリスマス』など。京大在学中に劇団『創造座』を創設・主宰し、演劇活動も行っていた)が、父と大学の同窓で親しい仲だったこともあり、当時の話は聞いていました。その影響もあったのかもしれませんね。監督が主宰していた『創造座』という劇団の名前を気に入ったので、自分が継がせてもらえないかなと思って、手紙を書いたこともあります。そうしたら、“自分の劇団をやったらいいんじゃないか”っていう返事をいただいて、これまで以上に演劇に本腰を入れ始めました」
──実際に劇団を主宰したのですか?
「実は、われわれの年代と先輩達が、劇団の方針で対立してしまった。それで、先輩達が嫌気がさしてみんな退団してしまったんです。そこから新生『劇団卒塔婆小町』として再スタートし、その1年後から、2代目の座長を務めました。もともと役者をやろうとしていたわけではなかったので、どちらかと言えば、プロデューサーや経営者みたいな立場でしたね」
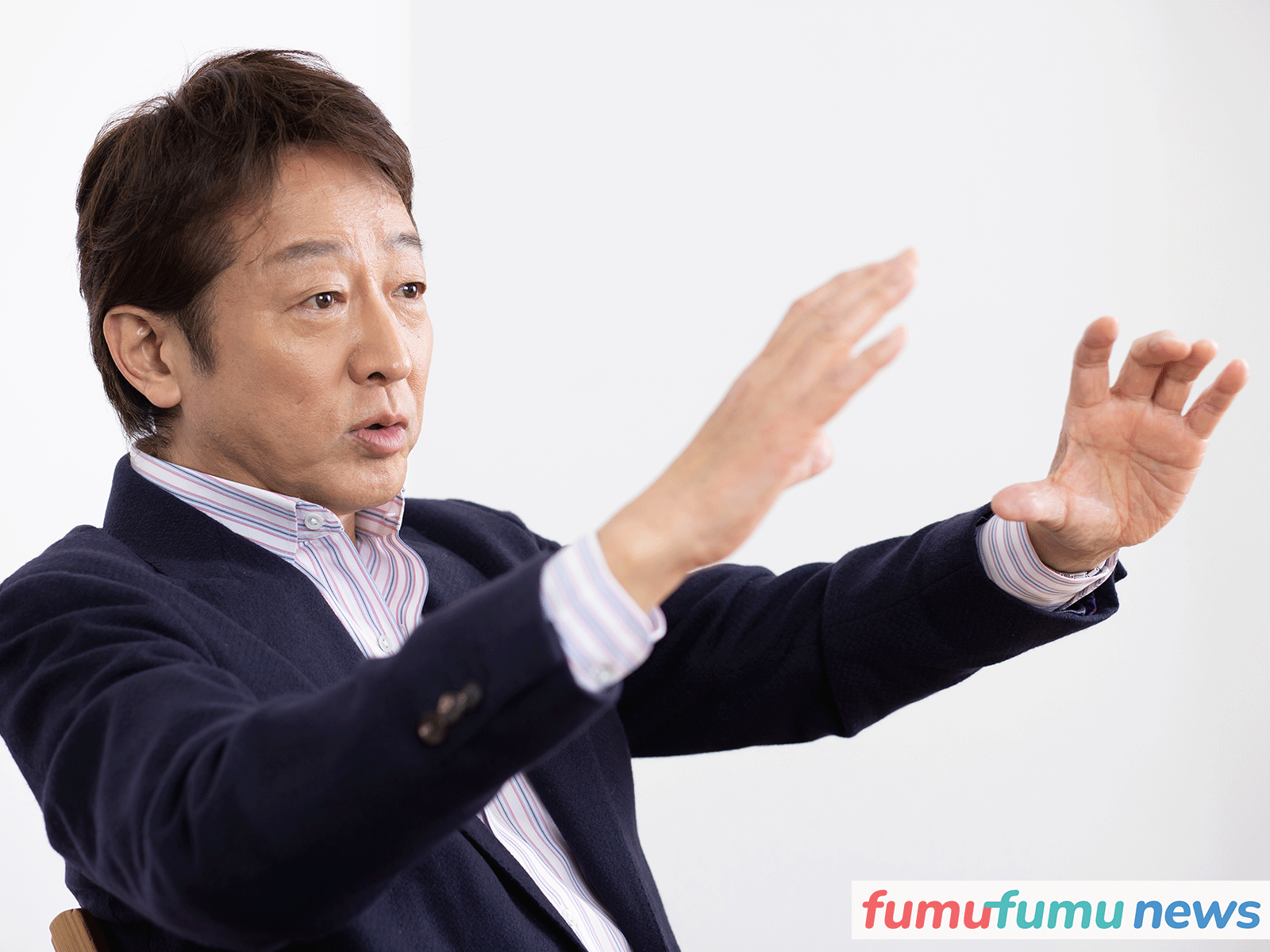
──座長になってからは、どのような活動をしていましたか?
「4回生のときに、京都・烏丸御池に100人ほど収容できるアトリエ(劇場)を構えたんです。学生劇団として自分たちのアトリエを持ったのは、『劇団そとばこばち』が初めてだと思います。京都中の不動産をみんなで手分けして回って物件を決めて、寄付や劇団員からの団費で運営していました。内装や電気工事も全部、自分たちで手がけたんですよ。天井を落として、アスベストまみれになってね(笑)。劇場があれば、いつでも稽古もできるし泊まることもできる。学生たちが劇場を持つなんて、東京にいたらできなかったと思います。
自分たちにとっては、アトリエで毎月行う新作公演が大切な活動でした。出演料も1ステージあたり1000円ほど出して、本格的にやっていたつもりです。劇場が空いているときには、一般に貸し出したり、ダンス教室や映画の上映会を開いたりしていました」
──’80年代は『小劇場ブーム』と呼ばれるほど演劇界が盛り上がったそうですが、同世代の劇団との交流はありましたか?
「年代的には、野田さん(劇作家の野田秀樹・元『夢の遊眠社』主宰)が先輩で、鴻上尚史さん(元『第三舞台』主宰)が同い年。夢の遊眠社が出てきたとき、うちは『西の遊眠社』と言われて比べられたりしました。向こうが東大で、うちは京大でしたからね。関西方面では大阪芸大のメンバーが旗揚げした『劇団☆新感線』が出てきたり、同志社大学の『第三劇場』を母体にして、マキノノゾミさん主宰の『劇団M.O.P』が誕生しました。こんな感じで、’80年代前半はまさに関西で学生演劇ブームがきていたんですよ。そのブームの中心にいたのが、『劇団そとばこまち』だったんです」
麻雀からは「人生観を学びました」、3留を経て卒業し、本格的に俳優業へ
──『劇団そとばこまち』はとても勢いがあったのですね! 演劇を続けるには、お金もかかりそうですが……。
「ひとり暮らしもしていましたし、さすがに収入なしでは厳しかったので、演劇の合間に塾講師や家庭教師のアルバイトをしていましたね」
──演劇やアルバイト、そして勉強や趣味活動なども含めて、大学生活は充実していましたか?
「楽しかったですが、自由にしていると人間、どんどん堕落するっていうことを身をもって実感しました(笑)。学生時代は、ほとんど芝居と麻雀しかしなかった。でも、麻雀から人生観を学びましたよ。流れに逆らっちゃダメだとか、逆に、流れに乗っているときは勝負に出るべきとかね。『麻雀放浪記』を書かれた阿佐田哲也さんの名言に、“麻雀を点棒のやりとりだとしか思えない人は永遠に弱者である。麻雀は運のやりとりなんだ”っていうのがあって、共感しています。当時はヨレヨレになりながら朝までやっていたんですけれど、考えてみれば、ムダじゃあなかったのかもしれません」
高校も大学も、自由放任主義の学校だったのがありがたかったです。その分、自分のことは自分で決めなくてはならないから、大変な面もありますけれど。でも、学生のうちに自らの意思でやりたいことを見つけるっていうのも大事なこと。そういう環境で過ごしたから今、世の中からちょっとドロップアウトして、こういう仕事をしているみたいなところはあると思います」
──自由に過ごしすぎて、両親から叱られたりしませんでしたか?
「うちは父方の親戚が父以外、みんな医者だったんです。祖母からも小さいころから“医者になれ”と言われて育った。だから、もし浪人していたら、医学部を目指していたと思います。全く別の人生を歩いていたでしょうね。
ただ、親も芝居好きだったから、高校時代から芝居に没頭していることについては、とやかく言われなかったんです。でも、大学で留年してからうるさくなりました(笑)。周りから、“息子さん、今年で卒業だろうけど、どこに就職したんですか”って聞かれていたみたいで。留年1年目はまだよかったんですが、2年、3年ともなると、親にもメンツがありますからね。自分自身はあんまり気にしないほうなので、深刻に考えず、“なんとかなるだろう”って思っていました」
──大学卒業後、就職はしたのですか?
「3年も留年しましたから、そもそも就職先を見つけるのが難しかったんですよ(笑)。それに、7回生のときにNHKの朝ドラ『ロマンス』のオーディションに挑戦して、大役をいただけることになったんです。それで卒業と同時に、役者として本格的に活動を始めました」
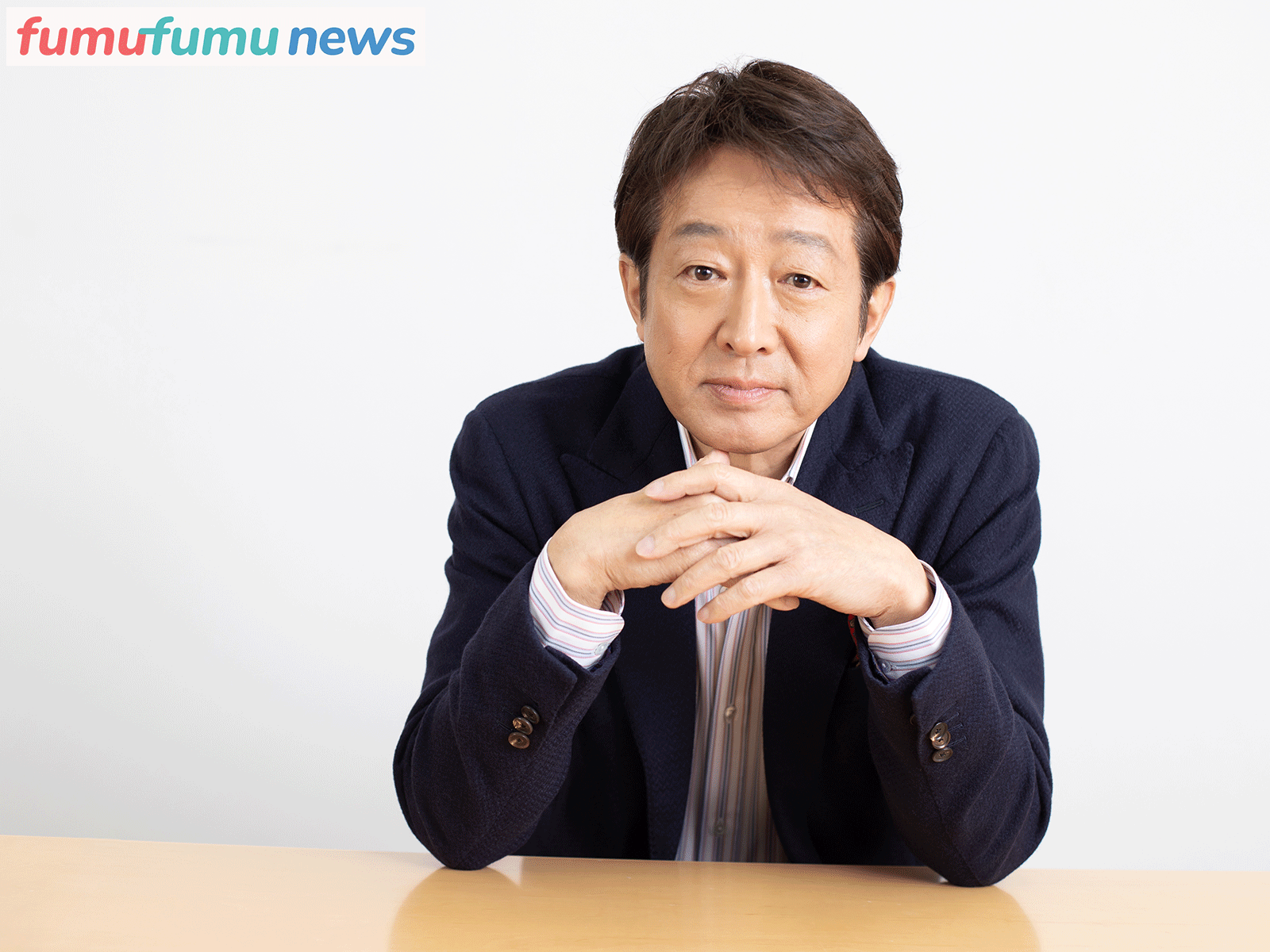
京大に入学しつつも、勉強よりも演劇にのめり込んでいったという辰巳さん。大学卒業後には、俳優業をスタートさせます。インタビュー第2弾では、朝ドラ『ロマンス』での全国区デビュー、クイズ番組への出演などについて詳しくお聞きします!
(取材・文/池守りぜね)
【PROFILE】
辰巳琢郎(たつみ・たくろう) ◎1958年、大阪市出身。大阪教育大学附属高校2年生のとき、つかこうへいの舞台に感銘を受け芝居を始める。京都大学文学部在学中は、関西では人気・実力ともにNo.1の『劇団そとばこまち』を主宰し、役者としてだけでなく、プロデューサー、演出家として’80年代前半の学生演劇ブームの立役者となる。卒業と同時にNHK連続テレビ小説『ロマンス』で全国区デビュー。以来、知性・品格・遊び心と三拍子そろった俳優として、テレビ、映画、舞台、バラエティと多岐にわたって活躍している。’23年3月には舞台『鋼の錬金術師』に出演予定。
◎テレビ番組『辰巳琢郎の葡萄酒浪漫』BSテレ東にて毎週日曜23:00〜23:30
◎テレビ番組『辰巳琢郎の家物語 リモデル★きらり』BS朝日にて毎週土曜12:00〜12:30
◎舞台『鋼の錬金術師』
〈大阪〉2023.3/8〜3/12@新歌舞伎座、〈東京〉2023.3/17〜3/26@日本青年館ホール
辰巳琢郎はキング・ブラッドレイ役にて出演! 詳細は公式HPへ→https://stage-hagaren.jp/
☆辰巳琢郎公式HP→http://www.takusoffice.jp/
☆辰巳琢郎公式Facebook→https://www.facebook.com/tatsumitakuro.official