第1弾では、小学校時代に場面緘黙症(ばめんかもくしょう)で苦しんでいた際、先生とクラスメイトから受けた“とある仕打ち”について振り返ってくれました──。
休み時間が怖い。
みんなが急に話し出す。校庭で騒ぎ声が聞こえる。私はその中に、入りたくても入れない。小学1年生からの6年間、ずっとそうだ。
言語能力は正常で、家の中や学校の授業で先生にあてられたときは、ほかの人と同じように話せるのに、休み時間や放課後になると話せなくなる。「なんで話さへんの?」と聞かれても、時にそれをクラスメイトから責められても、答えられなかった。私も理由がわからなかったからだ。
これが、場面緘黙症という症状であることを私が知るのは成人してからで、このときは自分で自分を「ほかの子とは違う変な子」としか受け止めていなかったし、周囲もそうだったと思う。
言語能力は正常であり、家では問題なく普通に話すことができるのに、特定の状況(例えば、幼稚園や学校など)においては声を出して話せないことが1か月以上続く疾患で、選択制緘黙症ともいう。話す必要があると感じても話すことができないほか、身体が思うように動かせず、固まってしまうことも。500人に1人ほどの割合で発症するといわれており、5〜10年以内に改善することも少なくないが、慢性化して成人になっても症状が続く場合もある。
先生だけが唯一、自分を理解してくれる存在だと感じていた
同級生に「ほかの子はなんで普通に話せるん?」と聞きたかったが、話せない私にとってはそれも不可能だった。ほかの子は、反対に私にこう聞きたかっただろう。
「授業中とか家では話せるのに、どうして休み時間になると話さなくなるの?」
「話せるのに話さないんや」と同級生たちは思い、それは、いじめというかたちで向かってくることもあった。声を出すよう強要されたこともある。5、6年生になったころ、休み時間になるたびにひとりで読書する私の様子を見かねた先生が、「みんなと外で遊ぼう」と声をかけ、私を校庭に連れて行くこともあった。
(クラスでの孤独な日々や、声出しを強要された経験については、以前のコラムで詳しく描写しています→記事:学校でどうしても話せない──「場面緘黙症」経験者の苦しみと“いま伝えたいこと”)
とはいえ、私は校庭を駆け回る同級生の輪に入れないし、入る勇気もない。先生は、私のことを何も知らない下級生が花いちもんめをしているのを見て、「みんなでやろう」と私を招き入れた。
背の低い低学年の子たちの中に、ひとりだけ背丈のある私が混ざっている状態は、はたから見たら変だったと思うが、花いちもんめは楽しかった。先生だけは、私のことをわかってくれていると感じた。
今もなお心に残り続ける、“正しさ”という名の刃
しかしある日、その気持ちは、ぐしゃぐしゃになった。
先生は私を理解しようと努めた。それだけではなく、私のクラスメイトたちに、私のことを「理解させよう」とした。
あの日のあの時間だけ、記憶は鮮明で、今も思い出すと刃になって私に向かってくる。場面緘黙症の症状がなくなったのは12歳のときだったが、あれから30年以上たっても、その刃の鋭さは変わらない。
きっかけは、先生から原稿用紙をもらったことだった。先生はやさしく言った。
「あなたが何を思ってるか、ぜんぶわかってあげたい。だから書いてくれへんかな」

文章を書くことは好きだったし、実際に自宅で自分の気持ちを言語化して文章にしてみると、自分では思ってもみなかった言葉がするすると出てきた。
「話せないけど、友だちがほしい」
そうだ、これが私の本心なのだ。
自宅で勉強机に向かい、ひたすらに自分の気持ちを文章にした。話せないせいで、クラスのみんなと友だちになれなくてつらいこと、話せないことが理由でいじめられて苦しいこと……。書く内容はどんどん出てきて、先生にもらった5枚くらいの原稿用紙のマスは、すぐに埋まった。
先生が私を理解しようとしてくれる気持ちがうれしかったし、先生がどんなふうに返事をしてくれるんだろうと思いながら、次の日の休み時間に、文字で埋め尽くされた原稿用紙を渡した。先生は目を通したあと、少し泣いた。そして言った。
「これ、みんなの前で読むね」
一瞬、何を言われているのかわからなかった。
いま、言葉で表すなら、頭が真っ白になったのだと思う。だんだんと先生の口にした内容が脳にしみこみ、先生に対する信頼は恐怖に変わった。
「いやです」
せっかく授業以外で声が出せたのだが、泣いている先生はそれすら気づかず、自分がしようとしている「正しいこと」に夢中だった。
「あかん。あなたが苦しんでること、みんなに知ってもらわないと」
涙があふれて、もう一度、先生の袖口を引っ張って「いやです」と言ったが、先生は私を振り払い教卓の前に立ち、授業開始のチャイムが鳴るのを待った。チャイムと同時に、クラスメイトたちが席についた。
「みんな、今日は勉強よりも聞いてほしいことがあるねん」
私の作文を先生がひたすらに読む時間が始まった。先生は要約もせず、作文の内容をぜんぶ読んだ。教室は先生が話し始めてすぐ、静まり返った。
クラスメイトたちの顔を見るのが怖かったので、私は自分の机に戻り、突っ伏した。小さな音も聞こえなかった。
いやです、って言ったのに。
先生に、先生だけに理解してもらうために書いた文章だったのに。
先生が読み終えても教室は静かなままで、クラスメイトが何を考えているのか想像すると、胸がきゅっとした。
晴れた日で、窓から光が差し込んでいた。だけど、突っ伏したきりの私の視界は闇に包まれていた。
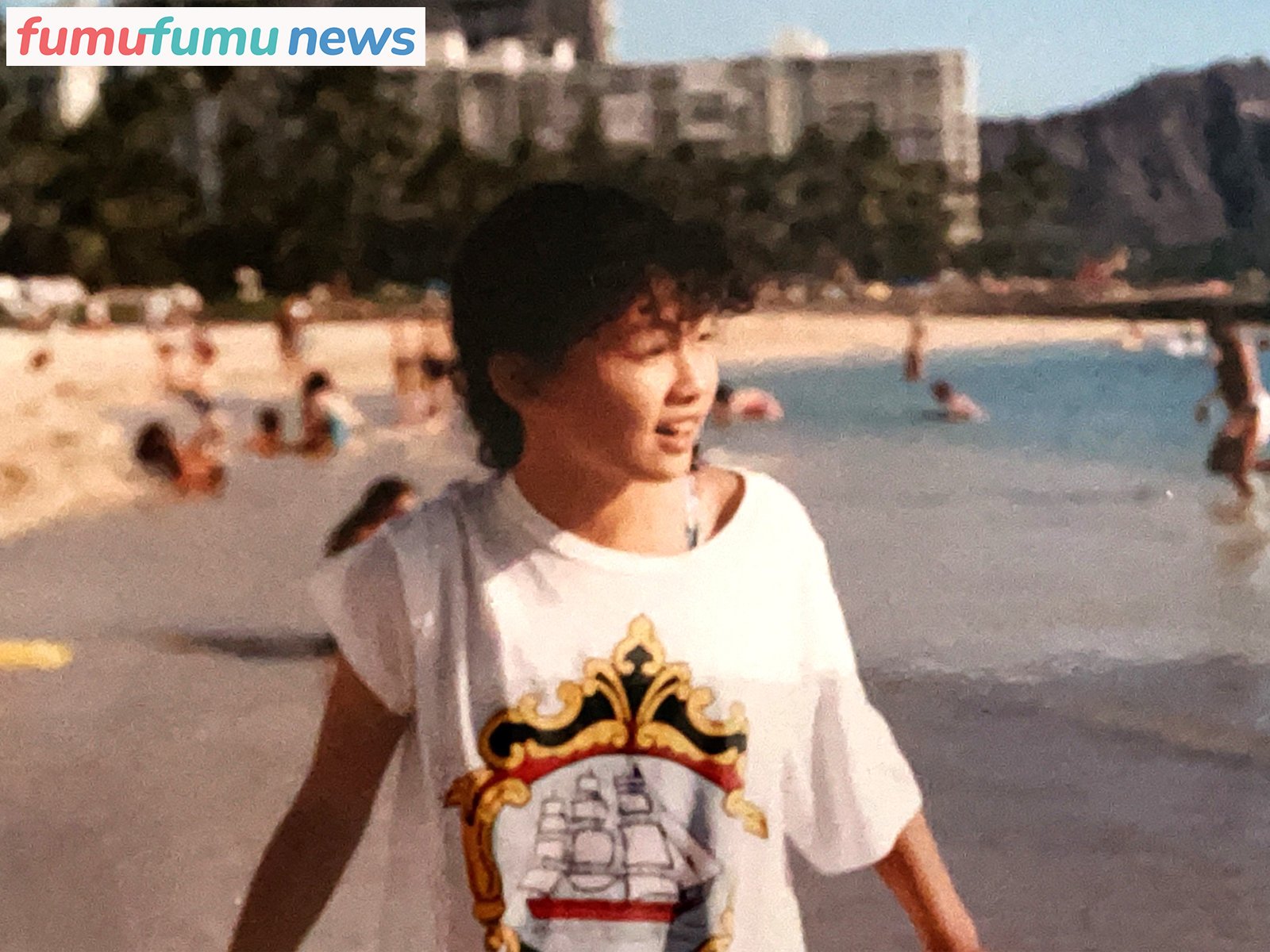
「みんな、クラスにこんなに悩んでる人がいるんです」
作文を読み終わったあとに先生が言った、この台詞までははっきりと覚えているのに、そのあとどうなったのかは記憶にない。なんとか最後の授業まで乗り切って帰ったのだと思う。親にも妹にも、このことは話さなかった。
このとき抱いた、「先生も私をいじめた人たちと一緒やったんやな」という私の感情は、30代半ばになった今も、私の心を揺さぶる。
「ありがとうございました」と、ひと言だけ残して去った
小学生の私は、ある確信を得た。
「きっと先生やクラスのみんなは正しいことをしている。ぜんぶ私が悪いのだ」と。
次の日からもクラスメイトの態度は一緒で、いじめてくる男子はこれまでと同じく、たたいたり、「なんで話さへんの」と怒鳴ったりしてきたし、女子たちが遠くでくすくす笑いながら「やめえや」と言うのも、変わらなかった。
先生は、昨日のことなんて忘れたように、いつもどおり授業をしていて、私が泣いたときだけ男子を叱った。
6年生の1学期の終わり、家族の引っ越しで転校することになった。もうひとり転校する子と一緒に、同学年の児童みんなが集まる6年生の会で、あいさつをするように言われた。話さないのではなくて話せないのに、あいさつなんてできるのだろうか。
集会では、もうひとりの子が、先生が満足するように泣いたり、「どこへ行っても、みんなのこと忘れません」と、感動するようなことを言ったりした。瞬時に先生がほしい言葉をプレゼントできる人は、たとえ子どもであっても頭がいいのだと思う。大人に好まれる言葉を選りすぐって残すのは、中学生になっても使える立派なスキルだ。
私の番になり、仕方なく立ち上がって周囲を見る。当時、大阪でいちばん児童が多い学校だったので、ひとつの学年だけでも少子化をまったく感じさせない人数だった。「ありがとうございました」と小さな声で言った。
同い年の子たちと5人の先生は、私の次の言葉を待っていたが、もう何も言葉を発する気になれなかった。
「言えない」じゃなくて「言わない」。
そのときの私は、「話せなかった」じゃなくて「話さなかった」。
でも、転校先の学校では話せるようになるかもしれない、と少しだけ胸に希望が宿った。

分かち合える人を増やすには? 答えの出ない“克服”のその先に
私の場面緘黙症が完全に消えたのは、中学校に入学したころだと思う。はっきりしていないが、会話のキャッチボールがとても難しかったことを覚えているので、そのころには克服していたのだろう。
克服が何を指すのかは、いまだにわからない。
中学生になった私は、会話に慣れていなくて、相手が答えるのを待たずに話したり、空気の読めないことを言ったりした。そんなことをしていたら、当然、嫌われる。中高一貫校に通っていた私は中学1年生の2学期から不登校になり、1年半、学校に行かなかった。3年生になってようやく通学できるようになり、一貫校だったおかげで高校に進めたが、出席日数は高校卒業までずっと、進級できるかどうかギリギリのラインだった。
いま考えると、小学生時代の場面緘黙症を、いつでもどこでも話せるようになった中高生以降も引きずり続けていたのだ。不登校に対しても理解のない時代であったが、こらえて大学は離れた場所にあるところを選び、なんとか10代を生き抜いた。
小学生だったあの日、先生は私のつらさを理解してもらえるように、苦肉の策でクラスメイトに作文をさらしたのだろう。
だが、それ以外に方法はなかったのだろうか。
理解してもらえる人、分かち合える人を増やす。それは、どうすればできるのか。
すぐに答えが出ないかもしれないが、私は考えている。
できるなら、記事を読んでくれているみなさんといっしょに、この問いの答えを考えていきたい。
(文/若林理央)








