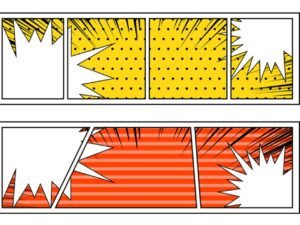週末などに美術館に行く方はわりと多い。人生で一度も美術館やギャラリーに行ったことがないという方は、ほとんどいないでしょう。しかし、こう……なぜか敷居が高そうなのか、漫画や映画に比べて、どっぷりハマる方っていうのは少ないんです。
私は今、休日に絵を描いてみたり、美術検定を取ってみたりしています。しかし、以前はぶっちゃけ、美術館で作品の前に10秒くらい立ち止まり、腕を組んで作品を眺めてみても、ほぼ何も感じなかったんです。ゴッホの絵を見ながら「……やっべ、腹減った。こってりしたハンバーグ食べたい……」とか思っていました。一応、TPO的に眉間にしわを寄せてはいた。やたら小難しそうな顔で、晩ごはんのことを考えていたんですね。
でも、西洋美術史をちょっと調べてみると、美術館での体験がガラッと変わりました。今までわからなかった作品の背景が見えてきたためです。すると作者の考えがわかってきて、理解が深まる。理解できると「この絵を描くのにも死ぬほど苦労したのね、この人」と、めっちゃ感動できるんですね。
ただ、世の中の美術解説本は、この境地に至るまでが難しい。いきなり、本で歴史を調べて知識をがっつり身につけるのは、けっこう覚悟や体力がいります。そこで、この連載では「西洋美術史的に有名なところ」を”おしゃべりする”くらいの感覚で、ざっくり解説しちゃいます。
今回は1910年代からブームになる「ダダイズム」と「シュルレアリスム」についてご紹介します。後者はお笑いなんかでよく聞く「シュール」の語源になった言葉です。鋭い方であればピンとくるかもですが「超不思議ちゃんの集まり」です。ここでは、この時代のきてれつ天烈な作品はどうしてできあがったのかを、勇気をもって見ていきましょう。
ダダイズムが目指した「考えるな、感じろ」的な精神
「ダダイズム」は1916年にスイスで始まった芸術運動です。ほぼ同時期にヨーロッパ各地やニューヨークでも発生しました。
「ダダイズムって何なの?」を説明するために、まずは時代背景を紹介させてください。1910年代のヨーロッパ、アメリカといえば「第一次世界大戦」。史上最大規模の戦争で、当然、芸術家たちはもう活動どころじゃない。世間の雰囲気も、どうも暗い……みたいな時期でした。
そんななか、アーティストたちは一時的に中立国・スイスのチューリッヒに集まります。なかでも「キャバレー・ヴォルテール」というキャバレーには詩人や画家、彫刻家などが集まって「いやマジで戦争だるいわ。気持ちがもう沈みっぱなしよ……」みたいな話をしていました。
そして芸術家たちは「人間が理性とか論理に偏ったから、第一次世界大戦が起きたんやんけ」という結論にたどり着きます。そもそも「戦争をして植民地を広げて利益をあげて国を拡大する」というヤバい思考は合理主義が極まったからこそ生まれたわけで、それを否定しなきゃならんよな、となったんですね。
それで、ダダイズム(以下:ダダ)が掲げたテーマが「理性の破壊」です。ざっくりいうと、ブルース・リー主演の映画『燃えよドラゴン』の名ゼリフ「Don’t think, Feel(考えるな、感じろ)」って感じ。とにかく、何かを表現をする際に理屈とか論理があっちゃダメよ、って叫んだんですね。すんごい極論ですけど、シンプルでわかりやすいですよね。
例えば「観客に自由の大事さを感じてもらいたい! だから大空を飛ぶ鳥を描いた」とか、もう完全にアウト。「そういう論理的な思考が争いを引き起こして、世間が暗くなるんよ!」と怒られます。
そうしたら、当たり前ですけど「超カオス状態」になりますよね、ええ。「ステーキを切って食べやすいサイズにしたい」と考えたとき、論理的には「ナイフ」を作るでしょ。でも、ダダの思考では「ステーキを切りたい。よし、確定申告しよう!」みたいな、何のロジックもないことをしでかして、その「カオス」をニコニコして受け入れるんですよ。
「ちょ、なに言ってんの?ナイフ作れよ」と思ったあなたは安心してください、正常です。しかし「肉を切るためにナイフを作る」というロジカルシンキングが戦争に発展しかねないとされたんだから、これはもう破壊するしかないんですね。
ちなみに「ダダ」という名前は、創始者のトリスタン・ツァラが名前を決めるときに、辞書にペーパーナイフを適当に刺して、そこに「ダダ(ドイツ語で『木馬』)」という単語があったから決まったらしいです(諸説あり)。論理性を省きたいから、もう偶然に身を委ねるわけです。
「アートとは何ぞや」を本質から問うた傑作「泉」
もちろん、これまでの芸術作品は、論理的な理由があるものがほとんどです。感動させたいからキレイな風景画を描くし、発注者の家に飾るために似せた肖像画を描く。でも、それらはダダイストからしたら”ガラクタ”なんですね。だからニューヨークのダダイスト・マルセル・デュシャンは「反芸術」を掲げるんです。
そんな彼は1917年に自身が展示委員をしていたニューヨークの「アンデパンダン展」で大スキャンダルを起こします。アンデパンダン展とは「出品料さえ払えば誰でも無審査で出展していいよー」という趣旨の展示会のこと。つまり、基本はどんな作品でも受け入れるんですね。
そこに『Fountain(泉)』というタイトルで、TOTO製品並みにどこにでもある男性用小便器を出品します。署名には自身の名前ではなく「R.Mutt」と書かれていました。

これは西洋美術史上で最高レベルの「事件」で、事実、2004年にイギリスでおこなわれた「500人の芸術専門家に聞いた『もっとも影響力のあるアート作品ランキング』」では1位を獲得しました。この作品は決して「アイディア浮かばなかったから、もう奇をてらっちゃおっかな~」ではないんです。ちゃんとダダイズムの考えにのっとっていました。
「便器」はレディメイド(均一的な形で大量生産された製品)で、「用を足す」ために作られたものですよね。でも「きちんと台座に載せて展示会に出す」ことで、便器は本来の役目を失って「完全に意味のないもの」となります。これは「論理的思考をぶっ壊す」という、ダダイズムの価値観にぴったりでした。
さらに、この便器は「芸術の定義」を根っこから覆した意味でも偉大なんです。「芸術」って、なかなか明確に定義されないんですけど、なんとなくみんな「芸術家の思想や哲学が反映された、五感を通して魅力を感じるハンドメイドの作品」だと思っていました。
その点、『泉』は真逆。大量生産された小便器で視覚的にちょっと不快だし、デュシャンの署名もなく、作者の思考は完全に排除しています。つまり「完全に何の変哲もないただの便器」なんですよね。
その結果『泉』は「何でもOK」のはずのニューヨーク・アンデパンダン展から出品を許されませんでした。「ちょっとちょっと。汚いんですけど!」とか「いやいや作品じゃなくて、これパクリじゃん」などと怒られたわけですが、確かに、その気持ちもわかります。
ただ、デュシャンは「そもそも、なんで芸術って1点もので、作者性があって、魅力的なものじゃなきゃいけないんすか?」と、軽々と宣言してのけました。これ、私はハッとしました。もう「ハッ」って言いましたもん。ダダイズムの「論理的思考の排除」があったからこそ、常識を疑うことができたんだと思います。
ここから「芸術の概念」は広がり、自由になっていきます。ポップアートや現代アートが出てきて、今でも「芸術の定義とは?」と解釈され続けている。こうした背景から『泉』は、アート史上MAXレベルで影響力のある便器として知られているのです。
ダダイズムからシュルレアリスムへ
そんなダダイズムの思想を引きつぎ、さらに深めたのが「シュルレアリスム」。前述した「シュール」の語源です。「あの芸人ってシュールだよね~」「わかるわ~、マジ世界観強め」という感じで、たびたび使われますよね。
シュルレアリスムは、ダダイズムの中心メンバーだったアンドレ・ブルトンが始めました。彼は医学生のころ、兵士が心の病で入院する戦争病院に勤めていました。そこでフロイトが唱えた「精神分析学」を知ります。
フロイト精神分析をざっくりいうと「人間は意識している部分より圧倒的に無意識の領域が多いんだよ~。だから、無意識下にある感情や記憶を意識化して治すのが大事だよ~」という治療技法の体系です。

ブルトンはこの「無意識」に目をつけるんです。意識できているものは理性によって”飾られた”ものであり、実は「理性の奥にある無意識こそ、何も着飾っていない人の本質だ」と考えたのです。
さらに「理性を取り外すと自由になれる」とも考えました。意識上だけだと、思考にリミッターがかかる。例えば「犬の絵を描いてくれ」と言われたら「四足歩行の獣」を描くでしょう。これが思考にリミッターがかかっている状態。「犬といえば四足歩行」という意識を取り払うと、自由に発想できるのです。
つまりシュルレアリスムの思想は「みんな理性のフィルターを外そうぜ! そうすれば真の自分の姿で、もっと自由に生きられるよ」というもの。ダダイズムの思考に近いですが、微妙に違います。だから、シュルレアリストはおのおの「無意識を作品に反映する方法」を探るんですね。
アンドレ・ブルトンは、とにかく高速で頭に浮かんだ言葉を書きまくる「自動筆記」という方法で詩を書きました。私が今やってみるとこんな感じ。
「ガチャピンが『明日やっと阿蘇山に登るぜ俺』と絶叫していたらしいが全員聞いておらず、ただ漫然とカルタをしながら次元大介を前にした緊張感のなか、ミジンコが住民票に印鑑を押すのを見ていた」
……おい、こいつ急にどうした、とか思わないで。自動筆記は誰がやってもこうなるんです。コレ、自分の内面を教えるみたいでちょっと恥ずかしいんですが、まあ私の無意識の領域にはこういう人や物があるわけです。確かに、紅白でけん玉するムックを見たし、正月にカルタできなかったし、ちょっと引っ越し考えてるし……うん、なんだかうなずける結果である。ぜひ、みなさんもトライしてみてはいかがでしょう。今、自分の内面を何が支配しているかがわかって、おもしろい遊びです。
ちなみに、このほかにも方法があって、例えばサルバドール・ダリは「夢に無意識が反映される」と考え、夢で見た光景をキャンバスに落とし込んでいました。キャンバスの前でスプーンを持って眠り、うとうとしてスプーンを落とす。その音で起きて、まどろみのなかで見た光景を描いていたんですね。ダリに関しては、以前の記事『ダリはなぜ”完璧な奇人画家”に仕上がった?「3大コンプレックス」から紐解いてみた』のなかで紹介しているので、ぜひお暇なときにでも。
そのほか、シュルレアリスムには、まったく関係ない組み合わせを配置する「デペイズマン」とか、石や木片といった物体のうえに紙を置いて鉛筆などでこする「フロッタージュ」といった技法があります。どれも「意識的に作ること」を徹底して排除しました。
シュルレアリスムを「許すこと」と解釈してみる
ダダイズム同様、シュルレアリスムの作品はもう全部、はちゃめちゃです。それは、理性のフィルターを通していないし、論理的なことを否定しているから。「1+1は?」と聞かれて「もみあげ」と答えてもおかしくはない。そりゃもうわけがわかりませんが、すべてを「受け入れる」というのがシュルレアリスムのミソです。
前述したダリの得意な表現に「柔らかい時計」があります。しかし「こんなにぐにゃぐにゃした時計、時間がわかんねぇよ」と言う人は誰もいません。

作品に対して「いや、ここの色合いはもっとこうしたほうが……」とか「パーツがズレてる……」とか、そういう問答をすること自体が無意味なんです。なぜなら、シュルレアリストの思想に「魅力的に見せよう」という気なんてなく、ただ自分の本質(とだけ向き合っている)からです。
私はシュルレアリスムについて「どんなに(世間的に)おかしなことも、ぜんぶ許して認めてあげること」と、ちょっと拡大して解釈しています。すると鑑賞者自体も「自由」になれるんですよね。
例えば、「この色のほうがいい」や「この線の引き方が甘い」といった見方をする背景には、「鑑賞者自身の人生」が反映されていると思うんです。「生きてきたなかで覚えた自分の常識」があるからこそ、何かを否定する。これはある意味で「呪われている」といってもいいかもしれません。
私は、シュルレアリスムの姿勢ですべてを受け入れることで、呪いがリセットされる感覚があるんですね。あくまで個人的な解釈ですが、この「優しい世界」がシュルレアリスムの魅力だと思っています。
アートが「生き方」まで拡大した20世紀初頭
ダダイズムとシュルレアリスムはもはや技法や画法という領域ではない。哲学とか生き方とか、そういう話なんです。この時代からアートは技法だけでなく「人の生き方」まで昇華したのだと思います。
個人的には「今まさに、ダダイズムやシュルレアリスム的な考えが人を救うんじゃないか」と考えています。数年前からコンプライアンスが厳しくなり、芸能人は今まで以上に世間のイメージを気にするようになりました。一般人も毎日のようにSNSから刺激を受けて「周りからどう見られているか」という、パブリックイメージを気にしてしまうことがあるかもしれません。
他人を意識して「自分のイメージに反したくない」と思うと、自由がどんどん制限されていってしまいます。すると、やっぱり疲れてしまうことがあるかもしれません。その根底にはすべて「理性」が存在しているんですね。人間に備わっている「理性」はとても便利ですが、たまーにハンパじゃなくめんどくさい存在になります。「あれをすると角が立つし、これをすると嫌われるかもしれないし……」と、がんじがらめになることもあるでしょう。
そこで、シュルレアリスムの精神が役に立つのではないか、と。いったん、いろいろ考えるのをやめて、自分の感覚で動いてみるのも大事です。とはいえ、常に理性を失うと「シンプルにヤバい奴」になります。だから、あくまで「たまには」理性を取り払って、周りの目を気にせずに生きてみるのもいいのではないでしょうか。
(文/ジュウ・ショ)